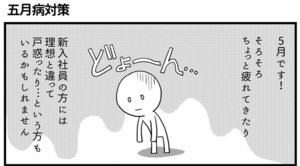新入社員や学生を中心に、大型連休明けに倦怠感や疲労感などの症状が出る「5月病」。ここ数年は、5月病と併せて「6月病」という言葉もよく聞かれるようになった。
環境が大きく変わる春を経て、連休が明けて祝日もない中で働き続けなければならない5~6月頃は、仕事の意欲低下や職場での人間関係のトラブルなどの問題を抱えやすく、早期離職なども増えがちだ。
5月病の認知度は世間的にも高い一方、多くの人が実践しやすい具体的な対策などは意外と知られていない。そこで今回は、そんな5月病や6月病の傾向と対策について、統合医療クリニック「ハタイクリニック」院長・西脇俊二氏にうかがった。
医学的に見た「5月病」「6月病」とは
そもそも、「5月病」「6月病」はどちらも正式な病名ではない。西脇氏によれば、そうした心の不調を訴える人には適応障害や気分障害という診断がつけられることが多いという。
「適応障害は気分障害の手前の段階で、適応障害が進行していくと気分障害になります。気分障害とは、日常生活に支障をきたすレベルで気分が変動するというもの。うつ病や双極性障害がこれに含まれます。うつは慢性的な疾患で、6カ月以上持続するというのが一応の診断基準です。適応障害は昔で言う抑うつ神経症。環境の変化などにストレスを感じ、それに適応できず様々な心身の症状が出てしまうというものです。そもそも違う病気ということで昔はこの2つは分けられていたんですが、今は混同されがちです。実際、その境目は曖昧なのですが、症状や効果的な治療法などに関しては微妙に違う部分もあります」
神経症という言葉はWHOの診断基準ICD-10に残っているが、現在は診断名としてはあまり使われず、不安性障害などの言葉に置き換わっているそうだ。
うつ病などと比べると適応障害という病名は一般的ではないが、5月病のような症状に心当たりがある人でも、自分でうつ病だと決めつけるのは尚早と言えるだろう。
「抑うつ神経症(適応障害)の方は、ストレスの原因が少ない休日は割と元気というパターンも多いです。温泉に行くなど、レジャーによる気分転換もおすすめできますね。平日に関しても、疲れが出る夕方以降に症状が現れやすい。逆に、典型的なうつ病の方は『今日も1日を過ごさなきゃいけない』といった感じで特に朝の調子が悪く、1日が終わる夜は比較的ラク。温泉なんかに行く気力がそもそもないし、無理に行っても楽しめないので家で休んでいたほうがいい。また、抑うつ神経症の場合は、気分障害ほど抗うつ薬が効かず、どちらかというとデパスやレキソタンなどの抗不安薬のほうが効果的な傾向があります」
心当たりのある人も多いだろうが、適応障害の具体的な症状としては「やる気や集中力が低下して仕事の効率が落ちる」「焦燥感によるイライラや不安」「倦怠感」などが挙げられる。
「適応障害になることで、仕事を先延ばしにしがちになってしまったり、仕事がどんどん溜まって余計なストレスが高まったりということも起こり得ます。常に緊張状態なので睡眠も浅くなり、寝ても疲れが取れないため、結果的に適応障害でも朝がすごくつらくなる。あとは、動悸やめまい、肩こり、便秘、下痢、食欲低下などの自律神経症状ですね。鬱に悩む人だと、好きな食べものも美味しく感じなくなり、“砂を噛んでいるみたい”と言う人もいます」
5月病や6月病というと新入社員や学生がなるイメージも強いが、きっかけは様々で管理職などベテラン社員も他人事ではない。
「部署替えや昇進のストレスが原因で鬱になる人も少なくないです。5月・6月に限らず、緊張から解放されたタイミングで急に鬱になる人もいて、母親世代だと子どもの大学入学や結婚による“荷下ろし鬱”などもあるんです」
5月病・6月病になりやすいタイプ
そんな中でも、特に新入社員が5月病・6月病の症状に悩まされやすいのはなぜか。西脇氏は2つの要因を分析する。
「一般論として、仕事ができない新人の時って、達成感を得にくいんですよね。人の脳には『報酬系』という回路のようなものがあるんです。達成感を味わうことにより脳内でドーパミンやセロトニンが分泌されて、気持ちよくなるからまた頑張れる。本当はその繰り返しで仕事をしなければいけない。セロトニンなどの神経伝達物質が足りない状態は、うつ病の原因にもなります」
「また、多くの新入社員は自己重要感(承認欲求)も満たされにくいでしょう。人には生存本能の次に自己重要感を満たしたいという欲求があり、時にはそれが生存本能より上位に来ることさえあります。一番の虐待はネグレクト・無視とも言われますが、新入社員は『私は必要ないんだ』みたいなネグレクトに近い状態になりやすい。新人に限らず『ありがとう』と言い合うとか、名前で呼び合うというのは、その人の自己重要感を満たす上ですごく大事なんですね」
近年、入社早々退職する新入社員も定期的に話題になるが、そうした早期退職者の中でも適応障害のような症状が出ているケースはあるらしい。適応障害になりやすい性格や職場環境も存在するとのことで、西脇氏は以下のように解説する。
「発達障害傾向の方、性格的に完璧主義な方は要注意ですね。自閉症、アスペルガー、ADHDといった発達障害の傾向を抱えている方は、もともと現代社会で適応が難しいので人一倍ストレスを抱えやすいんです。例えば、普通の人も通勤時の電車はつらいものですが、自閉症の人はストレスがかかると五感の過敏さが増すので、すし詰め状態の満員電車は触覚的にも嗅覚的にも最悪。優先順位をつけるのも苦手で、会社での人付き合いや急な仕事に対応することへ強いストレスを感じ、人一倍頑張ってヘトヘトになる」
様々な企業で個々の仕事量が増えているのも事実だろうが、自分だけやたら残業が長い、休日出勤が多いという人は、発達障害の可能性を疑うことも大切かもしれない。「会社に障害を隠した状態で働いている」「周囲からなかなか理解してもらえない」という悩みを抱える発達障害当事者も多い現代では、支援団体などの数も増えてきている。
「正しい/間違い、好き/嫌いとはっきり分けたがる完璧主義も、実は発達障害(自閉症)の方に多い。完璧な人なんていませんし、当然、完璧主義な人自身も完璧じゃないので常に不満や不安を抱えることになります。完璧主義は真面目とほぼ同じ意味ですが、なんでも全部自分でしっかりやろうとして、どうでもいいことにも一生懸命なので、結局、人より仕事やストレスを溜めてしまいやすい」
「発達障害の方は二次性のうつ病にもなりやすいんですが、うつ病や適応障害の治療だけでは根本的な解決にはつながりません。グレーゾーンの発達障害は精神科や心療内科でも気づかれにくく、きちんと見抜かれていないことが一番の問題だと思いますね。二次障害で適応障害になっていて一次障害をなんとかしなればいけないのに、抗うつ薬を出してしまうとか。しかも、発達障害の方は薬の副作用が出やすく、薬が原因で余計に調子が狂うこともあります」
後編では、こうした症状に苦しむ人や周囲の人が心がけるべきポイント、個々ができる具体的な対策法を紹介する。

|
監修者
西脇俊二 (にしわき しゅんじ)
統合医療クリニック「ハタイクリニック」 院長
ハタイクリニックの院長として診療をしながら、メディア出演やドラマなどの医療監修、執筆など多数の分野で活躍中。著書に『自分の「人間関係がうまくいかない」を治した精神科医の方法』(ワニブックス)、『コミックエッセイ アスペルガー症候群との上手なつきあい方入門』(宝島社)など。YouTubeチャンネルの運営も行っている。