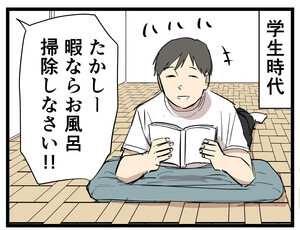◆本記事はプロモーションが含まれています。
【この記事のエキスパート】
三星舎 代表・鍼灸師・家庭料理家:調 香生子(Koko Shirabe)
学生時代の一人暮らしをきっかけに、SNSで朝ごはんの投稿を始めました。
鍼灸師として働きながら、健やかに丁寧に生きる豊かな暮らしと、健康づくりについて考えています。
影響を受けたのは、街の開業医に嫁ぎ「健康とは」と考え続けた祖母の健やかな暮らしの知恵。
衣食住に必要なすべてのものに歴史や風土の影響があり、物の本質を見抜けるようになりなさいという教えを大切にしています。
平成26年「日本の暮らし」をテーマに三星舎を立ち上げ、健やかな生活に欠かせない商品作りを始めました。
美味しくて身体に良い食べ物、調理道具、器など「家庭料理」にまつわる歴史や文化に興味を持っています。
本記事では、すり鉢の選び方とおすすめ商品をご紹介。溝のないすり鉢やおしゃれなデザインなどを厳選。人気の「もとしげ」やかもしか道具店の商品もピックアップしました。ユーザーのイチオシ商品や口コミもチェックできるので、ぜひ最後まで参考にしてください。
大きさや素材、デザインなどに注目!
すり鉢の選び方
すり鉢の選び方をおさえておきましょう! ポイントは下記のとおり。
【1】作りたいものに合わせてサイズで選ぶ
【2】すりたい食材に合う素材を選ぶ
【3】すりやすさで選ぶ
【4】注ぎ口や持ち手があると便利!
【5】食卓にそのまま出せるおしゃれなデザインも
【6】お手入れがかんたんなものがおすすめ
これらのポイントをおさえることで、より具体的に自分に合うすり鉢を選ぶことができます。
【1】作りたいものに合わせてサイズで選ぶ
すり鉢のサイズは商品によってさまざま。作りたいものや食べる人数に合う大きさを選びましょう。
すり鉢の大きさは「号(寸)」で表記され、1号は3cm程度。号数に3cmをかけたものがすり鉢の直径になるのでチェックしてくださいね。
ゴマすりや薬味、離乳食作りには「4~5号」がおすすめ
4~5号はお茶碗程度の大きさで、直径でいうと12〜15cmになります。ゴマすりやスパイスなどの薬味作りや、離乳食作りにのみすり鉢を使いたいという方は、このぐらいのコンパクトサイズがおすすめです。
置くときも場所を取らず、洗うときもすぐにきれいになりますよ。
とろろや和え物などを作るなら「6~8号」が便利
和え物やとろろなどをすりたいという場合は、6~8号サイズのすり鉢がおすすめ。直径だと18cm〜24cmぐらいありますので、ごまをするのはもちろん、そのまま食材をいれて和えることもできます。
このぐらいのサイズ感のすり鉢であれば、洗い物を減らせますし、どんな食材・料理にでも対応しやすいです。はじめてすり鉢を買う場合にも、使いやすくていいですよ。
【2】すりたい食材に合う素材を選ぶ
すりばちに使われる素材は陶器製が多く、ほかにも磁器、ステンレスや石でつくられたものなどもあります。すりたい食材に合うものを選びましょう。
幅広い料理に活用するなら「陶器」や「磁器」を
さまざまな料理に活用したいなら、スタンダードな陶器製がおすすめ。電子レンジに対応しているものなら、人参やカボチャなどの食材をチンして柔らかくしてからすりつぶすことができます。
磁器製はつるつるとして透明感のある白っぽい色味のデザインが多く、そのまま食卓に出して楽しめますよ。
スパイス類に使うなら「ステンレス」や「石製」を
にんにくや山椒、生姜などのスパイス類に使うなら、ステンレス製や石製がおすすめ。ステンレスや石製のすり鉢は、香りが強いスパイス類を入れて使っても匂いが残りにくいのが特徴です。特にステンレス製は、汚れを落としやすくサビにも強くて、お手入れが簡単です。
【3】すりやすさで選ぶ
すり鉢のすりやすさは、安定感がポイント。3つの要点をおさえて、すりやすいすり鉢を見つけてください。
ある程度の重さがあると安定しやすい
すり鉢が軽すぎると、手が滑ってしまい、中身ごとひっくり返ってしまうリスクがあります。そのため、ある程度の重さのあるすり鉢を選ぶと使いやすいですよ。すり鉢の重さは、号数×100gを目安にするのがおすすめです。たとえば4号なら400g程度、5号なら500g程度のものを選びましょう。
【エキスパートのコメント】
家庭用台所の調理台の多くは、ステンレスや人造大理石といったものでつくられています。そのため、すり鉢を使用している最中に「滑って中身をこぼしてしまった」ということも起こります。すり鉢の重量と底裏の加工を、きちんと確かめて選んでください。
まず、重量は重たい方が安定感があります。そのため無駄な力もかからず気持ちよくすることができますよ。
底面の滑り止め加工で安定感がアップ
すり鉢の中には、底裏にシリコンやゴムを使用した滑り止め仕様になっているものがあります。水に濡れやすくツルツルしているキッチンの作業台やテーブルの上で使う時には、滑り止めがあると安心。安定感がアップして使いやすいのも魅力です。
【エキスパートのコメント】
底裏の加工はゴムが貼ってあるもの、または素焼きのままザラザラしているものがあります。
ゴム底のものは、食卓で使うのには滑りにくいですが、調理台が濡れているときは滑ってしまいます。底のザラザラしたものは、ステンレスの調理台をキズつけてしまいます。とくに大きなサイズのものは負荷も大きくなりますので、注意が必要です。
不安定なときは、固く絞った台拭きを底に敷くと安定します。現代の台所は、昔ながらのタイル張りや板張りのものとはすこし事情が変わってきていますが、注意しながらすり鉢を選ぶといいでしょう。
すり鉢の溝の形状もチェック!
【エキスパートのコメント】
溝によってすりやすさや洗いやすさが変化
すり鉢の溝には「波紋」と「垂直」、そして一見してはすり鉢には見えない「溝なし」といったものがあります。
力をかけずに早くすりたいという方には「波紋」を、洗いやすさ重視という方には「垂直」をおすすめします。
どちらのすり鉢も、すりつぶしやすさを見極めるために手で触って、溝の作りがしっかりとしたものを選ぶといいでしょう。波紋は、左利きの方も使えます。垂直のものにも左利き用がありますので、購入前に確かめてください。
溝のないすり鉢は、「する」ことに加え、ポテトサラダや白和えなどといった「材料を潰す」のにもおすすめです。洗いやすく水切れもいいです。
【4】注ぎ口や持ち手があると便利!
すり鉢には、持ち手や注ぎ口がついている商品もあります。持ち手が付いていると、するときに手でおさえやすくて便利。さらに注ぎ口も付いていると、ドレッシングやソース、とろろなど液状の具材を注ぎやすくなります。
【5】食卓にそのまま出せるおしゃれなデザインも
さまざまなデザインのすり鉢が販売されています。食卓に並べる料理に合うデザインのものだと、デザインが統一されるのでおすすめです。たとえば、和食なら和風のどっしりとしたデザインのすり鉢を、洋食ならカラフルなものやサラダボウル感覚で使えるものがマッチするでしょう。
よく作る料理や食卓をイメージしながら、デザインにも注目して選んでみてくださいね。
【6】お手入れがかんたんなものがおすすめ
すり鉢は、食材をすりつぶすため、使ったあとは溝などが詰まってしまっていることもありますよね。その際は釉薬などですり鉢がコーティングされていると、食材が詰まりにくいので手入れがしやすくなります。
すり鉢をよく使用する場合は、食洗機対応のものを選ぶのもいいでしょう。ほかの食器とまとめて食洗機で洗えれば、手間も減ります。
選び方のポイントはここまで! では実際にエキスパートが選んだ商品は……(続きはこちら)