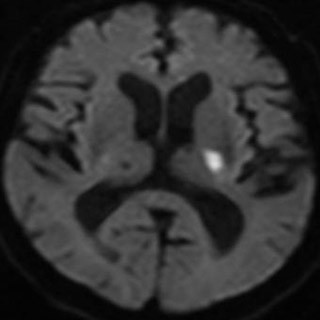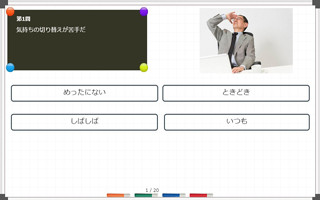回復期
続いて、回復期のリハビリでは以下のようなことを実施する。
(1)ベッドから起き上がったり、ベッドに座ったりする
(2)手すりなどを利用しながら立ったり、歩いたりする
(3)箸を持って食事をするなどの日常動作を行う
理学療法士や作業療法士、言語療法士、リハビリ専門の医師らがそろうリハビリテーション病院でより濃密な内容のメニューを行うのが回復期だ。リハビリ病院では、退院後の社会復帰や自宅での生活を見据えつつ、ケアマネージャーなども介入してトータルケアを行えるメリットがある。以前に比べて患者の利用度合いも増えてきているという。
維持期
そして最後となる維持期には、下記のようなリハビリを行う。
(1)「歩く」「歯を磨く」「着替えをする」などの日常生活全般を行う
すなわち、かつての自分ができていた行為をすること自体がリハビリになるというわけだ。
ただ、「維持」という言葉が示すように、現在出ている後遺症を維持期以降に劇的に改善させることは難しい。脳梗塞は発症後、3カ月~半年で症状が固定するため、回復期リハビリの期間も最大で「150日」と設定されている。個人差はあるものの、それ以降は後遺症の根幹となる部分が固定されてしまうのが一般的だ。
支える側の休息も重要
後遺症の程度は、発症した脳梗塞のダメージに比例する。リハビリがうまくいかなかなったときの患者のショックは計り知れないし、うまくいったとしても社会的地位が高かった以前のように戻れない患者もいる。そんなときこそ、家族に患者を支えてほしい。
「今まで普通に動けていたのがうまく動けなくなり、何らかの障害が残ったとなると、本人はものすごく受け入れるのが大変です。心のケアはもちろん、まひがあったら身の回りで介助してあげるとか、身体面のケアもお願いしたいです。リハビリの先生もいろいろと細かく教えてくれますしね」。
ただ、24時間365日付きっ切りでケアをしていたら、支える側の家族も疲弊してしまう。サポートをする側とされる側を「切り離す時間」も必要だと福島医師は訴える。
「デイサービスやデイケア、ショートステイをちょっと利用して、患者さんと離れる時間があるといいですね。それでも、普段のケアをしていることに変わりはないわけですから、うしろめたいことは何もありません。時には、自分だけの時間を大切にするようにしてください」。
※写真と本文は関係ありません
記事監修: 福島崇夫(ふくしま たかお)
日本大学医学部・同大学院卒業、医学博士。日本脳神経外科学会専門医、日本癌治療学会認定医、日本脳卒中学会専門医、日本頭痛学会専門医、日本神経内視鏡学会技術認定医。大学卒業後、日本大学医学部附属板橋病院、社会保険横浜中央病院や厚生連相模原協同病院などに勤務。2014年より高島平中央総合病院の脳神経外科部長を務める。