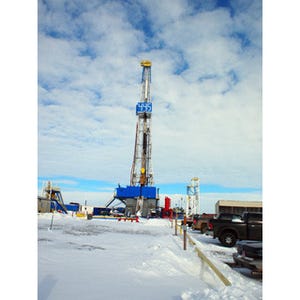政府は11日に開催された閣議において、中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」を決定した。原子力発電所を「重要なベースロード電源」と位置づけ、民主党前政権が掲げた「2030年代に原発稼動ゼロ」施策から大きく転換した。
原子力発電所については、発電(運転)コストが安く安定的に発電することができ、昼夜を問わず継続的に稼働可能な「ベースロード電源」として、地熱、一般水力(流れ込み式)、石炭とともに重要電源とする。また、原子力規制委員会が安全と判断した原子力発電所は再稼働を進め、国も前面に立ち、立地自治体に理解と協力を得るよう取り組むとしている。
原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより「可能な限り低減させる」とした一方、エネルギーの安定供給やコスト低減、温暖化対策などの観点から「確保していく規模を見極める」と表明。また、東京電力福島第1原子力発電所事故の教訓を踏まえ、リスクを最小限にするために万全の対策を尽くすとともに、万が一事故が起きた場合には国が「責任をもって対処する」としている。
天然ガスやLPガスなどについては、発電コストがベースロード電源の次に安く、電力需要の動向に応じて出力を機動的に調整できる「ミドル電源」として、石油や揚水式水力などについては、発電コストは高いが、電力需要の動向に応じて出力を機動的に調整できる「ピーク電源」として、それぞれ位置付けた。
再生可能エネルギーについては、現時点では安定供給面やコスト面など課題はあるが、「エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源」と表現。2013年から3年程度、「導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進していく」という。今後は、系統強化、規制の合理化、低コスト化等の研究開発などを着実に進めていくために、再生可能エネルギー等関係閣僚会議を創設し、政府の司令塔機能を強化するとともに、関係省庁間の連携を促進していく。
高速増殖炉原型炉「もんじゅ」については、高レベル放射性廃棄物の減容・有害度の低減や核不拡散関連技術等の向上のための「国際的な研究拠点」と位置付け、当面存続させる。