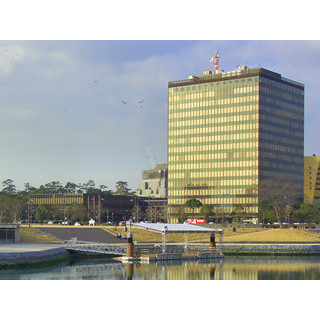堀高明代表取締役社長とともにスターフライヤーを立ち上げたひとりとして、スターフライヤー創業の歴史をここに記していこうと思う。前回、航空事業をはじめるにあたって必要な初期資金を60億円とし、なんとかそのめどが立つまでの話にふれた。その折に、北九州市役所からひとつの連絡があった。「そんなので大手と戦えるのか?」と。
ブランディングとの遭遇
資金集めを本格的にスタートさせた2004年が暮れようとする頃、北九州市役所からあった連絡は以下のようなことだった。「末吉市長がスターフライヤーの知名度について心配されている。特に東京では全くニュースにもならない。こんな状態で大手と戦っていけるのか?」
設立当初は必要資金確保のめども立っておらず、航空局との認可交渉をやり切る人材の確保も不十分だったので、正直、会社の認知拡大策まで考えをめぐらす余裕はなかったというのが実態だった。しかし、末吉興一・北九州市長の懸念はよく分かった。開港まで1年と少し、時間と知恵が足りないことはみな感じていた。
当時、北九州市は「デザイン塾」を開催するなど、地元の文化資源を活用する取り組みに力を入れており、ブランド戦略に造詣のある方もおられた。この周辺からスターフライヤーの首都圏での認知を上げるには、そのコンセプトを統一したデザインのもと、感性とビジュアルに訴えることが必要という意見があり、我々に投げかけられたのであった。
「このデザインとなら心中できる」
堀社長とじっくり相談し、ここは企画に乗り、デザインから会社を見せるという手法を採ろうと決断した。何より、「他のエアラインがやってない」ことだったからだ。こうして社長ともども、当時外部から参画してデザイン塾を進めていた方々とのミーティングに臨んだ。
ここでお会いしたのが、ロボットデザイナーでフラワーロボティクス代表の松井龍哉氏と東京藝術大学の桂英史助教授だった。ブランドの持つ力、というおふたりの話には非常に説得力があったし、松井氏の代表作である精密・繊細なロボット「Posy」を見て、「このデザインとなら心中できる」と直感した。
「エアラインのトータルデザインをまとめてお願いしたい」。堀社長から決めの一言が出て、ここに「デザインエアライン」の一歩を踏み出したのだった。
「世界のどこにもないと今言えるのは真っ黒だ」
トータルデザインといっても対象物は多岐に亘り、簡単に全部を具体化できるものではない。まず、最も視覚に訴える機体デザインと会社のロゴを決め(これまで持っていたロゴはデザイナーさんに丁重におわびしてお蔵入りとなった)、そこから備品、広告、パブリシティーに展開しようということになり、我々からは盛り込むべきコンセプトだけを伝えた。「感動のあるエアライン」「他社とは違うエアライン」の2つだ。
そこからは、フラワーロボティクスの人々には地獄の日々だったのではないか。機体デザイン、模型、設備備品への展開例を盛り込んだプレゼンテーションを作成するまでに世界中の千にも及ぶ機体デザインをくまなく調べ、案を絞り出してコンセプトの独自性を示さねばならない。3カ月を経て、「デザインコンシャス」「ラグジュアリー」「モダン」と3つの機体デザイン案が提示された。
末吉市長にはお花畑のような「デザインコンシャス」案がいいと言われ、社内でもそれぞれが好き嫌いを述べ合ったが、こういうものは議論をしてまとまるようなものではない。最終的に堀社長が、「世界のどこにもないと今言えるのは真っ黒だ」と決断を下した。黒・白・シルバー(灰)を基調とした備品や航空券、アメニティーの展開も上品でスタイリッシュさを感じさせるものだった。
その後、多くの国内外のブランド、有名企業からコラボの申し入れを受けることになる「スターフライヤーイメージ」が歩き出した。
「顔」をめぐるエアバス技術者との議論
航空会社の象徴が固まり、事業コンセプト・機体デザイン・ロゴ・備品・広告と展開するためのブランディング戦略の全体像を発表するのだが、その前にもう一悶着あった。世界のエアラインが航空機を真っ黒に塗らない理由のひとつに「黒は太陽熱を吸収し、機体の温度が上がって計器の作動に影響が出る」との懸念があると言う人もいた。
果たして、エアバス技術陣から高温誤作動リスクを避けるためレーダー・飛行計器が詰まる「レドーム」と呼ばれる航空機の「鼻」の部分は黒く着色しない方がいい、とのアドバイスが出てきた。しかし、これを飲めば機体デザインは鼻が白くふくらみ、とても間延びした顔になってしまう。
「世界には日本よりずっと暑い地域に、濃紺を施した機体が飛んでいる。どこが違うのか」「いったん上空に上がれば気温は下がる。地上気温で計器に不具合が生じるような機体なのか」など厳しいやり取りがあり、エアバス側も入念な数値検査を繰り返した結果、何とか「セーフ」。現在の機体の「顔」に落ち着くことができた。
「マザーコメット(母なる彗星)」の衝撃
2005年5月に行ったブランディング発表会では、デザインという切り口だけでなく、「どんなエアラインにしたいのか」という我々の想いを伝えることが重要だった。それが「マザーコメット(母なる彗星)」という基本コンセプトである。
初期スターフライヤーロゴ |
乗っていただいた乗客に「あ、この会社、いいな」とまず感じてもらえること。それが「他にないものだね」という感動につながり、それを世界中に振りまいていければ、との想いを表したコンセプトだ。松井氏が我々の想いと自らの考えを昇華しつくした上で提示いただいたものだと感じ、これを見た時は身内ながら正直感動した。
しかし、ブランディングとはそんなたやすい代物ではない。制服、機内インテリア、サービス、広告など具体的なモノをどうするかとなると必ず好き嫌いの違いが表面化し、ディテールを作る過程では反対論は噴出するのだ。それも社内、地元、どこからでも。この平坦でない道のりについては後に触れたい。
※本文に登場する人物の立場・肩書等は全て当時のもの
筆者プロフィール: 武藤康史
航空ビジネスアドバイザー。大手エアラインから独立してスターフライヤーを創業。30年以上におよぶ航空会社経験をもとに、業界の異端児とも呼ばれる独自の経営感覚で国内外のアビエーション関係のビジネス創造を手がける。「航空業界をより経営目線で知り、理解してもらう」ことを目指し、航空ビジネスのコメンテーターとしても活躍している。