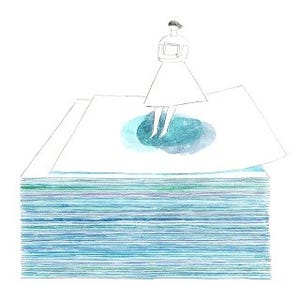二十五、六歳の頃だっただろうか。津奈美はそのとき、勤めていた会社の経営が傾いて急に退職することになり、人生で最大のパニックに陥っていた。
新卒で勤め始めて三年やそこらで貯金もろくになく、このままでは数ヶ月で家賃も払えなくなってしまう。かと言って、生活費を稼ぐためにフルタイムのアルバイトをすれば、就職活動ができない。
よくある話だが、このとき「水商売」という言葉が津奈美の頭をよぎった。特に偏見はなかったが、男あしらいが上手いわけでも、人と話を合わせるのが得意なわけでもない自分に務まるのか、それが心配だった。しかし、面接ではそんなことはまったく問題にされず、呆気なく「採用」になり、津奈美はいわゆるキャバクラで働き始めた。
嫌な客もいた。金を払っているのだから、自分は王様だ、と言わんばかりの男。払ったぶんだけ触らなければ損だと思っているのか、とにかく肌に触れようとしてくる男。
学生時代にアルバイトしていた喫茶店と、基本的には同じだった。どこでも自分の権力を誇示したい人や、「とにかく金を払っているのだから、可能な限りのサービスを受けなければ損だ」と思っている人は、男に限らずどこにでもいる。津奈美はそれを受け流すことを覚え、不器用ながらお世辞を言ったり、柔らかく拒否したりしてお客の相手をした。
その中にひとり、ほかの誰とも違う男がいた。澤田という男だった。42歳だと言っているのを聞いたことがある。津奈美にはよくわからなかったが、何か事業をしているらしく、仕事の接待で店に人を連れてくることが多かった。
あまり邪魔されずに男同士で仕事の話をしたい、というときなどに、津奈美は呼ばれることが多かった。ノリ良く騒げるほうではなかったが、こういう場ではそのことを良い方に取ってもらえるのか、と、自分の長所を見つけてもらえたような気がした。
たまに澤田はふらっと一人で飲みに来ることがあった。ボトルから何杯か飲み、長居せずに帰ってゆく。若かった津奈美の目には、それも好ましく思えた。
三ヶ月ほど経ち、津奈美はやっと次の就職先を見つけた。澤田が店に来たとき、そっとそのことを打ち明けると、澤田は就職祝いにとシャンパンを開けてくれた。
津奈美は初めて、ピンクのシャンパンというものを飲んだ。ハーブの香りのような、果物の香りのような、複雑な香りが立ち上ってきて、まるで美味しい香水を飲んでいるようだ、と思った。
そして、その帰り際に澤田に連絡先を渡され、「就職祝いにデートしよう」と誘われた。
津奈美は澤田にメールを送り、会う日を決めた。店の外で会うとなると、急に焦り始めた。これまでは店からドレスを借りていたし、生活費と貯金のために必死で、この三ヶ月、服は買っていなかった。クローゼット代わりに使っている押し入れを開けてみると、どの服も安っぽく見えた。かといって、以前仕事で着ていたスーツで行くわけにもいかない。
店ではドレスと暗い照明でそれなりの雰囲気に見えていただろう。けれど、今度会うのは昼間だ。澤田に子供っぽいと思われたくなかった。店でのイメージのような、大人っぽい落ち着いた女の服装をしなくては、と思った。
津奈美はまず、ファストファッションの店に行き、ワンピースを次々と試着した。これまで選んだことのないような背中の開いたデザインのものや、身体のラインがはっきり出るようなもの、大胆な花柄、そういうのを着てみた。
着るごとに自分が別人になったように感じた。「私は、こういう服が似合う女だったんだ」と、また新たな発見をした気がした。服を選ぶと、脱がされることを想像した。澤田のような大人の男には、最初のデートで当たり前のようにスムーズにそういう展開に持ち込むように思えた。
今度はファストファッションではない、隣にある老舗の百貨店に入った。これまで選んだことのない、濃い色のランジェリー、綺麗なレースがあしらわれているブラやショーツが目に飛び込んでくる。
「大人の女」は、いったいどういう下着を着けているものなんだろう? 目が回りそうな色彩の洪水にのまれそうになったとき、ふと黒いレースのセットに目が留まった。黒なんて、「いかにも」っぽすぎないだろうか。セクシーすぎるように思えて、これまで着けたことのない色だった。
パッドの薄い、繊細なレースで作られた、とても華奢なセットだった。津奈美が持っている、上下セットで三千円程度のサテンやフリルの下着が、とたんに色褪せていくように感じた。
試着すると、今まで見たことがないくらい、自分の身体が色っぽく見えた。津奈美はワンピースよりもずっと高いその下着を買った。
そういう過程を味わって、津奈美は自分のいいところは全部、澤田が見つけさせてくれるような気がした。
待ち合わせの場所に、津奈美はスターバックスのアイスコーヒーを買って待っていた。澤田はやたらと車高の低い外車に乗って来た。頭をぶつけそうになりながら乗り込み、津奈美はスマートにこういう車に乗れない自分の経験値のなさを恥じた。
コーヒーを受け取ると、澤田は「ありがとう」と言い、ストローに口をつけた。
「うちの嫁さん、コーヒーが駄目で、匂いだけでも嫌だって言うから、家で飲めないんだよね」
津奈美はその言葉で、空気の流れが止まったように感じた。
「結婚、してたんですか?」
なるべく普通の声を出そうとする。
「あれ? 言ってなかったっけ? してるよ。随分前だから、もう男と女って感じじゃないけど」
澤田は指輪をしていない。一瞬の隙もない自然な言い方だったせいで、津奈美は逆に気づいてしまった。わざと言っていなかったはずだ、と。そういうずるい男なのだと。
澤田のデートコースは、津奈美のような二十代の、贅沢をほとんど知らずに生きてきた女にとっては夢のようなものだった。海辺のフレンチで食事をしたり、ホテルのラウンジでお茶を飲んで休憩したり。ドラマのようだと思ったし、こういう高級なお店では、お手洗いにペーパータオルではなく布のハンドタオルが丁寧に畳まれてたくさん置いてあるんだな、と、どうでもいいような細かいことを考えたりした。心はすっかり離れていた。この場からも、澤田からも。
当たり前のようにホテルに誘われたとき、津奈美はぞっとした。あんなに憧れていた澤田が、急に小さい男に見えた。
「ごめんなさい、ここでいいので降ろしてください」
かたい声でそう告げると、澤田は明らかに気を悪くしたようだった。乗り込んだときと同じように、頭をぶつけそうになりながら苦労して車から這い出していると、澤田が言った。
「お前みたいな女、いるよな。キャバ嬢なのに『私だけは違います』って顔してる女。『ここにいるような女じゃないんです』って気取ってる女。自分が特別だと思ってるんだろ? そんなんじゃ、どこの会社入っても続かねえよ。どうせ前の会社も、自分には合わないとか思って辞めたんだろ? 自分の価値、高く見積もりすぎなんだよ」
車が走り去るのと逆方向に、津奈美は早足で必死に歩いた。動揺していることを後ろ姿でも悟られたくなかった。涙がこぼれていたが、拭う仕草も見せたくなかった。もういないはずだ、バックミラーでも見えないはずだ、という距離まで来ても、津奈美は歩調をゆるめられなかったし、涙も拭けなかった。
帰ってすぐ、着ていた服を捨てた。今日のことを思い出させるものは、見たくなかった。
でも、下着はあまりにも美しすぎて、捨てることができなかった。津奈美はそれを使わないスカーフにくるんで、引き出しのいちばん奥に入れた。
あれからたぶん、十年が経った。あまりにも嫌な出来事すぎて、何歳のときのことだったか、正確な年齢を覚えていない。津奈美はあのとき入った会社に勤め続けている。さすがに貯金も十分にでき、そろそろクローゼットが押し入れの部屋から引っ越そうと荷物を整理しているとき、あの黒い下着を見つけた。
スカーフを解き、手に取ってみる。今見ても、最初に見たときと同じくらい新鮮に「美しい」と感じた。
あのときの澤田の言葉は、なんだったのだろう、と津奈美はこの十年間、何度も自分に問い直してきた。あんなにつらく感じたのは、本当のことをずばりと言い当てられたからじゃないのか、と自分を責めた。澤田のほうが正しいのではないか、そんな澤田に嫌悪感を抱く自分は、ただ潔癖ぶっているだけの、特別ぶっているだけの人間なんじゃないか。
澤田の予言が当たらないよう、どんなことがあっても会社を辞めようとは思わなかった。何度でも泣いたし、ストレスで胃潰瘍寸前までいったこともあった。けれど踏みとどまり、今はなんとか中堅のポジションに就くことができている。
ブラを着けてみる。サイズがもう合わないのではないかと思ったが、締め付けない素材のせいか、ぴたりと身体に合った。津奈美は自分の姿を鏡で見た。
私は、私の美しさを、自分で発見したのだ。澤田に教えてもらったわけじゃない。そして、澤田が本当のことを言ったのだとしても、去り際にあんなことを言う男は、やはり卑怯で、ひどい男なのだ。この十年で初めて、はっきりそう思えた。
津奈美はその下着を、丁寧に手洗いした。これから身につけるために。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望