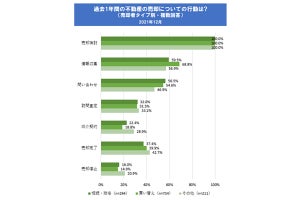マイナビニュースの読者様にお聞きした「住宅ローン」についてアンケート結果から、皆さまが気になっていることに対してQ&A形式でお答えしていきます。
第4回は「離婚をした場合のその後の住宅ローン」についてです。
Q.離婚を検討していますが、現在住んでいる持ち家を売却するのか、住み続けるのかはまだはっきりしていません。気を付けるべき点などがあれば教えてください。
A.住宅は資産のうち大きな割合を占めるので、離婚の際に悩む大きな問題のひとつです。売却か住み続けるかまだはっきりしていないとのことですが、住宅ローンは長期間返済が続いていくものですので、基本は売却がおすすめです。しかし様々な事情で住み続けることを選択するという場合もあると思いますので、今回はどのような選択肢があるのかと注意点を解説していきます。
検討前準備
●住宅ローンの契約内容を確認:住宅ローンの残高・誰が債務を負っているか・連帯保証人の有無などを確認する
●「登記簿謄本」を取得:誰の名義になっているか・不動産にどのような担保権が設定されているのかを確認する
●不動産業者に査定依頼:不動産の価額が分かれば、売却するのか、住み続けるのかの判断がしやすくなります
債務者が住み続ける場合は連帯保証人に注意
現在は住宅ローンを借りる際に連帯保証人は不要となっているケースが多いので、該当する方は少ないかと思いますが、連帯保証人になっている方は要注意です。
連帯保証人を元妻にしたまま、元夫(債務者※)が返済不能になれば、離婚後も元妻に返済の責任が求められます。基本的に連帯保証人から外れることは難しいと言われていますが、別れた後に長期間そのような不安を抱えないためにも、可能な限り連帯保証人から外れておくことをお勧めします。
※債務者とは貸金業者や金融会社などからお金を借りた人のことです。今回の場合は、住宅ローンを借りた人のことを指します。
連帯保証人から外れる方法
・連帯保証人の変更
妻に代わって夫の親や兄弟などに連帯保証人になってもらうことを銀行側が了承をすれば変更することが可能です。
※土地や建物を担保にして外すことができる可能性もあります。
・借り換え
債務者本人が単独でローン審査に通る必要がありますが、別の銀行へ住宅ローンの借り換えをすることによって連帯保証人から外れることが可能です。
債務者以外が住み続ける場合
債務者以外が住み続ける場合の選択肢は主に3つです。
免責的債務引受で名義変更をする
免責的債務引受とは、債務を引受人が新債務者として債務者に代わって同一内容の債務を負担することをいいます。
金融機関の了承が前提となりますが、元々の債務者である夫が借りている住宅ローンをそのまま妻が引き継いで住宅ローンを返済しながら住み続けることができるというものです。
そもそも対応している金融機関が限られていることや、対応するかどうかを判断するために、妻の年収や信用情報、健康状態などの審査があることや、離婚協議書(公正証書)の提出を求められる場合もあります。
別の銀行へ借り換えを行い、名義変更をする
夫名義のローンの残債分を、妻が別の銀行でローンを組み、夫名義で借りていた銀行に返済するという方法です。借り入れをした時期によっては当時よりも低金利で組むことができる場合もあります。
ただし、借り換え時に審査があることや諸費用がかかる点、免責的債務引受同様に対応してくれる金融機関が限られる点は注意が必要です。
債務者に支払い続けてもらう
妻と子どもが住み続けて、養育費の代わりに夫(債務者)が支払いを続けるという方法があります。しかしこちらは双方にリスクがあるため、あくまでも最終手段です。
例えばこの場合の妻側のリスクは、別れた夫が返済を滞納してしまうと最悪の場合家から追い出されてしまうなどが考えられる一方で、夫側は住宅ローンを返済しているものの居住はしていないので、「住宅ローン控除」が受けられないことや、将来新たな物件が欲しいとなった場合に住宅ローンを借りづらくなることなどが考えられます。
この方法を選ぶ場合は、離婚後にトラブルにならないように住宅ローンの支払いや妻が住み続けることに関する取り決めなどを記した公正証書を作成しておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、離婚する場合の住宅ローンに対してどのような選択肢があるのかとそれぞれの注意点を解説してきました。離婚後の住まいについては、子どもを転校させたくない・住み慣れた家を手放したくないなど様々なお考えがあると思います。
しかし離婚して数年後に返済が滞ってしまい競売にかけられるなど大きな問題になってしまっては本末転倒です。そうならないためには、離婚後も住宅ローン返済をしていけるのか、その他の支出に影響がないかなどその後のライフプランが問題ないかが一番重要です。債務引受や借り換えが難しい場合は、居住することにこだわりすぎずに売却することも手段のひとつでしょう。
※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。