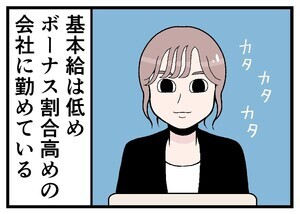前回のコラムで日本の企業においても確定拠出年金の導入が増加傾向であることに触れました。
確定拠出年金=日本版401k
ところで、確定拠出年金は新聞の見出し等で、「日本版401k」と記されることがあります。日本版という響きからして、いかにも海外を参考に導入された制度という印象ですね。
では「401k」というのは何かの暗号でしょうか。これは俗に「ヨンマルイチケイ、またはフォー・オー・ワン・ケイ」と呼ばれるもので、もともとは米国の内国歳入法(Internal Revenue Service Code)という法律の401条(k)項において定められた税制適格要件を指しています。
少し話が難しくなってしまいましたが、要は会社勤めをしている個人が職場の制度を通じて積み立てた老後向け資産について、課税を繰り延べる(掛金の拠出時、運用時には課税を行わず、資金を引き出す段階で課税する)ための要件を規定した法律で、1978年に成立しました。日本の確定拠出年金はこれをもじって日本版401kと一部で呼ばれるようになったわけです。
企業年金制度に個人が意思を反映できる
この法律が画期的だったのは、会社が提供する企業年金制度に社員個人が自分の意思を反映させられるようにしたことにあります。それまでは現在の日本同様、米国においても企業年金と言えば、会社が掛金拠出から運用、給付まで一手に担う確定給付型の制度が主流でした。
料理に例えれば、材料の仕入れから調理、配膳まで全てお任せで食事にありつけるというスタイルです。逆に言うと、社員全員が同じメニューを頼むことになるため自分の希望を食事に反映することはできません。
それに対して、確定拠出年金は、材料の仕入れ(社員が選択する金融商品の選定)は会社が行いますが、どの材料をどれだけ使うか(どの金融商品にどれだけ資金を配分するか)、どのように調理(運用)するか、どのように配膳してもらうか(受け取るか)は社員本人が決めます。
おいしい食事にありつける保証(会社による利率保証)はないものの、自分の好みに合った食事を作ることができます。調理に不慣れな人のために、講習やテキスト(投資教育)も用意されていますし、社員にとっては個人で仕入れる(銀行や証券会社の窓口で購入する)よりもお値打ちの食材(手数料を抑えた金融商品)を使える場合もあります。
いずれにしても、これまで会社任せだった自分の老後のお金を、「自分事」として捉え、自ら育てていく環境がいち早く整ったのが米国でした。
米国では労働人口の半分が確定拠出年金に加入
米国では確定拠出年金の制度ができて以降、過去30年以上加入者数は増え続け、今では7,671万人と確定給付型の企業年金加入者数の5倍(2013年時点)にまで膨らんでいます。これは全米の労働人口1億5,490万人の、約50%に達する水準です(ちなみに日本の民間サラリーマンに占める確定拠出年金加入者の割合は2015年3月末時点で約14%です)。
確定拠出年金の加入者が飛躍的に増加し、社会インフラの一部となったことで起こった最も大きな変化は、長期の資産運用(投資)がより多くの人々にとって身近になったことです。
アメリカ人というと常日頃から投資に慣れ親しんでいるという印象をお持ちの方もおられるかもしれませんが、確定拠出年金制度が始まる1980年代までは、個人が投資をする際によく利用する投資信託(投信)の家計保有比率は6%弱に過ぎませんでした。それが20年で46%まで急拡大したのです。
また、投信を保有している家計のうち、職場の制度を通じて、すなわち確定拠出年金制度を通じて初めて投信を購入した割合も6割を超えており、90年代以降この割合はさらに増加傾向にあります。
このことから読み取れるのは、アメリカ人の多くは必ずしも元から投資に縁があったわけではないが、職場が提供する確定拠出年金制度を通じて、投資に触れるきっかけができたということです。米国の場合、この間自国株式市場が長らく好調であったことなど、考慮すべき点は他にもありますが、それにしてもこの劇的な変化は、「貯蓄から投資へ」というスローガンを何年も掲げっ放しの日本にとって示唆に富む事実と言えるでしょう。
年金保護法で加わった「自動加入」と「自動運用」
当初は確定給付型の企業年金制度を補完する位置付けでスタートした米国の確定拠出年金ですが、制度の普及が進むに連れて、新たな問題が叫ばれるようになりました。それは、制度加入自体が任意であるがゆえの非加入者の増加、制度には加入したものの投資対象を分散せず自社株や元本確保型商品といった単一資産に100%資産配分してしまう加入者(適切な運用ができていない加入者)の存在、という悩ましい問題です。
制度への加入から運用方法に至るまで社員自らが選択するという確定拠出年金の仕組みからすれば、制度に加入しないことも、偏った資産配分も、個人の選択の結果と言ってしまえばそれまでですが、そうした選択によって、リタイア時に十分な資産形成ができていない層が増えることは社会的にも見逃せないという機運が強まり、問題解決のため2006年に成立したのが年金保護法という法律です。
この法律によって、それまで完全に自己選択の制度として位置付けられていた確定拠出年金制度に一種のガードレールが加わることになりました。「自動加入」と「自動運用」という仕組みです。
自動加入とは、会社の確定拠出年金制度にいったん全社員を加入させてしまい、どうしても加入したくない場合には社員が能動的に意思表示することで非加入扱いにするというものです。
自動運用とは、どのように資産を配分すればよいか分からない場合の「とりあえず」の選択肢として、会社が選定した分散投資商品(適格デフォルト投資商品)に掛金を自動的に配分するというものです。米国では、この自動加入と自動運用という二つの進化よって、確定拠出年金の加入者数および加入率は上昇し、同時に運用状況の改善も進みました。
日本の確定拠出年金の場合、会社が実施する制度であるため対象者は全て自動加入となっている場合が多く、低加入率という問題はあまり聞かれませんが、運用においては改善余地があると言えそうです。
次回は、英国の事例にも目を向けつつ確定拠出年金の運用の実態に迫ってみましょう。
筆者プロフィール:本庄洋介
フィデリティ投信 法人/年金ビジネス本部 シニアマネージャー。2006年フィデリティ投信入社。確定拠出年金を含む法人/年金業務全般に携わる。2014年にはフィデリティ・インターナショナルのロンドン拠点に駐在し、英国の確定拠出年金市場の調査に従事。京大院卒。公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。1級DCプランナー。
※写真は本文と関係ありません