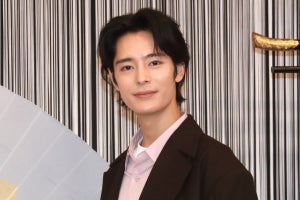3番目に注目されたシーンは20時39分で、注目度76.9%。一条天皇がようやく中宮・藤原彰子に振り向いたシーンだ。
一条天皇は、左大臣・藤原道長(柄本佑)との公務を終えると立ち上がり、道長に御嶽詣の御利益はあったのかと問うた。「まだ分かりませぬ」と答える道長に、「今宵、藤壺に参る。その旨、伝えよ」と、一条天皇は言った。あの日の彰子の涙がついに帝の心を捉えたのだ。道長は目を見開いた。待ちに待った日が来たのだ。藤壺では女房たちが慌ただしく一条天皇を迎える準備を進めていた。宮の宣旨をはじめ、女房たちは晴れやかな表情でかいがいしく中宮・彰子の身支度を調える。
しかし、当の彰子は魂の抜けたようなうつろな表情で、女房たちにただ身を任せていた。我が身に起こっていることがいまだに信じられないのだろう。雪の降り積もる中、一条天皇が藤壺へ足を運んだ。「いくつになった?」「二十歳にございます」一条天皇と彰子は、寝所で2人きりとなった。
「いつの間にか、大人になっておったのだな」「ずっと大人でございました」待つものの気持ちは、待たせた方には分かりにくい。2人の間にはまだ、大きな溝があった。「そうか…さみしい思いをさせてしまって、すまなかったのう…」彰子の心に触れ、いたたまれない気持ちになりながらも、一条天皇は妻の体を優しく抱き寄せた。彰子は自分の想いのまま、夫の背中に手を伸ばした。
「やっと一条天皇が彰子さまを受け入れて下さった!」
ここは、彰子の恋が実った瞬間に、多くの視聴者が感動したと考えられる。
長らく心を通わせることができなかった彰子と一条天皇だが、彰子の決死の告白でようやく本当の夫婦となることができた。ネットでは「やっと一条天皇が彰子さまを受け入れて下さった!」「彰子の告白を受けた一条天皇の反応がよかった」「一条天皇と彰子さま、ほんとに少女漫画みたい」と、2人を応援する視聴者のコメントが多く集まった。
1007年当時、実は一条天皇には藤原義子・藤原元子(安田聖愛)・藤原尊子という3人の女御と皇后・藤原定子が産んだ3人の子がいた。女御とは中宮に次ぐ后の身分。藤原義子は内大臣・藤原公季(米村拓彰)の娘で996年に入内して、弘徽殿女御と呼ばれた。藤原元子は右大臣・藤原顕光(宮川一朗太)の娘で996年に入内して、承香殿女御と呼ばれた。997年に妊娠した兆候が見られたが、998年に体内から水分が出たのみでこの妊娠は終わっている。藤原尊子はあの藤原道兼(玉置玲央)の長女だ。彰子にとっては従姉妹である。998年に入内し、暗戸屋女御や前御匣殿女御と呼ばれた。3人の女御はいずれも一条天皇の子どもを宿すことはできなかった。一条天皇が定子に強い愛情を見せたのも、定子だけが子どもを産んでくれたということもあったのかもしれない。
第1皇女・脩子内親王(井上明香里)は997年生まれ、非常に信心深い性格だったそうだ。高貴な皇女がそうだったように、終生未婚だったが、道長の次男・藤原頼宗(上村海成)の次女・延子を養女とし、延子が後朱雀天皇に入内した際には養母として付き添ったそうだ。
第1皇子・敦康親王は999年に生まれた。生母・定子が亡くなった後は養母・彰子と仲むつまじい姿を見せてくれている。しかし彼は彰子の産んだ異母弟・敦成親王と東宮(皇太子)の地位を争うことになる。
第2皇女・ビ(※女へんに美)子内親王は1001年に生まれた。定子の忘れ形見だが、1008年に病のため夭折した。『栄花物語』にはビ(※女へんに美)子内親王が亡くなった際、一条天皇や脩子内親王が悲嘆にくれる様子が描かれている。このように、一条天皇には作中ではあまり描かれていない妃や子がいた。そんな状況で彰子が一条天皇を振り向かせるのは非常に困難だったのだ。