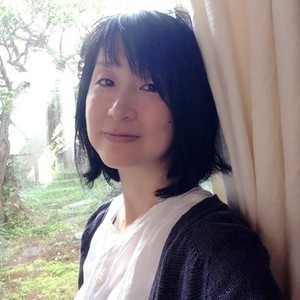24日にスタートしたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『エルピス -希望、あるいは災い-』(毎週月曜22:00~)。実在の複数の事件から着想を得て、女性連続殺人のえん罪事件を扱う重い題材ながら、コミカルな会話劇や人間味のある登場人物たちが登場する、「正しさとは何か?」を問う社会派エンタテインメントで、初回が放送されると、SNSでは「初っ端から度肝を抜かれた」「これは本気のやつだ」と反響があった。
NHK連続テレビ小説『カーネーション』などを代表作に持つ脚本家の渡辺あや氏と、『大豆田とわ子と三人の元夫』などを手がけたカンテレの佐野亜裕美プロデューサーが向き合いながらオリジナル脚本を仕上げていった作品。そんな2人にインタビューし、テーマと題材の必然性に迫った――。
■「腸内細菌」を社会に置き換えて…
――『エルピス -希望、あるいは災い-』というタイトルからして意味深ですが、どのように名付けたのでしょうか?
渡辺:代官山の会議室で、みんなで考えていたんです。でも、なかなか良い案が思いつかなくて。何気なしに「パンドラの箱」についてwebで調べてみると、箱の最後に残ったものをギリシャ語で「エルピス」と呼ぶことが分かり、しかも訳し方によってその意味は希望とも災いとも受け取れる。作品を示唆するものでした。それで「これがいい」となって、決まりました。
佐野:先に脚本が仕上がっていたので、むしろ、この脚本を表現するタイトルは何か? という視点でした。あやさんとは台本作りから「人間や出来事の多面性」について話していたことも大きかったのかもしれません。
渡辺:そうなんです。台本を書きながら、「正しさって何だろう」と疑問を持ち始めて。正しいと思って、良かれと思ってやったことが災いになることがままあります。だから、正しいことをやりたいと思っていろいろ行動もするけれど、本当に正しいって言えることはないんじゃないかって考え始めたんです。そんなときに「腸内細菌」についての本を読んだら、菌に善玉と悪玉があるわけではなく、いろんな菌が多種多様にバランスよく存在していることが実は、腸にとって理想的であることを知ったんです。そこから、私たちが生きる社会に置き換えて「何が正しいのか、正しくないか」「何が幸福か、不幸か」「何が希望か、災いか」は言えないという答えにたどり着きました。物語の中でもこれについて触れています。作品を表すピッタリのタイトルだと思っています。
――普遍的なことに立ち返る一方で、今だからこそ求められる作品とも言えますか?
佐野:コロナウイルスによって世界がガラっと変わってしまいました。変わったからこそ、今まで見えなかったことがあぶり出されています。希望なのか、災いなのか、結局のところ分からないことも多く、当たり前のことが当たり前じゃないってことに私自身、気づかされたんです。日本に限らず、世界で生きている誰もが今、感じていることだとも思います。言語化されているのか、意識化されているかどうかは分からないけれど、潜在的に感じているはずです。だから、この作品は普遍的な話であると感じています。
■本質的なテーマは「信じることが希望」
――おふたりで作り上げていった作品なわけですが、「渡辺あや×佐野亜裕美」の掛け合わせには、どんな独自性があると思いますか?
渡辺:2016年の頃、国の政治に不穏な空気感と危機感を持ち始めたことを覚えています。普段は島根の田舎で家族以外の誰とも会わずに主婦をしている生活ですから、不安でした。この不安を誰と共有したらいいのかも分からず、世の中の人はこれをどう思っているのかと思いあぐねていたら、ある日ドラマ脚本の依頼に佐野さんが訪ねて来られたんです。最初はラブコメを書いてほしいという話だったんですが、どうも盛り上がらない。2人で一緒に熱くなれた話こそが、今の日本は何かおかしいっていう話だったんです。
問題意識をドラマにし、自分が社会や政治に対して感じている不安とか、違和感をかたちにし、ひいてはそれを視聴者とも共有できるんじゃないか。それは希望のように見えました。佐野さんという深く信頼できるパートナーと、自分のこれまでの人生とか人格を作品に全て投じて作り上げることで不安を払拭できると、まさに希望だったんです。だから、物語の中でも「希望とは何か」について、そして、「たった1人でも目の前の人を信じることができれば、自分にとって大きな希望になり得る」ということを描いています。信じることが希望。これがこの物語の本質的なテーマです。
佐野:日本は報道の自由やジェンダーギャップなど、先進国の中での遅れが目立っていると思います。斜陽国と、揶揄(やゆ)して言ってしまうこともあります。そんな行き詰まっている国の現状で人を信じられること自体が希望だと思います。日本は司法制度の改革も遅れています。構造を変えたい、法を変えたいという思いはもちろんありますが、すぐにできるわけじゃない。一人一人の力は微々たるもので、大きく働きかけができるわけではないけれど、物語の力を信じて悪あがきをしたい。最後の最後まで戦ったという気持ちを持ち続け、あやさんと物語を作り、それが結果的に、作品の特異性を表すものになっていると感じています。
えん罪を扱っていることも必然的です。なぜえん罪が起こったのかは、国によって違います。例えば、ポン・ジュノ監督の『殺人の追憶』のでっち上げられ方は韓国ならではのもの。国それぞれの社会が抱える鬱屈とか、押し寄せるひずみは、えん罪に表れやすい。立場が弱い人が追い詰められて犯人にされていくからです。今の日本のあり様を反映している題材だと思っています。えん罪モノをやりたいと思ってスタートしたわけではありませんが、社会に対する憤りを初めにあやさんと共有できたことから始まった作品です。