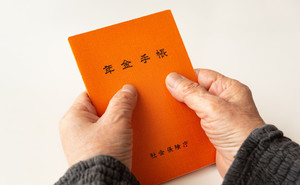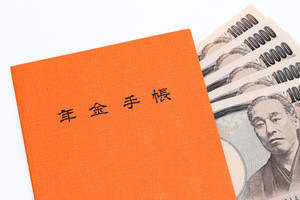遺族年金について考えたことはありますか? 令和3年簡易生命表によると、日本の男性の平均寿命は 81.47 歳、女性の平均寿命は 87.57 歳なので、夫に先立たれ、遺族年金を受給する妻は多いということです。
遺族年金は家族構成や死亡した人の年収によって受給額が異なります。そこで、会社員の妻を想定して、家族構成および年収別の受給額の目安を一覧でご紹介します。どのくらい受給できるのか知っておけば、夫亡き後の生活がイメージできるでしょう。
■遺族年金の受給要件
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、それぞれ受給要件が異なります。
<遺族基礎年金>
死亡者の要件
- 国民年金の被保険者
- 老齢基礎年金の受給権者
遺族の要件
- 死亡者と生計維持関係にあった「子のある配偶者」または「子」
<遺族厚生年金>
死亡者の要件
- 厚生年金の被保険者
- 老齢厚生年金の受給権者
遺族の要件
死亡者と生計維持関係にあった者の中で優先順位が高い人のみ受給
- 配偶者(夫の場合は55歳以上)および子
- 父母(55歳以上)
- 孫
- 祖父母(55歳以上)
※子と孫については、18歳到達年度の末日まで、障害等級1級または2級の者は20歳未満の者
18歳未満の子どもがいる会社員の妻であれば、生計維持関係にあった夫が亡くなった場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。
■遺族年金の受給額
<遺族基礎年金>
777,800円+子の加算額となります。
子の加算額は、2人目までは1人当たり223,800円、3人目以降は1人当たり74,600円となります(令和4年度額)。
たとえば、配偶者と子ども2人であった場合は、
777,800円+(223,800円×2)=1,225,400円となります。
<遺族厚生年金>
死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
※最低保障として、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算します。
たとえば、老齢厚生年金の報酬比例部分が120万円(年額)であれば、その4分の3である90万円を受給することができます。
■年収別の受給額
遺族厚生年金の受給要件を満たした会社員の妻がもらえる年金額を夫の年収と家族構成をもとに計算してみたいと思います。
まずは、老齢厚生年金の報酬比例部分の計算方法です。
報酬比例部分は次の計算式(1)+(2)の合計額となります。
(1)2003年3月以前
平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の月数
(2)2003年4月以後
平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以後の月数
※1946年4月2日以降に生まれた者の乗率
ここでは簡易的に(2)の計算式のみを使い、平均標準報酬額は年収を12カ月で割ったものとします。また、年収は変わらずに40年間勤務した場合の年金額とします。
<年収400万円の場合>
老齢厚生年金の報酬比例部分
33万3,333円×5.481/1000×480月=87万6,959円
遺族厚生年金の額
86万8,190円×3/4 =65万7,719円
●子がいない妻
遺族厚生年金
65万7,719円
●子が1人いる妻
遺族厚生年金
65万7,719円
遺族基礎年金
100万1,600円
合計:165万9,319円
●子が2人いる妻
遺族厚生年金
65万7,719円
遺族基礎年金
122万5,400円
合計:188万3,119円
<年収500万円の場合>
老齢厚生年金の報酬比例部分
41万6,667円×5.481/1000×480月=109万6,201円
遺族厚生年金の額
109万6,201円×3/4 =82万2,151円
●子がいない妻
遺族厚生年金
82万2,151円
●子が1人いる妻
遺族厚生年金
82万2,151円
遺族基礎年金
100万1,600円
合計:182万3,751円
●子が2人いる妻
遺族厚生年金
82万2,151円
遺族基礎年金
122万5,400円
合計:204万7,551円
<年収600万円の場合>
老齢厚生年金の報酬比例部分
50万円×5.481/1000×480月=131万5,440円
遺族厚生年金の額
131万5,440円×3/4=98万6,580円
●子がいない妻
遺族厚生年金
98万6,580円
●子が1人いる妻
遺族厚生年金
98万6,580円
遺族基礎年金
100万1,600円
合計:198万8,180円
●子が2人いる妻
遺族厚生年金
98万6,580円
遺族基礎年金
122万5,400円
合計:221万1,980円
このように、年収から遺族厚生年金額を計算し、家族構成によっては遺族基礎年金も受給できるので、遺族年金の総額を出すことができます。
以下に年収別の遺族年金額を一覧にしてみました(1万円未満を四捨五入して概算にしています)。
■遺族年金についての補足
前出の遺族年金の一覧で示した年金額は、40年間勤務して退職した夫が亡くなった場合を想定しているため、子どもは成人しているケースが多いと考えられます。そうすると遺族基礎年金は受給できないことになるので、子のない妻の金額が参考になるでしょう。
仮に夫が若くして亡くなった(厚生年金の被保険者期間が25年に満たない)場合は、最低保障として25年(300月)として計算するので、年収500万円であれば、51万円の遺族厚生年金を受け取ることができます。さらに要件にあてはまる子どもがいれば、遺族基礎年金も受け取ることができます。ただし、子のない30歳未満の妻の場合は、遺族厚生年金は5年間のみの支給となります。
遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」があります。これは夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満の場合に、遺族基礎年金を受給していなければ、58万3,400円(令和4年度)が遺族厚生年金に加算されます。65歳になると自分の年金が受給できるようになるため、中高齢寡婦加算はなくなります。
遺族年金は残された遺族の生活を守るための社会保障制度です。そのため、生計維持者を失ったことで生活苦に陥りやすい「子のある配偶者」に手厚くなるように制度設計されています。そのため、子のない配偶者は、亡くなった者が厚生年金の被保険者であった場合は遺族厚生年金のみ受給できます。
これは本来受け取るべき年金を本人が受給できなかったため、遺族が代わりに受け取るといった意味合いがあるので、納めた保険料の金額に応じた年金額となっています。老齢厚生年金の額がわかっている場合は、遺族厚生年金の額も自ずと出せるので、将来自分ひとりになったときの生活をイメージしておくといいでしょう。