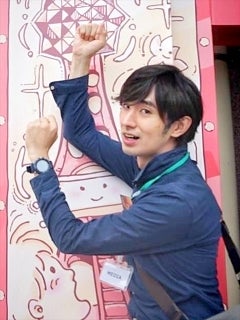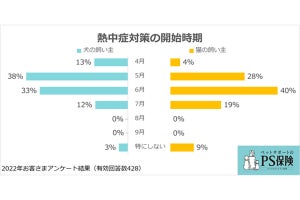梅雨が明け、いよいよ今年も暑い夏がやってくる。猛暑、酷暑が続くなかで、気をつけたいのは”熱中症”。電力不足のため節電まで叫ばれるようになった今夏だが、エアコンを適度に使いつつも、賢く乗り切るためのコツはあるのだろうか?ひまわりクリニック院長で、臨床内科医会専門医の野崎豊先生に詳しい話を聞いた。
熱中症が起こるメカニズム
まずは熱中症が起こるメカニズムと、発症しやすい時期について聞いた。
「人は暑さにより熱を体内にためこみますが、汗を気化することで体温を下げています。このとき、熱をうまく放出できないと熱中症になります。主に熱中症が増える時期は7月中旬から8月初めにかけてと言われています。でもここ数年、梅雨が明ける前後から、急激に気温が上昇する日が増えていますね。今年は異例の早さで梅雨明けを迎えた地域も多く、すでに多くの方が熱中症で搬送されています。つまり夏本番を迎える前に、多くの方が熱中症の危険にさらされる事態になっています。さらに、今年の夏は2年ぶり全国的な猛暑予想。ラニーニャ現象により、暑い日が長く続くことが予想されています」
続けて野崎先生は、コロナ禍ならではの影響も懸念する。「このところコロナ対策のため、家で過ごす時間が増えました。つまり多くの人が、外の暑さに身体が慣れないまま夏本番を迎えます。しかも外ではマスクが常態化している状況。困ったことに、マスクの中は湿度が高いため、喉の渇きを感じづらい。つい、水分補給を怠りがちになります」と、この夏は『マスク熱中症』に注意が必要、と警鐘を鳴らした。
では、どのような対策をしたら良いのだろう?まずは、熱中症の最大原因となる”水分不足”に日頃から気をつけていきたい。特に体温調節が苦手な、小さな子ども、高齢者、放熱の下手な肥満のかた、筋肉量が少なくて水分余力のない女性は注意して欲しい、と野崎先生。「夏の暑さが本格化する前に、熱中症になりにくい身体づくりに励んでください」と呼びかける。
「暑熱順化」とは?
熱中症対策のひとつに、身体が暑さに慣れる「暑熱順化」があるのをご存知だろうか。そもそも「暑熱順化」によって、身体にはどのような変化が起きるのか聞いてみた。
「たとえば、赤道付近の亜熱帯地域に住んでいるかたは、日本の夏程度の暑さでは熱中症になりません。それは何故かというと、常に暑さに対応できる身体になっているからです」と野崎先生はいう。
「『暑熱順化』とは、暑さに対して『より高い体温調節機能』を獲得することを言います。先に述べた通り、人は汗をかくことで体温を調節しています。でも夏前は汗をかく機会も少なく、汗腺機能が低調です。上手く汗をかける身体になっていないんですね。そこへきて急激に気温が上昇すると、暑さに順応できず、簡単に熱中症になってしまうんです」
「暑熱順化」を獲得するためには、深部体温を1度上げる工夫が必要になる。これに順化できると汗腺機能が高まり”さらさら”した汗を素早くかけるようになり、しっかりと体温を下げることができるようになるそう。これが熱中症対策には効果的だという。
では、深部体温を1度上げるためには?「手軽に行えるという意味で『入浴』をオススメしています。入浴はシャワーだけでなく、40~41度の湯船に10~15分程度、しっかりと首まで浸かること。すると深部体温を約1℃上げて発汗できます。あるいはウォーキング、ジョギングなど、汗ばむ程度の運動を30分ほど行うのも良いです」。ただ、これらの「暑熱順化」を行うとたくさんの汗をかくため、脱水にはくれぐれも注意して欲しい、と補足する。水分の吸収には最低30分ほどかかるので(胃通過時間)、30分前にコップ1杯分の水分を取ると良いそう。そして「暑熱順化」を獲得するには、数週間程度が必要だという。
熱中症対策として、むぎ茶がオススメ
日頃の”隠れ脱水”が熱中症の原因となる、と野崎先生は繰り返す。「日常的に、こまめに水分とミネラルの補給を心がけましょう。1時間にコップ1杯のペースで、水分とミネラルの補給を行うことで、血液の循環量は増え、汗をかきやすくなります。つまり『暑熱順化』を獲得しやすい身体になる。ただ、汗と一緒に失われた身体の健康維持に必要なミネラルは、身体では作れない栄養素なので、食品や飲料から補給する必要があります。そこで推奨しているのは、ミネラルが手軽に補給できる『ミネラル入りむぎ茶』です。無糖でカロリーもなく、カフェインを含まないので妊婦さんでも毎日、手軽に飲めます。さらに『ミネラル入りむぎ茶』には、『血流改善効果』や『体温下降効果』もあります」と説明した。
今年の夏はお出かけの予定を立てている人も多いはず。普段以上に自分の身体を労り、正しい熱中症対策で賢く乗り切ることが重要だ。
 |
取材協力:野崎豊先生ひまわりクリニック院長日本体育協会 公認スポーツドクター/日本東洋医学会 名誉会員/認定産業医/漢方専門医/日本小児学会専門医/臨床内科医会専門医 |