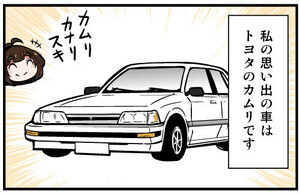使用済みバッテリーをいかに集めるか
中古リチウムイオンバッテリー事業の今後について、普及が進むEVやプラグインハイブリッド車(PHV)から使用済みバッテリーを回収するという根幹を、いかにうまく運用できるかも忘れてはならない課題である。
「国内の自動車販売は、売り切りとリースなどの割賦販売があります。ことに売り切りの場合、EVの所有権はお客様となるため、その後の行方が分かりにくくなる可能性があります。もちろん、販売店が情報をつかんで回収するのが一番ですが、廃車や解体などへ持ち込まれた場合には、リチウムイオンバッテリーの処理に費用が掛かるところを逆手にとって、日産が若干の費用で買い取ることで回収を進めています。リースなど割賦販売では、ファイナンス会社が所有権を保持しますので、回収しやすいといえます」
「北米ではリース販売が多いので、回収しやすいでしょう。欧州は日本と同様ですので、同じやり方で回収します」
「さらに将来的には、他の自動車メーカーの使用済みバッテリーの回収も、例えば遠隔地で1つだけ回収するとなるとトラックの運送費が高くつきますから、メーカーの枠を越えた共同での運搬・回収といった協議も必要になるのではないでしょうか」
メーカーの違いを超えた協業も視野
現在、日産がEVやHVなどで使用しているリチウムイオンバッテリーにも、銘柄の違いがある。あるいは他の自動車メーカーのリチウムイオンバッテリーも、フォーアールエナジーで再利用することは可能なのだろうか。
「浪江事業所の発表後、多くの企業に関心を持って頂いています。これからは他の自動車メーカーが作ったEVの使用済みリチウムイオンバッテリーをどうするかという話も出てくるでしょう。その際、バッテリー情報を開示していただければ、検査して品質を見極め、レベル分けをして再利用につなげることは弊社でできます。また、競合であるために情報開示ができない場合でも、性能測定方法を教えていただければ、それを基にレベルを分けることもできると思います」
「回収バッテリーの運搬や性能・品質によるグループ分けなど、競合他社と協調できる領域はあると思いますし、各社が弊社でやってきたことを新たに始めるとなれば、それは大変な労力と時間を要しますから、協力していけるのではないかと考えています」
「その上で、リチウムイオンバッテリーで使われる貴重な金属はすでに高騰しはじめています。また法規制において、たとえば中国では、販売したEVやPHVの使用済みリチウムイオンバッテリーはメーカーが回収すべきとなっています。それを、各自動車メーカーが個別にやっていたのでは大変です。そうした情勢からも、EVで使用済みとなったリチウムイオンバッテリーは再利用すべきであり、その運用面で各メーカーが協調することはできると考えます」
牧野氏が先駆者としての知見をいかし、メーカーの壁を越えた協調を目指す姿勢には、EVの充電器設置のため、経済産業省が補助金制度を実施した際、補助金で賄いきれない分を自動車メーカー4社(トヨタ、日産、ホンダ、三菱)で協力し、補助する制度に主要メンバーとして参画した過去の経験も生きているはずだ。
「何より、北米駐在の頃からEVに乗り、EVを普及させたいという個人的な気持ちが強いからではないでしょうか。その実現のためには、大同団結でも何でもする。ことに海外とのやりとりでは、“日本丸”として動くことも大切ではないでしょうか。もちろん、弊社が動くときには、日産や住友商事に許可を得る必要がありますが」
牧野氏は、ことを動かすことのできる人物である。その源は情熱の一言に尽きる。彼のやってきたことを振り返れば、いまさら言葉にする必要もないだろう。そういう人物が、未来を動かしていくのである。