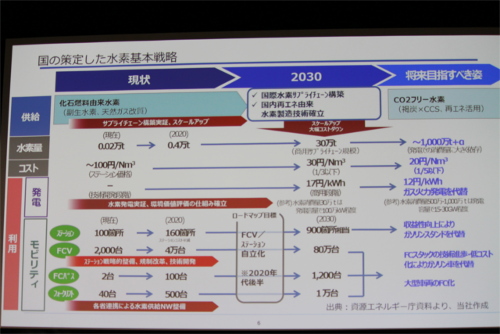水素ステーションの建設費を低減
まず新会社は水素ステーションの整備方針を提示し、広くインフラ事業者に参画を呼び掛ける。参画したい事業者は新会社に水素ステーションの整備計画を提出、同社と新会社は共同で当局に補助金を申請し、共同で施設を建設する。施設ができたらインフラ事業者は新会社にこれを資産譲渡する。新会社は譲渡を受けたステーションの運営をインフラ事業者に委託する。これが流れだ。
従来、ステーションの建設には場所や要件などにもよるが1基あたり4~5億円かかっていた。ここに国や自治体からの補助金が50%くらい入るわけだが、新会社の画期的なところは、資金を提供する参加者として、豊田通商と日本政策投資銀行(DBJ)という投資家が入っているところだ。この投資家から建設費の10~20%の資金が出てくるというのがおおざっぱなイメージだという。
金融投資家の参加メンバーは増やしていく方針で、現在も数社と交渉中とのこと。FCVが普及するかどうかは現状、誰にも正確に見通せないわけだから投資にはリスクが伴うが、DBJの穴山眞常務執行役員は「(新会社は)業界をこえて日本の最強メンバーが集まっているので、参加者でリスクを分散できるのであれば、支援できると考える。FCVが普及すればアップサイドも狙える」との考えを示す。
水素社会を牽引するFCVは普及するか、鍵を握るのは…
日本企業の「最強メンバー」が集まり、政府も後押しする姿勢を示す今回の新会社だが、実際に、水素ステーションの普及が同社を中心に進んだとしても、FCVを筆頭とする需要サイドにボリュームが出てこなければ、水素充填施設の稼働率は上がっていきそうにない。
FCVが実際に普及するかどうかについて、新会社に参加するトヨタの寺師茂樹副社長は「FCVやEV(電気自動車)といったクルマの普及率は、グローバルで見ると現状で1%以下。これがどうなるかはお客様、市場が決めることだが、何を提供できるかが自分たちの課題だ。従来の(エンジンで動く)クルマよりも『こういういいところがある』『買ってみたい』と思ってもらえるような、付加価値をいかに付けるか」が重要との見方を示していた。
-

トヨタは風力で発電した電力を水素に変え、それを近隣の工場などに運んで燃料電池フォークリフトに供給するという実証も行っていた
消費者は欲しいクルマを買うだろうし、エンジンで動くクルマが無くなると決まった時、選択肢がますます増えていきそうなEVから次のクルマを選ぶか、何らかの理由でFCVにするかは、消費者が付加価値を見て判断することだ。そのクルマが格好いい(かわいい)から買う人もいるだろうし、家の近くに水素ステーションがあるからFCVを選ぶ人もいるだろう。買う人が何を重視するかが問題だ。
結局のところ、自動車メーカーが“欲しくなるFCV”を発売できなければ普及は難しそうだ。すでにEVでは、スポーツカーやSUVなど、多種多様なクルマが世の中に登場しつつある。FCVに幅広い選択肢が登場するかどうかも、クルマを選ぶ消費者にとっては重要な要素となりそうだ。