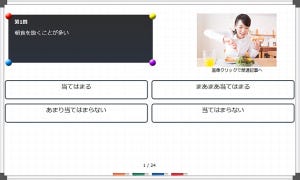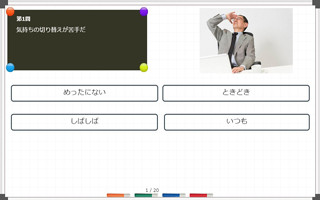Honda歩行アシストのこの驚異の能力を支える機能は「測定と操作」にある。同機器は、股関節の角度を感知するセンサーを内蔵しており、足を振り上げる力である「屈曲」と後ろにける力である「伸展」が測定できる。測定したデータはタブレットで確認でき、個人の症状に合わせて設定を操作しサポートする力を変えられるというわけだ。
この発想のベースには、伊藤さんの経験が生かされている。伊藤さんはかつてF1チームのエンジニアとして活躍しており、伝説的ドライバーの故アイルトン・セナ氏のマシーン整備などを手掛けていた。
F1では、リアルタイムでのエンジン回転数などのデータ解析が欠かせないが、それを可能にしているが「テレメーター」と呼ばれるシステム。レース走行中のマシーンから送られたデータがレース場のコンピューターを経由して別の場所にある解析室に届けられ、その解析結果が現場にフィードバックされるという仕組みだ。この手法がHonda歩行アシストに応用されている。
「技術をもって人間に奉仕する」
ただ、子供用アシストの実用化はHonda歩行アシストの機能をもってしても一筋縄ではいかない。脳性まひの男子のように、「歩くという感覚そのもの」が欠如している子ども相手では、これまでと勝手が違うからだ。「Honda歩行アシストをそのまま小さくすればいい」という単純な問題ではない。
実用化のためにはさらなるデータが必要と思い立った伊藤さんは、脳性まひの男子に2週間継続して子供用アシストを使用してもらうことを決意。男子宅に機器を貸し出し、その効果を見ることにした。
その男子は、つえを用いた歩行訓練とは別に、自宅内で壁に手をついた状態での横歩きをする訓練もしている。ただ、左足の筋力が弱いそうで、途中でしゃがんでしまう姿が映し出されていた。だが2週間の"訓練後"は、一度も休まずに壁の端から端まで横歩きができるようになっており、スピードもアップしていた。
中学から高校生にかけては、身長が伸びて体重も増える。その結果として、骨は伸びるが、筋肉は伸びずに膝がかたくなる。そのため、中学生時代にどれだけ歩き続けることができるかが、将来の歩行を可能にするための分水嶺(ぶんすいれい)になるという。脳性まひの男子を含め、残された時間が少ない患者は世に多数いる。子供用アシスト実用化に向け、伊藤さんたちの厳しい闘いは続く。
それでも、同社創業者の故本田宗一郎氏の「我々は技術会社である限りは、技術をもって人間に奉仕する。技術は人間のためにあるんだ」という言葉を常に胸に秘める伊藤さんは、1歩前進した手ごたえを感じていたようだ。
「あとはどういう設定をするといいかそういうところをしっかりと見極めて、もう少し幅広く勉強しないと一気に商品化まではいかないと思うが、非常に役に立つのではないかという自信は持てた」。