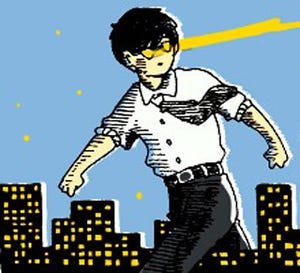|
---------------------------------------------------------------------------
ドラマにありがちなシチュエーション、バラエティで一瞬だけ静まる瞬間、
わずかに取り乱すニュースキャスター……テレビが繰り広げるワンシーン。
敢えて人名も番組名も出さず、ある一瞬だけにフォーカスする異色のテレビ論。
その視点からは、仕事でも人生の様々なシーンでも役立つ(かもしれない)
「ものの見方」が見えてくる。
ライター・武田砂鉄さんが
執拗にワンシーンを追い求める連載です。
---------------------------------------------------------------------------
テレビが流し続ける涙の総量
「涙は女の武器だ」なんて平気で言っちゃう人は、その話法があまりに錆び付いていて言葉以外の武器が必要だなぁと心配になるが、涙を武器にしているのは、明らかに女よりテレビである。1週間のテレビ欄を隅々まで見渡せば、「念願のオーロラ旅。その絶景に涙、涙、涙」「生き別れた母と20年ぶりの再会……スタジオ大号泣」「ケガとの戦い。マウンドでは目に光るものが」と、涙があちこちに点在している。少し前に『1リットルの涙』という作品があったが、ラテ欄には、毎日500ミリリットルくらいの涙が溜まっている気配があり、こうなると年間180リットル程度になる計算だから、なんだかもう大変な事態である。
泣いている誰かを「泣くんじゃねぇ!」と叱りつけることで更に泣かせてしまい、その様子を恍惚とした表情で見届ける熱血教師のような心意気は、どこで生じていようとも大嫌いだ。むしろ、「泣きたい時は泣けばいい」という80年代J-POPのような心がけに賛同してきた。叱咤にしろ感動にしろ、私たちは「泣きすぎている」「泣かせすぎている」という自覚をいい加減持たないと、涙が洪水となって、人の感情の侘び寂びをかっさらってしまう。テレビの涙は、なぜ1リットルではおさまらずに週に3、4リットルもたまってしまうのか。それは、泣かなくてもいいのに泣いているから、に違いない。
負けたチームの9割の選手がむせび泣く高校野球
昔から、泣かなくてもいいのに泣いている人が嫌いだった。生徒会長は男子、その会長を支える副会長に名乗り出そうなタイプの女子・山田は、予想通り、副会長になった。彼女は、ここで泣けば共感を得られるという場面で的確に涙を流す才能があり、誰かの飼い猫がいなくなったと聞けば泣き、学校に講演しに来たエッセイストの思い出話を聞けば泣き、修学旅行の訪問先で戦争体験を語るおじいさんの前で声をあげて泣いていた。バファリンの半分が優しさでできているならば、彼女の半分は涙でできているほどに涙を出しまくっていたが、体の半分が邪念、もう半分が嫉妬でできていた当時の自分は「あいつ、いっつも都合良く泣いているよなぁ。ここぞってときに必ず泣いて、すぐにケロッとするんだから」と数少ない友人と談義していた。話を聞いて泣いた直後の夕食の場で、誰よりも大きな声で破顔する彼女。しかし、そんな適応能力があってこその副会長の座だったのだろう。
山田の存在を強烈に記憶している。今、テレビをつけて「その場のおおよそが泣いている場面でちっとも泣いていない人」に共感を寄せるようになったのは、山田の反動かもしれない。この季節、観る気はないのに、時折、高校野球にチャンネルを合わせる。試合が終わりそうな場面ならば、さすがにそのままにしておく。9回裏、2アウトランナー無し、最後の最後で代打で登場した3年生。内野ゴロを放った彼は、お約束のヘッドスライディングだ。そのまま駆け抜けたほうが早いという説もあるし、あれによって審判の判断基準を揺さぶり多少のロスを補うという説もある。いずれにせよ、そのヘッドスライディングによって試合が終了した途端、道が閉ざされた選手の9割がむせび泣く。泥と汗に涙が入り交じった表情は、青春そのものだ。
代打で登場してレフトフライに終わった選手が泣いていない
勝者敗者ともに、応援団が集うアルプススタンドの前で挨拶をする。勝ったチームは、ぴょんぴょん飛び跳ねてガッツポーズを繰り返している。カメラマンも、辺り一面が喜んでいるので、誰を映すか、最適な構図を探すのに忙しそうだ。片や、負けたチームである。しんみりと1列に並んだ選手に動きはない。大変失礼ながら丸坊主の高校野球児は泣きじゃくるとおおよそ同じ顔をしているので、カメラマンも退屈そうだ。風に揺られるチューリップ畑を映すように、左から右へと均等配分でカメラを回していく。
こんな時、私はテレビの前で身構える。泣きじゃくる選手と泣きじゃくる選手の間に時折、泣きじゃくらないどころか、ちっとも涙を流さない選手がいるのである。じっと前を見据えている。こんな時こそ毅然としていなければならないという責任感の強いキャプテン……かと思って調べてみれば、終盤に代打で登場してレフトフライに終わった選手だと分かる。試合に出られなかったベンチの選手も、不甲斐ない結果を悔しがるスタメン陣も、県予選からずっと頼りにされてきた得意のストレートが高めに浮いて打ち込まれてしまったエースも、押し並べて泣いている。でも、途中出場の彼だけが、すべてを悟ったかのような目をしている。
明後日から夏期講習だなと頭を切り替えているのか
彼は何を考えているのか。「もう終わったからこれからは受験勉強を頑張んないと。最初の試合で打ったタイムリー2ベースは快心の一撃だったし、あの打席をスカウトが見てくれていればドラフト5位くらいでなんとか指名してくれる可能性もあるのではないか。バカ言え、そんなに甘くない。実家の文房具屋を継ぐ選択肢は今のオレにはない。オヤジはまだその線を期待しているかもしれないが、オレは断る。甲子園が終わった今、改めてはっきりと伝えなければいけない。そのためにも、ここからの半年で然るべき進路に向かわないといけない。そう簡単なことではないけれど」と考えている彼は、ただただ泣きじゃくる皆を横目に、すっかり前に向かって歩き始めているのである。すべて想像だが。
彼らを讃えるアルプススタンドでも同じ現象が起きている。控えの選手たち、チアリーダー、応援団、押し並べて泣いている。肩を組んで泣いている。抱き合って泣いている。OBや保護者の面々は、顔を上げんかい、おまえたちは良くやった、と精一杯の拍手を送っている。しかし、ここにもいるのである。泣かない控え選手、拍手を送らないオジさんが。後者はこの後の飲み会に心が移っている可能性が否めないが、泣かない前者は、明後日からは夏期講習だなと早めに頭を切り替えているのだろうか。その9割が同じ表情をしている時に残りの1割で居続けるというのは、よほどの信念がなければ難しい。それに、人はカメラを向けられた時、その場で求められている最適の表情を自然と作り出してしまう性向を持つから、あの場面での「泣かない」には、よほどの信念を感じるのだ。
「寂しくなりますね」と声をかけて泣かせる
涙を流し続けるテレビは、こらえきれない涙とそうでもない涙を区分けせずに押し並べて必要な涙として取り扱うものだから、受け取るこちらも、涙というものをランク付けしてはいけないと思い込むようになった。先日、葡萄ジュースがそろそろ賞味期限切れになるはずだと思い、冷蔵庫のあるリビングに向かうと、妻が韓流ドラマを観ていた。いかにも御曹司役の恰好をした青年が、走らせていた外車を一旦路肩に停止した途端に突っ伏し、声をあげて泣き始めた。その泣き声を正確に書き起こすと「ウァァァァァァン、ウォォォォォォン、アァァァァァァン」なのである。豪快に泣きすぎている。しかも、顔をあげた彼にズームするも、彼の目にも頬にも、涙の形跡はない。声の大きさのみで泣くシーンを乗り切っていた。
これを見て、ついつい「演技が下手だねぇ」と漏らす。そこで、はたと気づく。むしろ私たちは涙がこぼれ落ちる瞬間を重宝しすぎているのではないか。ただただ涙の有無で評価してはいまいか。ドラマだけではない。近しい人が亡くなり、気丈に振る舞う有名人に、先んじてウルウル状態の記者が畳みかける。「最期に話した言葉は……」というような疑問系ならばまだしも、「これからはお一人。寂しくなりますね……」などと、土足で踏み込む設問も少なくない。泣かせるべきところで泣かせるのが彼らの仕事でもあるから多少の荒療治は致し方ないのだろうが、その荒療治を引き受けずに涙を流さない人を発見すると、この人頼もしいな、と勝手に誉め称えるのだった。
修学旅行の集合写真で下を向き続けた石崎君
泣かない人が好きだ。どんな攻めを食らっても屈しない。ここで泣いたら、その顔のアップ写真がニュースサイトに配信されて検索ワードランキングに食い込んでくることを、彼は、彼女は知っているのだ。泣かせにかかるプライドと泣かないプライドとのぶつかり合い。負けた高校野球チームで、たった1人涙を流さなかったレフトフライの男は、メディアが求める構図に抗っていたのではないか。彼一人がちっとも泣かないことで何が起きるか。「強豪・○○商業、2回戦で散る」というニュースに使う映像や写真として、1列に並んだ全体写真が使いにくくなるのである。なぜって、彼だけものすごく真顔だから。
今でも手元にあるが、副会長になった山田を私と同様に嫌っていた石崎は、修学旅行の集合写真で必ず下を向いた。カメラマンが「1足す1は?」と叫ぶのに合わせて下を向いていた。学校から雇われたカメラマンは、立場上、直接名指しをすることはできなかったのか、「もういちど撮りまーす」と何度か繰り返すものの、いつまでも下を向く彼に屈した。長崎ハウステンボスでも浦上天主堂でも、彼は下を向いた。それは、副会長になる山田的な善良さに必死に抗う手段に思えた。青臭いけれど、今でも彼のスタンスに共振する。「その場のおおよそが泣いている場面でちっとも泣いていない人」も同様だ。それは、ただただ醒めている人、ではなくて、明確な主張がある。そんな人をテレビで見つけると、テレビの前でたった1人の私設応援団を立ち上げ、エールを送る。泣かないお前が正しいんだ。
<著者プロフィール>
武田砂鉄
ライター/編集。1982年生まれ。2014年秋、出版社勤務を経てフリーへ。「CINRA.NET」「cakes」「Yahoo!ニュース個人」「beatleg」「TRASH-UP!!」「LITERA」で連載を持ち、雑誌「AERA」「SPA!」「週刊金曜日」「beatleg」「STRANGE DAYS」等で執筆中。近著に『紋切型社会 言葉で固まる現代を解きほぐす』(朝日出版社)がある。
イラスト: 川崎タカオ