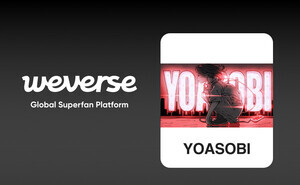130組以上の世界のアーティストが参加し、メッセージ投稿やライブ配信、Eコマースなど、ファンとの活発なコミュニケーションを実現する韓国発のプラットフォームサービス「Weverse(ウィバース)」。昨年10月に日本法人・WEVERSE JAPANのGMに就任したムン・ジス氏が取材に応じた。
アプリのダウンロード数、ユーザー数、ライブ配信の再生数など、右肩上がりで順調に推移する中、古くは「追っかけ」「親衛隊」などが存在し、ファン文化が成熟している日本において、大きな可能性を感じているというムン氏は、日本市場をどのように捉えているのか。今後の展望を含め、話を聞いた――。
アーティスト&ユーザーの声を積極反映
Weverseは245の国と地域で利用され、商品の配送可能な国と地域は209にのぼり、15言語のリアルタイム翻訳に対応している。昨年6月には累計アプリダウンロード数が1億を、同7月にはMAU(月間アクティブユーザー数)が1,000万を突破し、累計ライブ再生数は20億を超えた。
このように順調に推移する背景として、ムン氏は「数ある“推し活”に必要な機能が、一つのアプリにそろっている」と挙げるが、それに加えて特徴的なのが、アーティスト自身の声を積極的に取り入れていることだ。
アーティストからの意見を受けて、アーティスト同士の合同ライブ配信機能の導入を決めたほか、「Weverse LIVE中の自分のコメント、ユーザーからのチャットがリアルタイム翻訳されると、世界中のファンとコミュニケーションが取れるからそういう機能が欲しいな」という希望を受け、その機能の実装も検討しているという。
「コミュニティのフィード(ファンとアーティストがテキストで会話する空間)で“Weverseがこうなればいいな”という投稿もチェックしますし、一部のアーティストは、Weverseやレーベル(事務所)の担当者にも話してくれるんです。すべて実現する約束まではできないのですが、そういうアーティストやファンからの声をこまめにヒアリングしながら、サービスを改善しています」(ムン氏、以下同)と、柔軟な姿勢が強みになっている。
地域の独自文化を尊重するグローバルサービスに
この4月からサービスコンセプトとして、「Global Superfan Platform(グローバル・スーパーファン・プラットフォーム)」を掲げている。「スーパーファン」とは、アーティストのコンテンツ(アルバム・コンサートなど)を積極的に消費し、特別な体験を望んで購買意欲を高く持ち、誠実で熱心に心を寄せるファンと定義。ムン氏いわく「常に推し活を楽しんでいる方」との親和性の高いプラットフォームを目指すが、日本においては、スーパーファンのポテンシャルが高いと捉えている。
「日本はファンダムライフスタイルの歴史が長く、文化として強く根付いています。80年代からアーティストやアニメなどの推し活があり、それが世界に広がっているのだと思います」
ただ、推し活文化のデジタル化という点において、おくれを取っている現実がある日本。そこに、Weverseというプラットフォームが入ることによってデジタル化を補い、「もっと気軽に、より便利に使えるようになっていけたら、より高いポテンシャルを発揮できると思います」と期待を示した。
日本市場における特有の文化の一つとして挙げるのは、コンビニ決済。この対応を韓国の開発チームに持ちかけたところ、不思議がられたという。
「都市から離れた地域では、コンビニがライフスタイルの拠点になっているところもあり、現金で払うほうが慣れていたり、アナログな方法に安心感を覚える人もいると思います。韓国にはない決済方式なこともあり、“なんでコンビニ決済が必要なのか?”という説明が必要でした。細かく見ていくとローカライズが必要な部分はあって、各地域の独自の文化を尊重してバランスを取り、現地化をきめ細かく行ってこそ、グローバルサービスとしてさらに長く利用してもらえるサービスになると思います。これらの部分を調整することが日本法人の役割です」