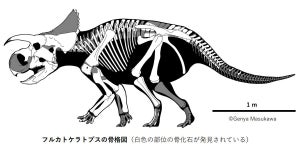国立科学博物館は3月27日、神奈川県川崎市の民家の水槽から発生したマリモ類がモトスマリモ (Aegagropilopsis clavuligera: アエガグロピロプシス・クラブリゲラ)であることを発表した。
このマリモは、川崎市の民家で、熱帯魚(コリドラス)を飼育していた水槽にマリモに似た藻類が大量に発生したことから、国立科学博物館に持ち込まれた。遺伝子を解析した結果、オランダの熱帯水族館から報告されたモトスマリモ(Aegagropilopsis clavuligera:アエガグロピロプシス・クラブリゲラ)の配列と一致した。また、顕微鏡観察の結果、形態的特徴も種と矛盾が見られなかった。
国内でのモトスマリモの発生報告例は、2022年に山梨県甲府の民家で見つかったものに次いで2例目となる。甲府の民家のものと今回川崎の民家で見つかったものは、遺伝的に違いがみられることから由来が異なると考えられるという。
マリモに似た球状の群体をつくるものとしては、「マリモ」「タテヤママリモ」「モトスマリモ」があるが、タテヤママリモとモトスマリモ(Aegagropilopsis属)は、湖沼でのみ見られるマリモ(近縁のAegagropila属)と異なり、人為的な環境下で発生しやすいと考えられた。
国立科学博物館では、更なる発生例を探している。