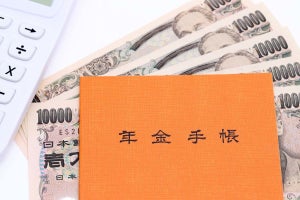厚生年金保険料が高いと感じている人も多いのではないでしょうか。厚生年金の保険料率は一律18.3.%ですが、標準報酬月額や標準賞与額が人によって異なるため、保険料に差が生じます。
自分が払っている厚生年金保険料や、いつまで払うのか知っておくことは大変重要です。そこで本記事では、厚生年金保険料の仕組みや計算方法などについて、くわしくご紹介します。
厚生年金保険料とは
厚生年金保険は、下記の1か2に該当する70歳未満の人が、原則として全員加入する公的年金制度です。
1.所定労働時間が週30時間以上
2.下記すべての条件を満たしている
a.所定労働時間が週20時間以上
b.月額賃金が8.8万円以上
c.勤務期間1年以上見込み
d.従業員規模501人以上の企業で勤務している。
500人以下の場合は、加入について労使で合意がなされている
e.学生ではない
被保険者は厚生年金保険料を納めなければいけません。なお、厚生年金は国が管理・運営しているため、保険料は税金と同じく給与から天引きされます。
厚生年金と国民年金の違い
厚生年金保険の加入者は厚生年金制度を通じて国民年金にも加入しているため、厚生年金と国民年金が合わせて給付されます。厚生年金と国民年金の主な違いは次のとおりです。
| 厚生年金 | 国民年金 | |
|---|---|---|
| 対象 | 厚生年金保険適用事業所に勤務する70歳未満の人 | 国内に在住する20歳以上60歳未満の人 |
| 年金保険料 | 18.3%を会社と折半 (自己負担は9.15%) |
一律月額16,540円(令和2年度) |
| 納付方法 | 給与から天引き | 自分で納付 |
| 給付される年金 | 基礎年金+厚生年金 | 基礎年金 |
厚生年金保険と厚生年金基金の違い
厚生年金基金とは、企業が国に代わって厚生年金の一部積み立てと給付を行う制度です。従業員の老後を支えるため、国民年金+厚生年金に加えて支給されます。
厚生年金基金は従業員にとって嬉しい制度ですが、バブル崩壊後は財政の悪化によって事実上の解散が相次ぎました。2013年には法改正が行われ、2014年4月1日以降の新規設立は禁止されています。
厚生年金保険料の計算方法とは
厚生年金保険料は、下記の計算式で算出されます。
・月給に対する保険料=標準報酬月額×18.3%
・賞与に対する保険料=標準賞与額×18.3%
保険料は会社と折半しているため、自己負担分は「標準報酬月額×9.15%」と「標準賞与額×9.15%」です。
標準報酬月額とは
会社から支給される基本給に、各種手当を加えた1カ月の総支給額を「報酬月額」と呼びます。厚生年金では報酬月額が32段階の等級に区分され、各等級に該当した金額を「標準報酬月額」と呼んでいます。
引用:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)一般・坑内員・船員の被保険者の方(令和3年度版)」
たとえば、報酬月額が26万5,000円の場合は「25万円以上27万円未満」の「第17級」に該当するため、標準報酬月額は「26万円」です。
なお、標準報酬月額は、主に次の方法で決まります。
1.定時決定
事業主が4月から6月の3ヶ月分の給与平均額を算出して、日本年金機構へ届け出る方法です。各被保険者の標準報酬月額は、届け出を受けた厚生労働大臣が決定します。この方法で決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。
2.随時改定
被保険者の状況に応じて標準報酬月額を改定する方法です。随時改定の対象となるためには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
- 昇給や降給など固定的賃金に変動があった
- 変動した月から3カ月間に標準報酬月額が2等級以上変わった
- 3カ月間の各月に支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある
標準賞与額とは
標準賞与額とは、税引き前の賞与から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。ただし、1カ月150万円を超える場合は「150万円」とされます。
厚生年金保険料の計算例
下記のケースで厚生年金保険料がいくらになるのかを計算してみましょう。
・給与の額面が4月31万円、5月32万円、6月29万円
・標準報酬月額は定時決定による
・夏のボーナスは50万円、冬は55万円
3カ月の給与平均額は31万円で、厚生年金保険料額表の19等級に該当します。標準月額報酬は30万円です。30万円に自己負担分9.15%を掛けると月額保険証が27,450円と算出できます。年間の厚生年金保険料は32万9,400円です。
標準賞与額にかかる保険料は50万円と55万円にそれぞれ9.15%を掛けるため、45,750円と50,325円になります。
年間に支払う厚生年金保険料の自己負担分総額は、下記のとおりです。
- 32万9,400円+45,750円+50,325円=42万5,475円
厚生年金保険料は中途退職するとどうなる?
厚生年金保険料は基本的に月単位で計算されるため、月の途中で退職した場合は、資格を喪失した日の前月分まで保険料を納めます。
ただし、資格喪失日は「退職した日の翌日」となるため、月の末日に退職した場合は翌月1日が資格喪失日になります。この場合は、月の途中で退職したときよりも1カ月分多く保険料を支払うことになるので注意が必要です。
なお、同月中に別の会社へ転職をした場合は、資格を喪失した厚生年金の保険料を納付する必要はありません。
産前産後と育児中の厚生年金保険料
ここからは、産休や育休中の厚生年金保険料について、くわしく解説していきます。
産休中と育休中は厚生年金保険料が免除される
産前産後休業や育児休業などの期間中は、厚生年金保険料の支払いが免除されます。免除される期間は「休業の開始月」から「終了前月」までです。日割り計算は行われません。
なお、厚生年金保険料の免除を受けるためには、事業主による「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」の届け出が必要です。産休や育休を開始すれば自動的に免除されるわけではないので注意しましょう。
産休や育休から復帰したあとは、再び厚生年金保険料を払います。しかし、休業前と同じように働くのが困難で短時間勤務になったとしても、休業前の標準報酬月額で決まった保険料を支払わなければいけません。
このような場合は、休業終了日が属している月から3カ月間に受け取った給与を基にして、新たに標準報酬月額を決めることができます。たとえば、休業終了日が7月13日の場合は、7月・8月・9月の3カ月分が新たな標準報酬月額の対象です。
短時間勤務の3カ月分を基に標準報酬月額が改訂されるため、支払う保険料も少なくなります。なお、1月から6月に標準報酬月額が改訂された場合は同年の8月まで、7月から12月の間に改定されたときには翌年8月までが、新たな標準報酬月額の適用期間です。
ただし、この措置を受けるには下記2つの要件を満たさなければいけません。
1.産休や育休前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額を比較したときに1等級以上の差が生じる
2.休業終了後の翌日が属す月から3カ月のうち、最低でも1カ月は支払基礎日数が17日以上ある
産休や育休を取得しても厚生年金の支給額を下げない方法
産休や育休後の改訂によって保険料が下がると、将来受け取る年金も少なくなってしまいます。このようなことがないように設けられているのが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という制度です。
この制度を利用すれば、育児開始日から子供が3歳になるまでの期間、休業前の標準報酬月額に基づいて年金の給付額が算出されます。
保険料が安くなっても標準報酬月額は変わらないと「みなされる」ため、年金の支給額は下がりません。
厚生年金保険料を計算してみよう!
厚生年金保険料の料率は一律で18.3%ですが、会社と折半しているので自己負担分は9.15%となります。保険料は標準報酬月額や標準賞与額によって変わるため、計算例を参考にして自分の厚生年金保険料を算出してみましょう。
保険料の免除や、年金支給額が下がらないようにする「みなし措置」などの制度を利用すれば、産休や育休時の負担も軽減されます。