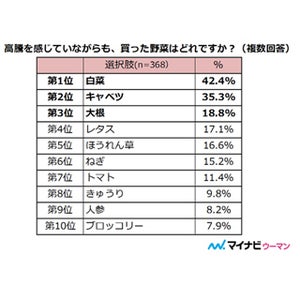3月になると、そこかしこから春の便りが届きます。3月5日の啓蟄(けいちつ)は、大地が温まり、冬眠をしていた地中の虫が春の陽気に誘われて穴から出てくる頃といわれています。3月20日の春分の日は昼と夜の長さがほぼ同じになり、この日を境に昼間の時間が長くなっていき、気持ちも明るくなりそうですね。まだ寒い日もありますが、暖かい日差しを感じされる日もだんだんと増えてきます。春がそこまできている3月に食べたい旬の食材をご紹介します。
3月が旬の野菜
3月になると、引き続き冬の葉物類に加えて、野山で芽を出す山菜類がたくさん登場します。独特の香りが楽しめる野菜を食べて、一足早い春を感じてみてはいかがでしょう。
からし菜
からし菜は、アブラナの一種で、チンゲンサイやハクサイなどと同じ仲間です。種から和からしを作るからし菜はその菜葉です。葉や茎はからし特有のピリッとした辛味があり、これがお浸しや漬物にしたときに味のアクセントになります。タカナ(高菜)やわさび菜もからし菜の一種です。
カリウムを多く含み、ナトリウム(塩分)を排泄するので高血圧に効果があります。また、カルシウムをはじめ、マグネシウム、リン、鉄分などのミネラルも豊富で骨を丈夫にする効果も。抗発ガン作用や動脈硬化の予防効果があるとされるβカロテンも豊富に含みます。さらに、葉酸を多く含んでいるので、不足気味になる妊婦さんにとってはお勧めの野菜といえます。
- 美味しいからし菜の選び方
葉の色が濃く鮮やかなグリーンの物で、葉先までシャッキリと元気なものを選びましょう。鮮度が落ちると葉が黄色っぽくなります。
- 保存方法
乾燥しないように濡れた新聞紙などで包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室へ保存します。それほど長持ちする野菜ではないので新鮮なうちに食べきりましょう。下茹でしてから小分けにして冷凍すると、ひと月くらいならからし菜特有の風味は味わうことができます。
たらの芽
たらの芽はウコギ科のタラノキの新芽で、もっちりした食感が春を伝える食材として人気があります。かつては旬の時期だけ味わえる貴重な食材でしたが、今は栽培も進んでおり、早い時期から比較的長期間スーパーの棚に並ぶようになりました。山形をはじめ徳島や富山、島根など各地でハウスでの水耕栽培も行われています。
カリウムを多く含むので、ナトリウム(塩分)を体外に排出する働きがあり、高血圧への効果が期待できます。マグネシウム、リン、鉄分などのミネラルを含み、β-カロテンも豊富に含んでいます。また、健胃、強壮、強精作用があると言われています。
- 美味しいたらの芽の選び方
たらの芽は、育ちすぎると苦みやエグミが強くなるので、芽のつぼみ状のところが開いて3~5cm位に芽が伸びたくらいの物がアクが少なくて食べやすいです。
- 保存方法
日持ちしないし、香りが大切な食材なので、新鮮なうちに早く食べたい食材です。保存するときは、乾燥しないように新聞紙などに包み、穴をあけたポリ袋などに入れて冷蔵庫の野菜室に入れましょう。調理する際、天ぷら以外はアク抜きが必要になります。
ふきのとう
ふきのとうはキク科フキ属の多年草で、日本原産の山菜のひとつとして知られ、全国の山野に自生しています。ふきのとうはフキの花で、咲いた後に地下茎から伸びる葉(ふき)が出てくるという、花と葉柄が別々の時期に地下から出てくる面白い植物です。早春を表現する山菜として日本料理には欠かせない食材のひとつで、独特な芳香と苦味があります。
カリウムを豊富に含むため、高血圧に効果が期待できます。また、苦み成分のアルカノイドは肝機能を強化し、新陳代謝を促進するといわれています。ケンフェールは活性酸素などの発ガン物質を抑制する効果もあると言われています。香り成分のフキノリドは胃腸の働きを良くする健胃効果があると考えられています。
- 美味しいふきのとうの選び方
鮮度がとても重要で、摘んだばかりのふきのとうは、とても清々しい香りがあり、エグミも少ないのですが、時間と共にアクや苦み、エグミが強くなってしまいます。根元の切り口を見て、黒ずんでいないもの、締まりがあり、つぼみがまだ堅く閉じていて、周りの葉で花芽が見え始めるぐらいのものを選びましょう。
- 保存方法
乾燥しやすいので、ポリ袋などに入れて冷蔵庫の野菜室に入れますが、できるだけ早めに食べることをお勧めします。長く保存する場合は、下茹でしてアクを抜いた状態にしてから冷凍します。
うど(独活)
うどはウコギ科タラノキ属の多年草で、「うど」と「山うど」(天然もの)は同じものです。昔から“うどの大木”という言い回しがありますが、実際には大木にはならず、大きくなってもせいぜい3mぐらいの草です。旬の時期には天然ものが出回りますが、一般にスーパーなどに並んでいるのはほとんどが栽培物です。独特の香りを持ち、苦味を持っているので、好き嫌いが分かれます。産地は栃木、群馬など関東各地で多く栽培されており、東京の三鷹市、立川市でも多く栽培されています。
クロロゲン酸という抗酸化性を示す物質を含んでおり、がんの発生予防や日焼けによるメラニンの抑制などの効果があると言われているので、美容にいいかもしれませんね。疲れにくく、抵抗力を保つと言われるアスパラギン酸も豊富に含み、うどが含む成分のジテルペンアルデヒドは血液循環をよくし、疲労回復に効果があると言われています。
- 美味しいうどの選び方
うどは、全体に白くうぶ毛が密についており、太く先の芽の方までまっすぐ伸びているものが良いです。天然物の「山うど」は、先の芽がみずみずしく、茎が太く短く、全体に産毛がびっしり付いているものを選びましょう。
- 保存方法
陽にあたらないよう湿らせた新聞紙などで包み、冷暗所で保存します。香りを楽しむ山菜なのでなるべく早く食べ切りましょう。長期保存は下ゆでしたものを小分けにして冷凍します。
あさつき(浅葱)
あさつきはネギとは違う独立した種類で辛みの強いのが特徴です。青ネギ状のものと東北特産の新芽状のものがあります。冬から早春にかけてが旬で、夏になると葉が枯れ、地下の球根だけの休眠状態に入ります。関西をはじめ多くは細い青ネギ状に成長したものを食用にしていますが、東北地方では冬から春に球根から伸びてきた新芽の部分を収穫したものを春の味覚として楽しみ、山形県では伝統野菜のひとつとして扱っています。
強い香りの成分は硫化アリルで、ビタミンB1の吸収を助け、血行をよくし、疲労物質である乳酸を分解する作用などがあると言われています。肩こりや疲労回復にも効果が期待できそうですね。硫化アリルは刻むことによって多く作られ、時間と共に消えてしまうので、食べる直前に調理することが大切です。他にもビタミンB1やB2、B6、パントテン酸などが多く含まれており栄養素の代謝吸収を高めることで、身体に活力を与えてくれます。
- 美味しいあさつきの選び方
青ネギ状のものは、葉先までピンとしていて、なるべく色が濃いものを選びます。新芽状のものは、収穫後時間と共に切り口から中心部が伸びてくるので、切られた根元を見て判断します。
- 保存方法
湿らせた新聞紙などにくるみ、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れます。できるだけ縦にして入れておく方が曲がらずに長持ちします。
3月が旬の魚類
ワカサギ
ワカサギはシシャモなどと同じキュウリウオ科で、体長15cm前後でスリムで少し側扁し、体色は背が薄い茶色で体側から腹にかけては銀白色です。ウロコは非常にはがれやすく、店頭に並ぶときにはそのほとんどがはがれて無くなっています。産卵を控えた冬から春にかけてのメスは子持ちで美味。漁獲量は青森県、北海道、茨城県、秋田県の4つで全国の9割を占めています。
- 美味しいワカサギの選び方
ワカサギは死んでからの傷みが早いため、できる限り新鮮なものを選びましょう。死後硬直が解けていない硬いものが新鮮なので、柔らかいものや、腹が緩んで裂けそうなものは避けます。表面がみずみずしく艶があり、銀色に光っているものが新鮮なものです。
ハマグリ
国産のハマグリは、沿岸部が昭和の終わり頃から干拓や護岸工事、水質汚染などによって激減し、今では鹿島灘など一部地域以外は絶滅に瀕している状態だそうです。そのため国産のものは高値で、スーパーなどの店頭には中国産のシナハマグリが並んでいます。
ハマグリは2枚の殻がぴったり重なることから「夫婦和合」の意味で縁起が良いとされています。結婚式にハマグリのお吸い物が出るのはこのためで、一生一人の人と添い遂げるようにという願いが込められています。また、3月3日のひなまつりに食べると「良縁」を招くとされ、お吸い物などに欠かせない食材とされています。
- 美味しいハマグリの選び方
生きているものを選びます。水中では水管を伸ばしていても触れると素早く殻を閉じるもの、水揚げされているものはぴったりと殻を閉じているものを選びましょう。ハマグリもアサリと同じように砂を噛んでいることがあるので、調理する際は砂抜きをした方がいいでしょう。砂抜きは、2%から3%ほどの塩水を、ハマグリが3分の2くらい浸る程度に張って、冷暗所に置いてできれば一晩、少なくとも2時間ほどはそっとしておきます。
ハマグリはアノイリナーゼというビタミンB1を壊す酵素を持っているので、生では食べない方が良いです。この酵素は加熱することで不活性化します。また、二枚貝はノロウイルスを持っている可能性もありますが、これも加熱処理する事で死滅させることができます。
まとめ
春の季節を感じさせてくる食材は、香り高いものが多くありますね。春分の日は、春のお彼岸でもあり、家族でお墓まいりをして、「おはぎ」を食べる習慣もあります。別名「ぼたもち」と呼ばれるお菓子ですが、漢字では「牡丹餅」と書き、季節の花にちなんだ名前で呼ばれ、秋のお彼岸に食べる「お萩」と呼び方を区別するという説もあります。日本の季節を楽しむ習慣は楽しいですね。