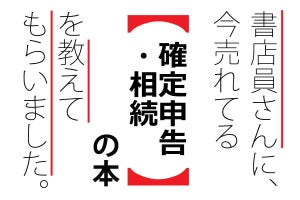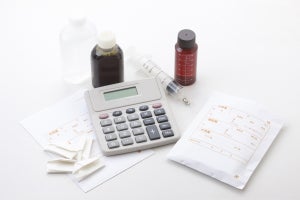給与所得者であっても確定申告を必要とするケースがありますが、ほとんどの方は年末調整だけで、確定申告は必要はないでしょう。このような、本来確定申告の必要とされない給与所得者でも、確定申告をすることによって、所得税が戻ってくるケースがあります。
多少の手間はかかりますが、最近はスマホでも確定申告が可能となりました。どのようなケースが該当するのかみていきましょう。
還付金とは?
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎている場合には、申告(還付申告)すれば税金が返還され、その戻ってくるお金のことを還付金といいます。
還付金は、前年の1月1日~12月末日までに支払った所得税が対象となり、確定申告を行うことで払い過ぎた所得税の還付を受けることができます。確定申告の時期は原則2月16日~3月15日まで、還付される時期は、それからおおむね1カ月~1.5カ月後となります。
還付対象となるケース
一般的な会社員にとって身近な還付対象事例には、以下のようなものがあります。いずれも詳細な要件がありますので事前に確認してください。
●配当所得がある場合
配当所得は、配当金の支払の際に、次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引きます。ただし、確定申告不要制度があり、一定範囲は下記の源泉徴収のみで終了とすることができます。
その年の所得税率が下記の配当に対する源泉徴収税率より下回った場合は、還付申告により、納め過ぎた分が戻ってきます。注意が必要なのは、納め過ぎた所得税は戻ってきますが、配当所得分の収入が増えたことになり、住民税が増えます。所得税の減額分と住民税の増額分を精査する必要がでてくるでしょう。
<上場株式の配当金の源泉徴収税率>
15.315%(他に地方税5%)の税率により、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
<上場株式以外の配当金の源泉徴収税率>
20.42%(地方税なし)の税率により、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
●医療費控除またはセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の場合
1月1日~12月31日までの1年間に、自己または自己と生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
また、通常の医療費控除とのいずれかの選択となりますが、自己または自己と生計を共にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合も、控除を受けることができます。
その際、年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っていることを条件に、支払った合計額の1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)が、セルフメディケーション税制の対象となります。
●雑損控除の場合
自然災害や火災、盗難、横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
●寄付金控除の場合
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
●住宅借入金特別控除の場合
住宅ローン控除としてよく知られた制度です。給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、必要書類を添付して確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
●住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除の場合
住宅耐震改修にかかる耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円)を、その年分の所得税額から控除できます。
住宅特定改修とは、個人が自ら所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等を行った場合、一定の要件で、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
●認定住宅新築等特別税額控除の場合
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅を新築等で取得した場合、一定の要件で、それらの認定基準に適合するために必要となる標準的な増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除することができます。
医療費控除について
比較的多くの方が手続きされる「医療費控除」を受けるには、所定の準備が必要です。明細書のサンプルは国税庁のHPよりエクセル版またはPDF版がダウンロードでき、医療費の明細書の添付が必要です。
還付申告に領収書の添付は不要となりましたが、領収書の保管は一定期間義務付けられています。医療費控除として請求できるものの詳細は、国税庁のHPを参照ください。
通院に必要なバスや電車代も請求できますので、私は下記の医療費明細サンプルを参考に交通費欄を追加してエクセルで集計しています。
高額医療費の還付を受けた場合は、その分を削減して申告します。削減する金額は実際に還付を受けた月ではなく、高額となった対象月分になります。問題は還付申告する2月末の時点では前年の12月分の高額医療費は確定されていない点です。その際は、多めの暫定値を記入して申告することとなります。
予定していた高額医療費として戻ってきた金額に差が生じた場合は、再度還付申告を行えば、その分の所得税は是正されます。
医療費控除できる金額は下記の算定式で算出します。
(支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-{10万円(所得の合計が200万円までの方は所得の合計額の5%)}=医療費控除額(最高200万円)
確定申告は、"会社にお任せ"で済む給与所得者にとっては、かなり面倒なことかもしれません。それでも多少なりとも節税できればうれしいですし、こうした機会に税の仕組みを正確に理解することは大切です。
行政の効率アップのためにネットで納税も良いですが、初回だけは税務署に出向いていろいろ聞きながらしっかり把握するのも悪くはありません。
いまは外出自粛の時ですので別ですが、次回の確定申告の際など、落ち着いていれば出向いてみてはいかがでしょうか。




.jpg)