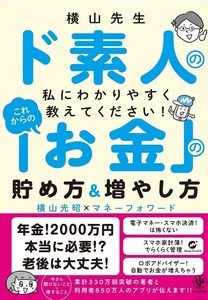今回の増税では全ての商品やサービスなどに一律10%の「標準税率」がかかるのではなく、飲食料品や定期購読契約を結んだ週2回以上発行される新聞には8%の「軽減税率」と2つの税率になります。
これだけならまだしも、10%になると同時にキャッシュレス決済によってポイントが付与される「ポイント還元事業」が2020年6月末まで実施されます。ポイント還元事業では、その事業に登録した中小小売店等でキャッシュレス決済を行った場合は5%、中小規模のフランチャイズでは2%の還元です。
ポイントは、決済をした事業者から後日ポイント還元もしくは、請求時に還元分が値引きされます。還元にも上限を設けている決済事業者もあり、クレジットカード会社の場合1万500円が月の還元の上限となります。電子マネーやQRコード決済では、決済事業者によって1回あたりの上限や1カ月あたりの上限が異なりますので、確認しておくと良いでしょう。
また、1人当たりの上限ではなく、キャッシュレス決済手段1つあたりの上限なので、月の上限に達したクレジットカードがあれば、残りは別のクレジットカードやQRコード決済でするといった使い分けをすると良いでしょう。
ただし、お店によってポイント還元となる決済手段は異なりますので、決済前にお店に確認をするか、店内に貼ってあるポスターの対象決済手段をチェックしましょう。
-

キャッシュレス決済ポスターイメージ 経済産業省HPより
大手コンビニエンスストアでは、一律でキャッシュレス決済での買い物時に、2%の値引きがされます。コンビニエンスストアはポイント還元事業の対象となるコンビニとそうでないコンビニがあるため、全店舗一律で値引きをする対応となりました。
ポイント還元事業の仕組みとは少し異なり、コンビニでキャッシュレス決済をしても、後日ポイントの付与や値引きがされるわけではないので注意が必要です。
大企業のスーパーや百貨店では、今回のポイント還元事業の対象外となるので、ポイント還元率は0です。
-

筆者作成
表をみると、ポイント還元事業に参加している中小規模の店舗で購入すると、実質的な税率が一番低いことがわかります。コンビニや大手スーパーでは、どちらも同じPB(プライベートブランド)商品が売られていることがあります。 PB商品はいつも手頃な価格で購入できる商品ですので、セールといった値引がされない商品です。大手スーパーでキャッシュレス決済で購入してもポイント還元はゼロですが、コンビニで購入すれば2%の値引きになり、コンビニで買った方が表面的には安くなるでしょう。
しかし、大手スーパーでは特定日にそのスーパーの電子マネー等で支払いをすると、ポイント5倍や5%引きがされることもあるので、買うタイミングや支払い方法によっても異なりますので、よく行くスーパーの電子マネーやクレジットカードは作っておくといいでしょう。
同じく表を見ると、コンビニでの飲食料品については増税後に買った方が実質の税負担が少なくなるので、コンビニで調味料などを購入しているなら増税後に買った方がお得になります。
増税前も増税後も、その制度の仕組みをよく理解しておくことが大切であると言えるでしょう。