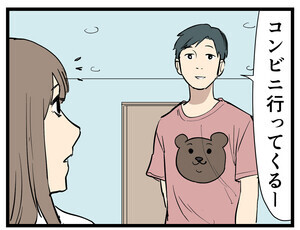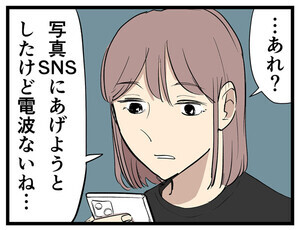THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)やSnow Peak(スノーピーク)など、登山向けアウトドアブランドがアパレルを展開している例はいくつかあるが、2017年に「釣り」の技術を活用した機能性アパレル製品を提供する「D-VEC」が登場した。
「D-VEC」は、釣り人たちの信頼を集める「DAIWA(ダイワ)」ブランドからはじまったファッションブランド。釣り竿に使用されているカーボンファイバーを使った超軽量折りたたみ傘など、釣り具のために生まれた技術を、街で使えるようなアイテムに付加して提供している。
DAIWAブランドでアウトドア向けのウェアを扱ってはいるが、D-VECは、明確にファッションブランドとして展開しており、原宿にショップを出店した後、2018年7月には外苑前にショールームを設置した。
すでに釣り業界で多大な支持を得ているDAIWAブランドとはあえて別の屋号でファッションに打って出た狙いは、どこにあったのだろうか。
今回は、DAIWA、D-VEC、および両ブランドが属するグローブライド(旧ダイワ精工)のブランディングに携わった佐藤可士和氏に、D-VECのロゴマークのデザインや、アパレルブランドを立ち上げた意図、そして今後の展望を聞いた。
「技術力」を感じさせるロゴデザイン
――最初に、D-VECブランドのみならずDAIWAブランドを含めたグローブライドのリブランディングに関わるようになった経緯を教えてください。
もう10年以上前になりますが、旧ダイワ精工が50周年を迎えるタイミングで、リブランディングを行いたい、とお話をいただいたのがきっかけです。まず、ダイワ精工という社名を現在のグローブライドへ変更しました。
そしてフィッシングブランドの「DAIWA」のリニューアルも併せて行いました。諸々の変更は2009年から展開しましたが、もちろんそれ以前から関わらせていただいています。
それから今に至るまで、さまざまなディレクションをさせていただきました。主にグローブライド、DAIWA、そしてアパレルブランドのD-VECですね。
――DAIWAのロゴマークとD-VECのロゴマークは同じパーツで作られています。新しくデザインされたロゴの解説、込められた意味について教えてください。
パーツを共通化したのは、D-VECブランドの初期段階として、DAIWAとのつながりをユーザーに感じていただくことが重要だと考えたためです。今や、釣りを趣味にしている方であれば、ロゴ全体でなくDの部分だけでもDAIWAと認識いただけています。
ですが、公開当初より、最終的にはD-VECのマークだけでコミュニケーションが行えるように設計しています。
――どちらのロゴも直線的なシルエットが印象的です。以前のロゴの曲線的なイメージと対称的ですが、どんな狙いがあるのでしょうか?
DAIWAには、カーボンなどの素材はじめ、ものすごい技術力があります。そういったことを感じさせるようなデザインにしよう、と考えたのが出発点です。
また、元のロゴでは使いにくいシーンがあったことも聞いていて、それを改善することも考えました。旧ロゴはトリコロールカラーだったので製品自体の色と干渉したり、またリールやロッドなど印刷面がごく小さいものに入れたりするのは難しかったそうです。特に後者について、金属製品に刻印したときの見え方も念頭に考えて、現在のものに決めました。
――D-VECのショップではハンガーの中央にロゴが配置されていますし、製品ごとにロゴの入れ方は異なります。各製品へのロゴあるいはマークの配置について、監修は行っていますか?
細かな製品監修は行っていませんが、ブランドごとに傾向はあります。
フィッシングブランドのDAIWAのウェア類では、かなりロゴを大きく入れています。それは、利用シーンが釣りに行った時なので、遠くからでも見えやすく、スポーティなグラフィックとして機能したほうが適しているため、大きく使うことが多くなっています。
一方で、D-VECはアパレルブランドで、街着を前提に考えています。あまりそこで大きくロゴを出してしまうのは日常のシーンにそぐわないので、DAIWAのロゴの扱いとはまったく異なっています。
――D-VECの各製品について、高い機能性とアパレル製品としての完成度が両立していると感じます。D-VECブランドではどのような理念で製品展開をされていますか?
すべての製品の大本には、DAIWAが快適なフィッシングのために作り出してきた防水・耐久テクノロジーがあります。一方、日常生活でも意外に通勤・通学でも雨風に悩まされることはあり、そうしたテクノロジーは活用できます。
ですが、D-VECで展開するのは「釣り用の服」ではないので、デザインは完全に日常のモノに思い切り振ってしまったほうが良いと思いました。なので、ほかのアウトドアブランドのファッション性の高いアイテムよりも、結構振り幅が大きいラインナップだと思います。
――ブランドの立ち上げの際から、アイテムの「振り幅の大きさ」を意識していたんですね。
はい。釣りブランドの服で、ちょっとだけファッション性がある…みたいなものを展開しても、あまり大きく広がらないと考えました。今あるものをまったく違うところまで振ったほうが、結果的にブランドで出来る部分が大きくなるのではないか、という意図があります。
――現在、D-VECブランドのキーになっているプロダクトは?
キーとなる特定の製品がどれかというより、やはり機能が重要と考えています。単に華やかなデザインを追いかけている、ということはないです。
レインブーツなどのフットウェアでは「ハイパーDソール」という、ロゴを模した靴底を採用しているんですが、本当に滑らないんですよ。釣り糸を極細にして繊維にした軽量布「モノフィラメント」で作ったウェアも今後展開していきます。どの製品でも、釣りの技術からはじまっていることは伝わるように作っています。
リブランディングと「大事なこと」探し
――リブランディングをする際、大きくわけて一新するポイントと保守するポイントがあると思われますが、「変える」のは難しい行為と考えます。「変える」ポイントはどのように見出していますか?
どのブランドでもそうなのですが、ものすごくわかりやすく言えば、「一番いいところは何だろう」ということを最初につかみます。
そして、すごく簡単な話なのですが、よいところは伸ばして、そうでないところはどうすれば改善できるか考える(笑) 言うと当たり前のことなんですけれど、意外にその整理が難しいというか。歴史があればあるほど、あれもこれも大事となってしまうので。
でも、本当に大事なことは、そんなにたくさんはないですよ。それがひとつでもあったら、素晴らしい企業です。企業が存続しているということは、それが必ずあるわけですから。
――「大事なこと」探しはどのように行いますか?
ヒアリングがメインです。経営層から新入社員、ユーザーの方々にも。ケースバイケースですが、ヒアリングですね。基本は。立場の違ういろんな人から聞いても、共通点があるとそれが本質です。必ず、何か出てきます。
DAIWAの場合、やはりものすごい「技術」を持っています。携わった当初びっくりしたのが鮎竿ですね。8~9mくらいの長い物なのに重さは約200gしかない、超ハイエンドな竿を30~40万円で販売している。その商品展開にまず驚きました。こういう製品を作れるのはすごいですよ。なので、「技術」がやはりこの会社の大事なところだとまずは確認しました。
逆に、もったいないところというか、やっていなかったところがあると僕はとらえました。まず、デザイン面が弱かった。もう少し大きく言えば、釣り具開発のためのテクノロジーの発展、いわば「縦」の進化はものすごいのですが、「横」の展開はあまりやっていないなと感じました。
――とことん釣り具のクオリティにこだわっていて、他の領域には手を出していなかった、ということですね。
そういうことです。テクノロジーは本当にすごいのに、釣りをやっていない人たちにそれを提供するような意識がなかった。DAIWAをはじめて知った人がいきなり鮎竿を買うことはないので、技術力を知る機会がなかったんです。「横」の展開にはアパレルが一番入りやすいものだと考えて、現在のブランド展開になっています。
先ほど「やっていなかった」と言いましたが、より正確には「視点が違った」のだと思います。以前のDAIWAブランドでは、アパレル関係のアイテムも竿や網、長靴といった製品の延長上で作っていました。
撥水・防水など衣類としての機能性はとても高かったのですが、たとえば女性が身につけたいと思うようなものは、ひとつもなかったように感じます。色展開もほぼ黒かグレーのみで…。そこで防水技術は残して、釣りをディープに楽しむ人でなくても、かっこいい・かわいいという視点から欲しくなるようなモノを作れば、お客様が広がっていく。なので、そこは変えましょう、と。
――ブランディングというのは製品開発の源流とも言える機軸を作る大きな事業です。D-VECの設立にあたって、佐藤さんが感じた「壁」は何かありましたか? また、どうやってそれを乗り越えましたか?
まだ立ち上がって日が浅いブランドなので、具体的な製品に結びついた話だと難しいですね。何かを改善して売り上げが伸びた、というものはまだ出てきていないので。ですが、日々アップデートですよね。D-VECだけではなくて、DAIWAのほうのアパレルもずっと見ているので、そういう意味で言うと日々変化しています。
現場からうかがった話で言えば、撥水性のある傘の布地で、海の柄のはいった真っ青なコートのエピソードが「壁」というか、そういう局面に近いかも知れません。すごく舞台映えするのでタレントの方たちが大勢着用してくださったんですが、実売には結びつかなかったといいます。
なぜかと言えば、タレントの衣装に適していた一方で、一般の方の普段着にはインパクトが強すぎた面があると思います。そのあたりは難しい面があります。広告的な商品と実売は必ずしも一致しませんから。
――自動車で言えば、派手なカラーを広告に使う一方で、白、黒なども展開しているようなものでしょうか。
それと一緒ですね。広告的製品と実売に結びつく製品は両方必要で、数量のコントロールで調整していきます。先ほどの海柄のコートも、それを見てD-VECを知っていただいて、ショップに来ていただけた例もあるかもしれません。そういった反響も分析しているところです。
――最後に、D-VECブランドの今後の展開についてお聞かせください。
今回青山で展示を行ったのも実験の一環であって、釣りから自転車、ゴルフ、テニスと、グローブライドのブランドを一堂に並べたのもほとんど初めてです。
これらのブランドを横並びで置ける店もないですし。いきなりこういうコンセプトの店を作っても、売り上げを立てるのはなかなか難しい。ここはスタジオ、アトリエのような実験的ショールームだから実現できました。

ここでの反応を見て、たとえば自転車と釣りの組み合わせを追求するなど、別の展示も行います。ほかのイベントでの提案についても、ifs未来研究所の川島蓉子所長に考えていただいています。
繰り返しになりますが、D-VECにしろDAIWAにしろ、方針をガッチリ固めるのではなくて、日々更新をかけていくようなイメージですね。デザイン性についても、単に既存のアパレルブランドを追随しようとしているのではなく、釣り具メーカーが提案する新規性を実現するために、チャレンジを進めています。
――ありがとうございました。
(杉浦志保)