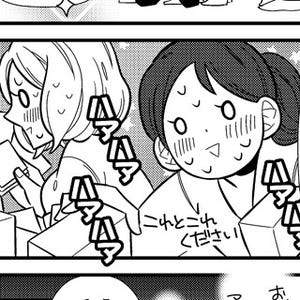実は複雑な構造
――素朴な疑問なんですが、開発の時はやはり何回も双眼鏡を見ているんですか?
家塚:何十回も何百回も見てます(笑)。
島田:開発者はもちろんですし、評価部門も厳しいので、そこをクリアするために、一緒に何十回何百回、それこそ数えきれないくらい見ています。
――じゃあ、バードウォッチングに出かけたりとか。
家塚:設計部門と評価部門の人たちと一緒に、開発している事業所の周りの公園に行って、双眼鏡を覗いていることもあります。あとは、社内で設計している人の頭を見たり(笑)。そうやって何百回も覗きながら、設計者や評価者が「こういうときはこのグリップの形だと疲れるから少し変えよう」とか、「ライブで下向きのときはどうか」と、使い方を想定して進めています。
島田:また、手ブレ補正の効き方も強ければいいわけではなく、心地良いところがあるんです。強くしすぎると、ちょっと動いただけでも視界がガクッと動いてしまって、ずっと見ていると気持ち悪くなってしまう。その辺の調整は、開発の努力のしどころだと思います。
――値段的にはかなりの嗜好品だという気もするのですが、値段が高いのはどんなところに理由があるんですか?
家塚: 新しい手ブレ補正技術の部分はもちろん、10数枚で構成されるレンズも高価なガラス材料を使っています。いちユーザーとして、気持ちはわかるので、できるだけコストは抑えて、と思うのですが、長く愛用していただく製品なので、多少不用意に何かにぶつかっても左右の視野の中心がずれないようにとか……外から見るとシンプルな形状なんですけど、中を開けると複雑なんですよね。
島田:双眼鏡って、価格帯のレンジが非常に広く、千円代のものから、数十万円のものまであるので、用途に合わせて選んでいただければと思います。
――値段の違いはなんだろうと思っていたのですが、ガラスなどの部分もポイントなんですね。
家塚:見えが良く高精度な双眼鏡を開発しようとすると、高価なガラス材料を使う必要があり、レンズ磨きの精度も高い技術が求められます。またそれらをしっかりと支える部品も必要になります。さらに左右のズレがないように作りこまなければいけません。
一番声が上がっているところ
――新しい「パワードIS」はどんなところで使うと良いのですか?
家塚:多分ライブだと、基本的にパワードISが良いと思います。馬のレースなどを見るときは、追いかけて見ているとパワードISが手ブレだと判断し、戻そうとしてしまうときがあるんです。ライブでもよっぽど前の席にいて、アーティストが走ったりする場合は、通常の手ブレ補正の方が見やすいと思います。
実はこの新製品も、企画を始めた頃はバードウォッチング向けと思って作っていました。開発が進んでいくにつれてどんどん防振双眼鏡がライブ需要で盛り上がっていったんです。
――では今後、ライブ鑑賞や観劇に特化した製品が出る可能性もあるのでしょうか。
島田:今、一番声が上がってきていますし、市場の声はとても大事にしたいと考えています。
家塚:流行りに合わせて変わっていく製品ではないので、基本性能の高さは譲らずに。でも、今まで使われてなかったお客様の使い方も把握しながら、考えていきたいと思います。