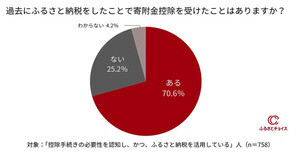アキュラホームが30周年記念一戸建応援プロジェクト「新すまい55」として販売した550万円住宅(建物本体価格)。昨年4月、期間限定で販売された同商品は大きな反響を呼び、販売から1カ月程度で1万件を超える問い合わせを受けるなど、好評を博した。その後も、延長販売など行い、2010年1月からは、2プランから10プランに拡充し、全国工務店ネットワークのジャーブネットから全国販売に踏み切った。
無駄を省き、合理的な家づくりの究極形とも言える「550万円住宅」を作ったアキュラホームとは、どのような会社なのか。そして、その家づくりの真髄とはどのようなものなのか。宮沢俊哉社長に、お話を伺った。
三代続く大工の血筋
私の祖父は宮内庁御用達の大工の棟梁、父は山梨で工務店を営んでいました。大工の血が私にも引き継がれたのでしょう。父親の作業場を遊び場に、小中学校の頃から鉋などの大工道具に親しんだものです。余り材を使って、木工の腕を磨きました。父や祖父のような大工になりたいという想いは、こうした環境から自然と育まれていきました。
中学校卒業後は、叔父からの紹介で、埼玉県にて工務店を開いていた親方に弟子入りしました。いつか大工として一人前になりたいという夢を抱いた自分は、祖父や父の助言を受けて「大工になって棟梁になれるのは一握りだ、まずは他人の釜の飯を食ってこい」と、見習い修行に出たのです。
そこで修行に励みましたが、合理化されていないムダの多い現状に頭を悩ませました。たとえば、押入れの天井。昔はベニヤ板がなかったので、天井板には杉板が使われていました。ところが、杉板でベニヤ板のような薄い板を作るとなると、幅30cmぐらいの板しかとれない。これを何枚か重ねて押入れに張り、垂れないように「竿縁」という木を入れていました。これを「イナゴ天井」と言います。ですが、私が見習い修行をしていた頃には既にベニヤがあって、イナゴ天井を作る意味がないのではないかと思ったのです。
そこで親方に「ベニヤをベタっとはった方が早いんじゃないのでしょうか」と進言したら、「馬鹿野郎! そんなの本格的な天井じゃない」と一蹴されたものです。今は、ベニヤの一枚張りで押入れを作るのは主流ですが、当時では考えられないことだったんですね。私はその当時から、創意工夫による家づくりの合理化に着目していました。
19歳で独立、苦悩の時代
修行は4年と半年に及びました。一人前として現場を任されるようになっていましたが突然、事件が起きました。親方が夜逃げをしてしまったんです。高度経済成長の時代、建て売りの下請けに手を出してしまい、親会社が倒産したあおりを食ってしまったんですね。非常によいご家族で、今でも当時のことを思い出すと寂しい気持ちになります。
その後やりかけの仕事を仕上げるということで、倒産した親会社とは別の親会社から依頼を受け、19歳で「都興建設」を立ち上げました。これがアキュラホームの原点になります。年齢も若く、独立したばかりで信用がない時期は、人が嫌がる後始末や営繕(リフォーム)の仕事が多かったですね。その時、思ったのは「ずいぶんいい加減な仕事をしているなぁ」ということ。さらに、建て売りの下請けをやるようになり、手抜きが横行していることに気づきました。
宮内庁御用達の大工の棟梁の祖父を持ち、いいもの作って喜ばれるのが大工の真髄だと疑わなかったので、この状況には非常に衝撃を受けました。そして「これなら自分の方がよい仕事ができる」と思い、新築にチャレンジしましたが、その当時、私は21歳。若造の言うことなんて、誰も相手にしてくれませんでした。下請けすら仕事が広がっていかない。苦悩の時代でした。