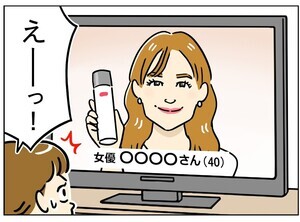スーパーマーケットでレジの順番待ちをしながら、やおら一枚の風呂敷を取り出し、端と端をささっと結んで買い物袋をこしらえる。そんな粋なふるまいが自然にできたら、素敵ではないだろうか? 風呂敷を、ものを包むだけの布と思ったらもったいない。
達人の技を学べば、やわらかくて丈夫な四角形の布を、色々なものに変身させることができる。この記事では、筆者がワークショップに参加して学んできた、風呂敷の達人・横山功氏の技と知恵の数々を紹介。どれも驚くほど手軽にでき、一度覚えてしまえばとても便利なばかりか、結んで開いてまた結んで……と繰り返すと、手になじむ布の感触が心地よく感じられてくる。達人曰く「風呂敷に不可能はない」とのこと。風呂敷をさりげなく普段使いして、エコバッグの先を行く"エコカッコいい"生活を送ろう。
横山功プロフィール

1979年浅草生まれ。武蔵野美術大学在学時、自分の部屋から出るたくさんのゴミに息が詰まりそうになり、エコロジーの一環として、風呂敷を使い始めたのがきっかけ。ゼミのテーマは「風呂敷の研究」。国内・海外旅行も風呂敷を結んだバッグ一つで出かけ、日常生活においても、より便利で新しい風呂敷の技を次々と編み出していく。数年後に風呂敷ブームが訪れるが、ただの流行で終わってしまわないよう、実践的な練習を主とした風呂敷ワークショップを各地で開催し、"便利と安心"を備えた和の心を伝え続けている。
風呂敷のサイズと素材の選び方
まず、用意する風呂敷について。素材は綿、大きさは1m角(以下、大)と50cm角(以下、小)の2種類があれば、大抵の荷物を運べるという。「ただし、風呂敷を手づくりする場合は、真四角でなく、縦横どちらかを1cmほど長めにして縫うといいですよ」と横山氏。そうすると、対角線方向に引っ張っても布が伸びすぎず、使い勝手がよいのだとか。
基本の「真結び」
今回紹介する風呂敷の技は、どれも布の角どうしを結んでいくことで完成するが、覚える結び方は「真結び(まむすび)」ひとつだ。

|
1.真結びの手順 |
かばんをつくる
真結びを覚えれば、あとはどの角どうしを結ぶかと、その順番の組み合わせとなる。まずは、レジ袋と同じように持ち手が2つある「買い物バッグ」と、浴衣を着る際に持ったり、ちょっとしたランチバッグとして使えそうな「きんちゃく」を紹介しよう。買い物バッグは大を1枚、きんちゃくは小1枚を使う。

|
2.買い物バッグときんちゃくのつくり方 |
買い物バッグは、中身の多さに応じて1回目に結んだ結び目の締め具合の調節が可能。そのおかげで、バッグの中身をある程度タイトに固定することができる。また、「中にかごを入れてかごバッグにしたり、バッグを別の1枚で覆うようにして結びつけることで、オリジナルのデザインにコーディネートするといった楽しみ方ができます(横山氏)。
きんちゃくは小さめの風呂敷を使うので、出勤時に熱い、または冷たくて結露する水筒を包むのに使った風呂敷で、ランチに出かける際にサイフや携帯電話を入れるきんちゃくをつくり、午後はほどいてハンカチとして使うといったアレンジが考えられる。また、かばんとしてではなく持ち手つきのポーチとして、化粧品などを入れても個性的だ。
ものを腰にぶら下げる
次はウェストポーチ。1980年代には日本人観光客の定番スタイルだった三角形のウェストポーチだが、近頃はすっかり見なくなった。とは言っても、サイフや携帯、カメラといった小物をコンパクトに持ち運び、なおかつ両手が自由になるというメリットは捨てがたい。このメリットを提供してくれる上に、必要なときだけあればいいというわがままにも答えてくれるのが、この「風呂敷ウェストポーチ」だ。
特定のものを運ぶ
ここからは、ある程度かさがあり、かつ通常のバッグでは収まりの悪い1種類のものを、包んで運ぶ風呂敷の使い方を紹介する。まずはびん。手土産のワインや日本酒を運ぶ際、発泡スチロールの網カバーで保護した上に、他の使い道が考えつかない極端に縦長の紙バッグを使うことがほとんどだ。そこで、風呂敷を使えば「保護しながら運ぶ」という機能を満たしてくれる。本に関しては、前述のバッグに入れば事足りるが、覚えておくと人に貸す際に包んで渡したり、読書のために本だけを持って外出するときに活用できそうだ。

|
4.びんと本の包み方 |
大きなものを運ぶ
最後に、中身が大きすぎて対角線にある角が届かない場合の、あっと驚く風呂敷術を伝授しよう。対角線ではなくまず隣り合う角を結び、できた輪に残りの2角のどちらかをくぐらせて、最後に残った角と結ぶと、不思議と収まってしまう。あきらめて他の布を探す必要がない上に、きっと、一緒にいる人を「え!なんで?」とびっくりさせることができるだろう。
知っておいて損はない、素朴で実用的な風呂敷の技たち。実際に手を動かして布に触っていると、1枚の布を"生かす"という日本人の知恵の奥底にある、ものを大切にする心がよみがえってくるようだ。