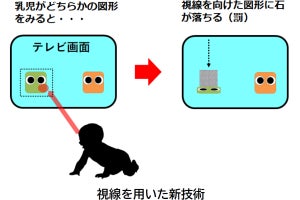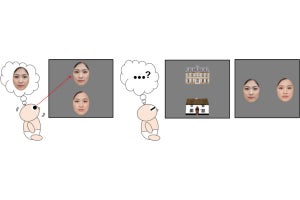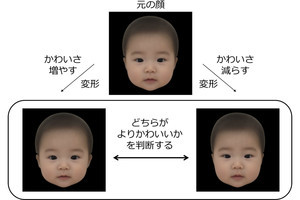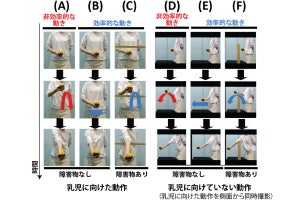京都大学(京大)は7月19日、幼児期の「満足遅延」(すぐに得られる小さな報酬を我慢し、将来得られる大きな報酬を優先すること)が文化に特有の「待つ」習慣により支えられることを明らかにしたと発表した。
同成果は、京大大学院 教育学研究科の齊藤智教授、東京大学大学院 教育学研究科の柳岡開地 日本学術振興会特別研究員PD(現・大阪教育大学 特任講師)、米・カリフォルニア大学デービス校のユウコ・ムナカタ教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、心理学協会(元・米心理学会)が刊行する心理学全般を扱う学術誌「Psychological Science」に掲載された。
子どもの満足遅延を検討する課題として多用されている「マシュマロテスト」。米国で開発されたもので、子どもにマシュマロなどのお菓子を1つ差し出し、「今すぐにこれを食べてもいいが、食べないで待っていたら、後でもう1つお菓子をあげよう」といって、標準的には15分待つことができるかどうかを試すといったものとして知られている。
以前の研究では、子どもの満足遅延は各自の認知能力が反映されると想定されていたが、2010年以降の研究では、他者との信頼関係など、社会環境からの影響に強く左右されると考えられるようになってきたという。
そこで研究チームは今回、そうした最近の流れを発展させ、子どもたちが日常生活の中で積み上げている待つ習慣が、彼らの満足遅延を大きく左右するという可能性を検証することにしたという。
具体的に日本の子どもの「待つ」習慣として着目されたのが食卓習慣だという。日本では、家族やクラスメートなど、ほかの人の準備ができるまで待って、全員で「いただきます」を唱えてから、はじめて食事を始める食卓習慣がある。そのため、日本の子どもは食べ物を前にして「待つ」経験が多く、テストで待ち時間が長くなると予想された。