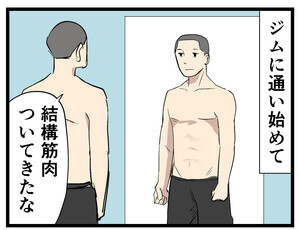第140回芥川賞・直木賞の選考委員会が15日、東京・築地の新喜楽で開かれた。芥川賞には津村記久子さんの『ポトスライムの舟』(群像11月号)、直木賞には天童荒太さんの『悼む人』(文藝春秋)と山本兼一さんの『利休にたずねよ』(PHP研究所)が選ばれた。贈呈式は2月20日(金)、東京會舘にて行われる。正賞は時計、副賞は100万円。
三度目の正直!? 芥川賞受賞の津村さん、喜びの受賞会見
津村さんは1978年大阪市生まれ。大谷大学文学部国際文化学科卒業。2000年より会社勤務。「カソウスキの行方」(2007年9月群像)で第138回芥川賞候補。「婚礼、葬礼、その他」(2008年3月文学界)で第139回芥川賞候補。『ポトスライムの舟』では、新卒で入った会社を上司のモラルハラスメントで辞め、契約社員をしながらカフェの手伝いなどをする29歳の主人公、ナガセの1年間を描いている。
選考委員の宮本輝氏は「底辺層に近い慎ましやかな生活を送る女性の日常が、衒(てら)いのない文章でよく書かれている。時代が変わっても、こういう女性達の生活は、文学的に普遍的なものがある。また、著者としてや、文章、小説の組み立てもはっきりと成長している。文句なしの受賞。」と褒め称えた。また、「最近では"そこそこの大学"を出て"そこそこ"の会社に入り"そこそこ"の収入を得ている層の"そこそこ小説"が定番化している。この受賞作のように、もっと底辺の、ギリギリの生活を送る人たちを使って、何らかの新しいものを世の中に提言していく文学を作っていくべき」という意見もあった。
東京會舘で行われた記者会見で、津村さんは開口一番、「物事を良いように考えない性質で、賞をいただけるとは考えておりませんでした。大変驚いています。お世話になっている編集者さんたち、家族、友達、会社の方々全員にいただいた賞だと感じております」と声を震わせた。3回連続で候補作に選ばれていたため、記者からは「三度目の正直で、何か予感するものがあったのでは?」との質問も出たが「あくまで諺ですし、そんなにうまくいくものでもないので、候補にしていただくだけで十分だといつも感じていました。(受賞するなんて)すごいことだと思います。」と率直に述べた。
同作が時勢をとらえているとの記者の指摘には「この本を書いた時期は、7月中旬から9月上旬で、こんな不況になるとは思わなかった。不況だから書いた小説ではない」ときっぱり。厳しい労働条件の中で働かれている方へのエールを、と言われると「私の小説なんて全然生ぬるいと思いますし、今回受賞させていただいた小説が、そういう方々を代弁しているとは思っていません。ただ、働くことを奪われる怖さは、想像しただけで寒気がすること。ほんの少しだけでもましになることもあるかもしれませんので、自暴自棄にはならず、しのいでいただきたいと感じております」と語った。
今後の抱負については、「いろんなこと書く予定はいろいろありますが、一貫して面白い小説、もっともらしいことではなく実感できるのかということを突き詰めつつ、面白いと言っていただける、感じてもらえる小説を書きたい」と力を込めた。自身の今後については「できるかぎり(現在働いている職場で)正社員として働きたい。働いているからこそ書けた小説なので」と笑顔を見せた。
直木賞受賞の天童さん「選ばれたことでご恩に少しでも報えたのではないか」
直木賞は、天童荒太さんの『悼む人』と山本兼一さんの『利休にたずねよ』。行われた投票回数は計3回で、第1回目投票では山本さんの作品の得票数が多く、第2回目投票では天童氏が山本さんの票数を上回った。しかし、最初の投票結果から「山本氏をどうするか」との意見が上がり、第3回目投票において、天童氏・山本氏のダブル受賞が今回の直木賞として最もふさわしいという結論に達した。両作品の共通点について、井上ひさし氏は「日本語で書かれていることくらい」と言って笑いを取った後で、「両作とも"個"がしっかりと書かれている」と評した。
天童さんは1960年愛媛県生まれ。1983年明治大学文学部演劇学科卒業。1986年以降、映画の原作、脚本などを手がけた後に作家となる。『永遠の仔』(1999年幻冬舎刊)で第53回日本推理作家協会賞受賞、第121回直木賞候補。『あふれた愛』(2000年集英社刊)で第124回直木賞候補。今回受賞した『悼む人』は、全国を放浪し、死者を悼む旅を続ける坂築静人(さかつき・しずと)を巡るドラマが繰り広げられている。
井上氏は『悼む人』について「この作品ほど書いている人の姿勢がはっきりわかる作品はない。修行僧のような作家の姿が、作品を読むにつれて、いつも並行して浮かんでくる、珍しい作品である。また、この作品では古今東西の芸術家が挑戦してきた『生』『死』『愛』の3つのテーマを1度に相手にしており、作家が悪戦苦闘している姿が作品と重なる。試行錯誤の中で失敗している部分もあるが、『文学は世界に向かって何ができるか?』という作家にとって最高のテーマに向かってぶつかって、成果を得ており、失敗を補って余りあるものとなっている。破綻している部分にも力がある」と語った。
山本さんは1956年京都市生まれ。1980年同志社大学文学部美学及び芸術学専攻卒業。出版社、編集プロダクションに勤務し、86年よりフリーランス。『火天の城』(2004年文藝春秋刊)で第11回松本清張賞受賞、第132回直木賞候補。『千両花嫁 とびきり屋見立て帖』(2008年文藝春秋刊)で第139回直木賞候補。『利休にたずねよ』では、茶聖ではなく人間利休に心魅かれる著者が、その謎に包まれた千利休の生涯を解き明かすというものだ。
井上氏は同作について「時間をさかのぼっていく小説の構造自体が、読者をある一点へ引っ張っていく。構成の仕方が非常に巧み。筋立て、構想、読者をある一点に導いていく筆の力など、厚い本だが、そこまで持って行く力は健勝すべき。」と評価した。また、井上氏は「日本の文化を根底からデザインした利休の姿に、様々な方向から照明をあてて、"利休らしさ"をえぐり出している」と語った。
直木賞を受賞した天童荒太さんは、受賞の感想をこう述べた。「この『悼む人』を大事な時間を割いて読んでもらったこと、長い選考の末に選んでいただいたことに感謝しております。自分ひとりで書いた小説ではなく、7年を費やして多くの人に支えられて書いた小説です。今回よい報告をすることができて、ご恩にわずかながらでも報いることができたのではないかと思っております」。
小説については、読者との対話の中で生まれた作品であることを強調した上で「日本において身近の人を亡くしていない人はいないでしょう。こうした方に、正面からこの本を書いたものですと向き合えるのかというのが、課題だった。自分程度の才能でこのような作品を書けるとは思わなかった。これまでで一番の到達点。こういう作品を書けて自分自身が幸せ」と笑顔を見せた。
今後の抱負について、天堂さんは「今後1カ月は不得手なエッセーを頼まれるので大変かな。ただ、自分の表現方法は決まっています。基本的にはつらい立場、痛みを感じている側の人が懸命に生きている人と歩いていくような小説を書きたい」と熱を込めた。
直木賞受賞の山本さん「期待しないようにとは思っていたが、選ばれてよかった」
山本兼一さんは受賞について「選考委員の先生に選んでいただき喜んでいます。候補に選ばれたのは3回目なのですが、よくぞこの作品で受賞できたなというのが率直な思い。1回目はどきどきしていただけ、2回目はこれはとれるんじゃないかと思っていたが外れてがっかり。3回目は、期待しないようにと思っていたが(選ばれて)よかった。」とほっとした表情を見せた。
利休の描き方については「利休は枯れた世界を望んでいたとは思っていなく、根底に艶っぽさがあると感じた。利休はどんな人なのか、恋する力が強い人なのではないかと思ったのが小説の原点であり、ここから広がりました。利休には、こんなあなたを書いてしまって申し訳ないと言いたい」と述べた。また同作は、時系列をさかのぼる構成をとっており「一度設定を書いてしまうとそれを変えることができず、自分に呪縛をかけることになると、書き始めて思いました。書き手に緊張感を強いる構成方法でしたが、自分の中でよい緊張感になりました」と話した。
今後の抱負については「モチーフは日本への旅。職人や大工、刀鍛治など取材に行くと、こんなに繊細な技術がここにあったのか、という驚きをいつも感じていて、それを小説に書いています。こうした日本の文化を探っていけば、もっと面白いことがあるのではないかと思っています」と語った。