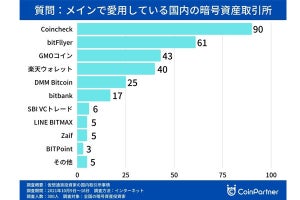「人生100年時代」と言われる現代。20代でも早いうちから資産形成を進めることが求められています。一方で、どのように投資・資産運用の目利き力を磨いていけばいいのか、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
この連載では、20代の頃から仮想通貨や海外不動産などに投資をし、現在はインドネシアのバリ島でデベロッパー事業を、日本では経営戦略・戦術に関するアドバイザーも行っている中島宏明氏が、投資・資産運用にまつわる知識や実体験、ノウハウ、業界で面白い取り組みをしている人をご紹介します。
今回は前編に続き「マインドとアウトプットのリスキリング」をテーマに、住友生命保険相互会社 情報システム部 デジタル&データ本部事務局 部長代理の猪山敦嘉氏にインタビューを行いました。
「意識改革」というマインドのリスキリング
――前編では「アウトプットのリスキング」についてお聞きしたので、後編ではマインド面についてもお聞きできればと思います。システム開発から秘書へというのは、すごい転換ですね。なにか苦労はありましたか?
猪山敦嘉氏(以下、猪山氏):着任してすぐにシステム開発状況の進捗会議をしていたのですが、これまで慣れ親しんだシステム開発者視点で報告をした際に、新しい職場の視点が不足していると管理職に指導を受けたことがきっかけで自分の業務領域が広がっており、視野を広げたり視座を高める必要があると感じました。苦労というよりも、自分の中で大きな意識変革がありましたね。
例えば、「なぜこのシステムを導入しているのか」「競合他社の状況はどうなのか」「どういったマーケティングをしていこうとしているのか」「仕様変更の背景の追求は妥当なのか」と管理者から言われ、自分の中での物事を掘り下げが甘いと感じることがありました。これを反省し、管理者はどういう視点で質問をしているのか、そういう背景を想像しながら仕事をするようになりました。ある事象に関する事実や人の見方など、今の状況になった背景を関係者に幅広くヒアリングしたり、関連資料を読みこんだりして、誰よりも情報を持ち解析をした上で自分の考えを明確にすることで初めて、自分の意見が力を持つため、このようなことを意識して仕事を行っています。
コロナ禍になり、「非対面だけでも仕事はできる」と思っていたのですが、今は出社を増やしています。仕事に関するやりとりの内容や背景、仕事を進めていく当事者である管理者や関係者の考えを理解しないといけないので、リアルで顔を突き合わせて言葉のニュアンスや表情をインプットすることもとても大切なことだと思います。オンライン会議やチャットだけでは伝わらないことがたくさんありますね。弊社は在宅ワークも必要に応じて選択できます。「在宅ワークしても良い」という状態が安心感につながり、仕事上やりやすさを高める部分も大きいので、例えば家族の誰かの体調が悪いときはオンラインに切り替えて仕事をしています。リアルとオンラインをうまく使い分けながら、生産性をあげて業務に取り組むことが大事です。
生成AIを知らずして社会で活躍できない
――猪山さんが考えるリスキリングやDX人材についても教えてください。
猪山氏:2022年11月にChatGPTの登場で、「世界が変わる」と強く感じました。この流れに乗らないと、後から巻き返すのが、大変だと思い、自分でもお金を出して研修を受けたり有償で売っているプロンプト事例の購入をしました。生成AIを使いこなせずにこれからの社会で活躍はできないと思います。
この2年ほどだけでも、ChatGPTは進化していますし、いろいろなツールも出てきています。日々いろいろな情報も入ってきますので、自分なりに精査しながら試しています。本社・グループ会社の職員約1万人を対象にした生成系AIチャットシステム(Sumisei AI Chat Assistant)では開発のほとんどに携わり、2ヶ月でローンチすることができ、自分の学びにより会社に貢献できたということは望外の喜びです。 今でもプライベートで、生成AIの高度な使い方を試したり、子供にも将来のために使わせたりしています。
「DX」という言葉は、いろいろなところで使われています。紙をなくすだけでもDX、今の業務をIT化するだけでもDX……と、定義がさまざまです。既存業務のIT化は課題が多く明らかになっていると思うのですが、DXのX部分(トランスフォーメーション)は課題がまだ見えていない部分も多いと思います。生成AIのような新しい技術を使って、なにができるのか?を知った上で業務を変革する。普段から、先端技術のことも業務のこともビジネスのことも考えて訓練しないと、本当の意味でのリスキリングはできないのではないでしょうか。
常日頃から物事について深く考え、小さな一歩でもいいのでよく考えその具体化や解決について明確化していくことが大切だと思います。実際にやってみないとわからない課題はたくさんありますし、やってみるとまた新たな課題も見えてくると思います。
よりパーソナライズされた保険と保険AIエージェント
――生成AIの活用は、企業も個人も避けては通れませんね。では最後に、猪山さんが考える保険の未来についてもぜひ聞かせてください。
猪山氏:人口減で保険のニーズも下がるのではないかという見解もあるのですが、リスクは減りませんし、新たなリスクも生まれてきますので、保険は必要で在り続けると私は考えています。今は保険というと金銭的な補償がメインですが、人の生活や価値観が多様化している分リスクも多様化しており、今後は補償も多様化するのではないかと思います。スマホ保険もその一例ですし、生保で言えば食生活による健康リスクや遺伝による健康リスクなど、個人ごとのリスクを細かく測り、それに合ったパーソナライズ保険のニーズが増えてくるのではないでしょうか。保険という「安心」の在り方がパーソナライズされ、保険商品もよりパーソナライズされていくだろうと個人的には考えています。
また、保険は加入手続きのステップも多く時間も掛かるので、顧客の満足度も低く、ユーザビリティ改良の余地があると感じています。契約やお支払い、病院の診断……といったプロセスをもっとシンプルにしていく必要があります。保険AIエージェントのようなサービスで、例えば夏に熱中症のリスクが高まると、その日の気温や健康状態、給水の状況などから保険AIエージェントが加入をおすすめし、了承を得ると手続きを自動化してくれるとか。もしものときは救急車を呼んでくれて、応急処置のアドバイスも保険AIエージェントがしてくれるとか。そのように生活に溶け込み、安心をご提供できる新しい保険の形を実現したいですね。画像認証・顔認証などの技術も向上し、AIが目や耳などの感覚器を持ち始めていますので、それも不可能ではないと思います。
保険AIエージェントが、ライフステージの変化に伴うリスク変動に合わせて、常に補償内容を最適化してくれるサービスも実現したいですね。安心して生活できるようになると、安心して人生を送れるようになると思います。そんな人が増えれば、少し大きな話になりますが少子化などの社会課題の解決にもつながっていくのではないでしょうか。「健康」「お金」「人間関係」という人生の3大課題の中で、保険は「健康」と「お金」に密接に関係するサービスです。それらの不安が軽減されると、社会はもっと良くなると思っています。弊社にはこれまでの顧客データが膨大にありますので、データを利活用することで社会課題の解決に貢献していきたいですね。