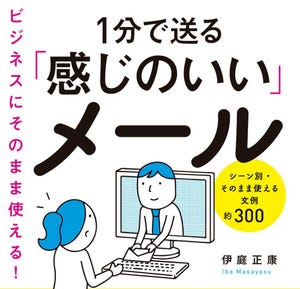ワニブックスは、このほど『めんどくさがりの自分を予定通りに動かす科学的方法』(1,650円/竹内康二著)を発売した。本書は、85年間の研究成果から導き出された「行動の技術」で、「後回し」「手に付かない」「気が乗らない」を解決する一冊。
著者は、明星大学心理学部心理学科・教授の竹内康二氏。学校や企業において、一般的な対応では改善が難しい行動上の問題に対して、応用行動分析学に基づいた方法で解決を試みている。
今回は同書の中から、行動とはなんなのかについてを抜粋。死人テストというびっくりするような名前のテストを用いて、「行動」というものを定義し、改善策を導き出す。ぜひ、そこのあなたもやってみてほしい。
■【重要】まずは、死人テストで「行動かどうか」を判断する
そもそも行動とはなんなのでしょうか。
行動の定義にはいくつかのレベルがあり、学問分野によっても解釈が異なります。たとえば、行動とは「筋や腺による活動のすべてである」と定義できます。しかし、こうした広い定義では、行動の具体的なイメージが持てません。
そのため、「行動か、行動ではないのか」を簡単に判断するために、「行動を死人にできること以外の行ない」と定義する「死人テスト」という判断基準があります。死人テストは、行動分析学の創始者スキナーの直弟子オージャン・リンズレーが提唱したとされています。
死人テストに従うと、死人にできないことが行動であり、死人でもできることは行動ではありません。たとえば、「車にひかれる」「笑わない」「名前を呼ばれる」「返事をしない」「静かにしている」「あいさつをしない」「上司に褒められる」という表現は、死人にもできることなので、行動ではありません。
「爪をかむ」「夢を見る」「ピカソの絵を思い浮かべる」「映画のラストシーンで胸がジーンとなる」「唾液が出る」「今夜の夕食のメニューを考える」というような表現は、死人にはできないことなので、行動です。
死人テストまで使って、「行動か、そうではないのか、を追求することにどんな意味があるのか」と思うかもしれませんが、とても重要なことです。
■たとえば、「あいさつをしない」も表現次第で改善策が変わる!?
たとえば、「あいさつをしない」という現象を具体的に表現すると、「歩いている途中で職場の人にあいさつをされても、あいさつを返さない」ということだったりします。
この場合、「あいさつされても、あいさつをしなかった」と言うより、「あいさつされても、そのまま歩き続けた」と言ったほうが明確に行動を表現したことになります。「なぜ、あいさつをしなかったのか」を分析する場合、この表現の違いはとても大きいのです。
「あいさつされても、あいさつをしなかった」という表現だと、その人が「なぜ、あいさつをしなかったのか」について分析する材料が乏しく、「この人は社会性のない人なのかも」と適当な推測をしてしまうことになりかねません。これでは、行動の改善は期待できません。
しかし、「あいさつされても、そのまま歩き続けた」という表現であれば、「もしかして、あいさつされたことに気がつかなかっただけではないのか」という可能性に気づくことができます。さらに、「あいさつされても、早足で歩き続けた」という表現なら、「急いでどこかに行こうとしていたのではないか」と想像することも可能です。
つまり、改善したい行動をどのように記述し、表現するかによって、原因の推測が変わることになります。当然、その後の改善策にも違いが生まれます。たとえば、上司Bさんから私が「最近、Aさんの様子がおかしいんです。仕事に集中してないんです。どうしたらいいですか?」と相談された場合、「Aさんは具体的にどういう行動をするんですか?」と聞く必要があります。
「集中しない」ことは死人でもできるため、行動とは言えません。死人にはできない行ない、つまり「具体的な行動がなんなのか」を知ることがとても重要です。
集中しないというのが、実は「寝ている」という行動なのであれば、コーヒーを出してあげたり、早寝するように助言したりすることができるでしょう。集中しないというのが、実は「同僚との私語が多過ぎる」という行動を意味しているのであれば、本人と同僚の両方に作業中のルールやマナーを明示すれば解決しそうです。
「〇〇しない」ことが問題だと思っている場合は、今一度、死人テストに従って「〇〇している」という行動の表現に言い換えてみましょう。そこから、解決の糸口がつかめるかもしれません。
また、行動には、爪をかむことのように目に見えるもの(顕現的行動)もあれば、メニューを考えるといった目に見えないもの(内潜的行動)もあります。思考や認知、検討や想像も行動です。そういった直接目に見えない行動は、他人からは観察が難しいですが、本人が自覚し、表現できるのであれば行動として扱うことができます。
大切なのは、その行動がなんらかの結果をもたらしているかどうかです。つまり、その行動が物理的環境や社会的環境になんらかの影響や効果を与えているのであれば、それは「行動」と言うことができます。
たとえば、「丁寧にメニューを考える」ことでおいしい料理が完成したのであれば、物理的環境に影響を与えているし、その料理を友人が喜んで食べてくれたのであれば社会的環境に影響を与えたことになります。
書籍『めんどくさがりの自分を予定通りに動かす科学的方法』(1,650円/ワニブックス刊)
同書では、本稿で紹介した以外にも「すぐやる人」「後回ししない人」に変われるヒントを行動分析学に基づいて解説。気になる方はチェックしてみてはいかがだろうか。