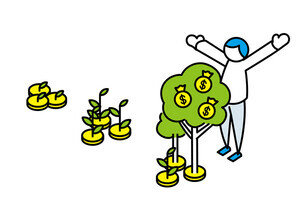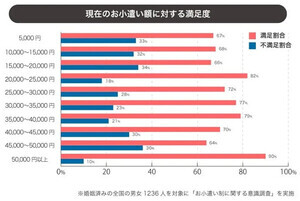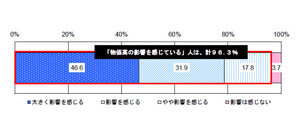とりあえずS&P500やオルカンといった、定番インデックスファンドに投資しているものの、意外と値動きがあって不安になっている、という方もおられるのではないでしょうか。それはそうです、大事な大事なお金を投資されているのですから。
不安、つまりリスクを少しでも減らし、コントロールしていくには、債券という選択肢があります。本稿では、意外を知られていない債券について、投資のプロ中のプロである、一般社団法人日本金融サービス仲介業協会 代表理事会長の中村 仁さんに教えていただきたいと思います。
* * *
皆さん、こんにちは。株式会社400Fの中村と申します。弊社は”オカネコ”というお金に悩んでいる方とお金の専門家をマッチングするプラットフォームを運営しており、その中で金融サービス仲介業を通して個人の皆様に資産形成に関するアドバイスを提供しています。
そんな中で今回は、金利環境の影響などによってここ最近非常に相談の多い債券投資について解説をしていきたいと思います。日本では新NISAが開始したことなどに伴い資産運用への関心が高まっており、書籍やYouTuberなどで様々な情報発信が行われています。
しかし、これらの中の多くはインデックスファンドへの積み立て投資を推奨するものであり、債券を活用したポートフォリオ(資産をどう分けて運用するかの組み合わせ)全体に関する内容は少ない印象です。インデックスファンドへの投資自体は非常に良いものでありますが、投資家としてリスクコントロールをするときに債券は無視してはいけない資産であると考えます。
そもそも債券って何?
債券とは、簡単に言うと「お金を貸して、そのお礼として利子をもらう仕組み」の投資です。国や企業にお金を貸す代わりに、一定期間ごとに利子を受け取り、満期になれば元本が返ってきます。
つまり債券は、基本的には借用証書の一種であり、政府や企業が資金を調達するために発行する証券です。そして債券には色々な種類があり、発行者の業態の違いで分類すると以下のようになります。
- 国債
国が発行する債券です。 - 地方債
都道府県、市町村などの地方公共団体が発行する債券です。 - 社債
民間企業が発行する債券です。
債券投資のメリットは?
では、実際に債券を資産運用に組み込むことのメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
リスク分散(資産配分)
債券は株式とは異なる値動きを示すことが多いため、ポートフォリオに債券を加えることでリスクを分散し、市場の変動に対する全体的な影響を減少させることができます。
安定した収入源
一般的な債券は定期的に利子(クーポン)が支払われるため、投資家は比較的予測可能で安定した収入を得ることができます。
安全性
債券は一般的にあらかじめ満期が決められていて、満期がくると元本が返済されることが発行体の信用力において約束されているため、信用力の高い発行体が発行する債券は、元本の安全性が高い傾向にあります。これはリスク許容度が低い投資家にとって魅力的です。
インフレ対策
一部の債券、例えばインフレ連動債(TIPSなど)は発行日を基準としたインフレ率の変動に応じて元本が調整されるため、インフレの影響を緩和することができます。
投資は将来の不確実性との戦いです。株式のみに依存するポートフォリオは、市場の波に大きく左右される可能性があります。しかし、債券を組み込むことでリスクを分散し、安定性を高めることができます。
ただし、債券投資にもリスクが伴います。金利が上昇すると債券の価格は下落しますが、特に長期債券は市場の金利変動に敏感です。また、発行体の信用リスクやデフォルト(債務不履行)のリスクも考慮する必要があります。そのため、投資家は自身のリスク許容度、投資目標、そして市場の状況を考慮して、適切な債券を選択することが重要です。債券の銘柄選びには様々な注意点等もあるため、こちらについて次ページにて説明いたします。
債券を組み込んだ代表的なポートフォリオ事例は?
では、債券を組み込んだポートフォリオ事例にはどのようなものがあるのでしょうか?今回は年金積立金管理運用独立行政法人(通称:GPIF)のポートフォリオを紹介いたします※1。
※1: 年金積立金管理運用独立行政法人のHPはこちら
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、私たちの年金を運用している公的機関です。実はこのGPIF、株式だけでなく、債券も約半分組み合わせて資産を運用しており、安定したリターンを出しています。
そして、GPIFはこれまで現役世代が納めた年金保険料のうち、年金の支払いなどに充てられなかったお金を年金積立金として預かり、将来世代のために運用しています。2023年9月末におけるGPIFの年金積立金は223.8兆円あります。そのうち国内株式と外国株式の資産額はそれぞれ54.9兆円、55.3兆円となっております。全体に対する比率としては24.52%、24.72%となっております。
残りの資産は国内債券と外国債券に投資されており、それぞれ59.4兆円、54.1兆円となっています。それぞれの比率は26.56%、24.19%となっており、大体株式と債券で半分ずつの資産割合となっております。
このようなポートフォリオにおいて市場運用開始以降(2001年度〜2023年度第2四半期)の収益率は+3.91%(年率)となっており、累積収益額は+126兆6,826億円となっています。
GPIFは私たち国民の年金を長期的に運用しています。長期的な運用においては、短期的な市場の動向によって資産構成割合を変更するよりも、基本となる資産構成割合を決めて長期間維持していくほうが、効率的で良い結果をもたらすことが知られています。皆さんは市場の短期的な値動きに一喜一憂して売買などはしていませんでしょうか?
このため、公的年金運用では、各資産の期待収益率やリスクなどを考慮したうえで、積立金の基本となる資産構成割合(基本ポートフォリオ)を定めています。この基本的なポートフォリオは国内債券・外国債券・国内株式・外国株式をそれぞれ25%ずつ保有して、乖離許容幅を設定しています。
乖離許容幅とは基本ポートフォリオをベースとしながらも、合理的に無理のない範囲で機動的な運用を可能とする仕組みが不可欠であり、GPIFでは基本ポートフォリオからの乖離を許容する範囲を定めているものです。
さて、この記事をお読みいただいている皆さんの基本ポートフォリオはどのようになっていますでしょうか? 株式だけで運用などを行っている方も多いのではないでしょうか?
ご自身のライフステージなども加味しながら、GPIFの運用を参考にご自身の基本ポートフォリオを構築してみることが今後長期的に運用する中においては重要であると考えます。
次のページでは、実際に債券を選んでいく際に注意すべきことなどについて解説をしていきます!