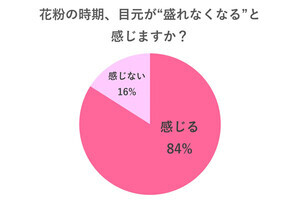森の環は、耳鼻咽喉科、アレルギー科、呼吸器内科、皮膚科、内科、眼科の医師1,009人を対象に、「医師の花粉症対策と栄養」に関する調査を実施した。調査期間は2025年2月28日~2025年3月3日で、調査方法はPRIZMAによるインターネット調査であった。
「花粉症の患者数は年々増加傾向にあると言われていますが、その主な原因は何だと考えていますか?(上位3つまで)」と質問したところ、「スギ・ヒノキなどの花粉の飛散量増加」(46.8%)と回答した人が最も多く、次いで「大気汚染の進行」(35.3%)、「都市部の環境変化」(33.9%)、「温暖化による花粉飛散時期の長期化」(32.6%)となった。
花粉飛散量の増加や大気汚染の進行、環境変化、温暖化による花粉飛散時期の長期化などが花粉症患者の増加に影響していると考える医師が多いことがうかがえる。
「あなたは花粉症ですか?」と質問したところ、約9割が「はい」(86.5%)と回答した。
また、「はい」と回答した人に、「花粉症対策として、薬(内服薬・点鼻薬・点眼薬など)を使用すること以外に工夫していることがあれば教えてください(複数回答可)」と質問したところ、「マスクの着用」(49.0%)と回答した人が最も多く、次いで「空気清浄機の使用」(46.3%)、「花粉対策用メガネの着用」(43.2%)となった。
花粉症対策として一般的な「マスクの着用」が最多となり、「空気清浄機の使用」や「花粉症対策用メガネの着用」なども多く、日常生活での工夫を積極的に行っていることがわかった。
「花粉症の症状緩和に、ビタミンDの摂取が役立つ可能性があることをご存じですか?」と質問したところ、約9割が「知っている」(93.6%)と回答した。大多数が、花粉症の症状緩和にビタミンDが役立つ可能性について認識していることがうかがえる。
また、「知っている」と回答した人に、「花粉症対策として、ビタミンDにはどのような可能性があると考えていますか?(複数回答可)」と質問したところ、「免疫バランスの調節」(51.0%)と回答した人が最も多く、次いで「抗酸化作用」(49.9%)、「腸内環境の改善」(48.7%)となった。
「免疫バランスの調整」や「抗酸化作用」、「腸内環境の改善」などが上位になり、幅広い可能性があると考えていることがうかがえる。
「あなたは日頃からビタミンDの摂取を意識し、十分に摂れていますか?(「意識しているか」と「実際に摂れているか」の両方を考慮してお答えください)」と質問したところ、「意識しており、十分に摂れている」(36.2%)と回答した人が最も多く、次いで「意識しているが、不足しているかもしれない」(51.7%)、「あまり意識しておらず、不足していると思う」(10.0%)となった。
ビタミンDを摂取している理由として、「花粉症緩和のため(30代/男性/東京都)」「疲労回復(40代/男性/岐阜県)」などのコメントが寄せられた。
疲労回復や免疫力の強化、花粉症の症状緩和などの理由で、多くの医師がビタミンDの摂取を意識しているものの、実際の摂取量不足を感じている方も多いことがわかった。
必要な栄養素を摂取する際、食事で摂りきれない場合はサプリメントを活用する人も多いが、「ビタミンD不足を補う場合、サプリメントで補うことは一般的な方法だと思いますか?」と質問したところ、約9割が「はい」(92.3%)と回答した。大多数の医師が、ビタミンD不足を補う手段として、サプリメントの活用は一般的な方法だと認識していることが明らかになった。
「ビタミンDを食事に取り入れる場合、どのような食材が摂取しやすいと思いますか?(複数回答可)」と質問したところ、「ビタミンD以外の栄養素も一緒に摂取できる」(44.4%)と回答した人が最も多く、次いで「手軽に食べられる」(43.8%)、「味にクセがなく、幅広い料理に使いやすい」(38.0%)となった。食事での摂取においては、他の栄養素も一緒に摂取できる食材や、手軽さや多機能性に優れた食材が摂取しやすいと考えられていることがうかがえる。
しかし、過去の調査では、必要なビタミンDを普段の食事で補うことは「難しい」と思っている医師が多いことが明らかになっているとのこと。そこで、「ビタミンDを簡単に摂取することができる食品があることを知っていますか?」と質問したところ、約9割が「知っている」(88.4%)と回答した。ビタミンDを簡単に摂取できる食品について知っている医師は多いことがわかった。