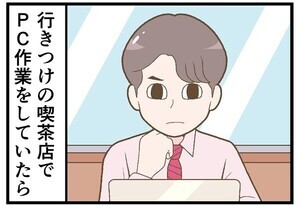サステナブルな未来について考えることを目的とし、親子で楽しみながら学べる体験型イベント「夏のわくわくキッズフェス2025in日本橋」が今年も開催されます。企業や団体、地域の商業店舗などがワークショップを出展し、子どもたちが楽しく学べる体験を提供するこのイベント。前回の来場者満足度は95%と高く、さらに100%を目指すために「次世代育成Session」をテーマに参加企業や団体が集まってのトークセッションが行われました。そこで話し合われたのは、次世代の子どもたち、さらには社会人を育成するために必要なヒント。AI時代の今、人の心に火をつける方法をお届けします。
AI時代の子どもたちの学びとは?
講師は、学生向けIT・プログラミング教育を提供している「ライフイズテック」取締役の讃井康智氏と、子どもの探究心を育むためのオリジナル授業を提供している「探求学舎」代表取締役の宝槻泰伸氏。10年来の親交があるという2人の楽しいかけ合いで、まず挙がったのは「企業が次世代教育に関わるべき理由」についてでした。
それはずばり「ITやAIが発達し、社会に出て求められることが多岐にわたっている現状、学校教育だけでは専門分野をカバーすることができないから」というもの。「例えばプログラミングや金融の専門知識を、子どもたちに対して体験を含めて教えられるのは、学校の先生よりも外部の専門家の方。次世代を担う人材育成をしていくにあたって、企業のみなさんが連携をしていかないと成り立たない。そうすることで企業も優秀な未来の人材を育てることができ、さらにはファンを増やせる」という話に、参加企業の方々の熱も入ります。
ドライビングクエスチョンでワクワクさせ、“興味開発”をしていく
次世代に活躍する子どもを育成するためには「好きなことや夢中になれることを持つこと」が大事だという話も。そのための育成方法として、企業は仕事に関する興味が湧くような“体験を届ける”ことが必要だと言います。それは、AIの時代になるからこそ。
「AIは黙っていても何もやってくれない。だから、AIをどのように使っていくかという情熱やビジョンを持たないといけないんです。しかもそれを言葉で上手く伝えられて初めてAIを使いこなすことができる。そう考えた時に、次世代を育てていくには興味や関心、情熱を育てること、つまり“興味開発”が大事になってきます」。
では、“興味開発”をしていくにはどうすればいいのでしょうか。
「心に火をつける。人々がワクワクする体験には、必ず考えたくなる“問い”がある。これを僕たちは“ドライビングクエスチョン”と呼んでいます。まず、情報と体験を並べてみる。その並べ方を工夫することで、人は時間軸の中で情報や体験に対して感情を抱きます。その感情がどういう波グラフになっていくのを見立ててみると、自ずと、どこで、どんな言葉でドライビングクエスチョンを発動すればいいのかが見えてきます」と宝槻氏。
そこで大切なのは、ワクワクとドキドキを提供しながら、インテリジェンスを伝えることだといいます。企業としてのインフォメーションをインテリジェンスに変える。もちろんそこには経験値が必要ですが、そここそがAIには負けない部分。むしろ、人間が研ぎ澄ませていくべきクリエイティビティのポイントになっていくのだとか。
「お盆の上に風船を置いて落としたらどうなる?」ワクワクする質問には大人も夢中になる
ここからは、実際にワークショップの企画を考えることで、ドライビングクエスチョンの実践に入ります。「参加する子どもたちや保護者たちの感情を見立ててください。どんな情報を与え、それに対して相手は何を思うのか。その見立ての先の子どもたちのリアクションに、何を返すのか。その連続技です」と紹介されたのは、ワークショップの基本となる「ハンバーガーモデル」という手法。
ハンバーガーの上のパンはイントロパート、下のパンはエンディング、真ん中がメインパートで、ここの肝がドライビングクエスチョンとなります。
その見本として、風船を使った科学実験の映像が紹介されました。そこで問いかけられたのは「お盆と風船があります。これを同時に落としたらどうなるでしょう?」というもの。実験結果は、重さのあるお盆が先に落ちます。この結果には違和感がありません。しかしその次。
「お盆の上に風船を置いて落としたらどうなるでしょうか。1番:お盆が先に落ちる。2番:お盆と風船が同時に落ちる。3番:風船は上に当たる」
参加者たちはクイズの答えについてそれぞれ班で話し合い、摩擦や空気抵抗などを考慮しながら答えを予測し、発表します。その姿は子どもさながらの白熱ぶりで、正解の「お盆と風船が同時に落ちる」という結果映像を見ると「ええ〜!」と声をあげて盛り上がりました。
子どもの心に火をつけることと、顧客や投資家の心に火をつけること
子どもたちの心に火を付けるドライビングクエスチョンを実際に体験したあとは、企業ごとにワークショップの企画を考え、発表することに。そのときのセッションの一例をそのままお届けします。
企業A「伝えたいメッセージは“ITにも人のぬくもりが必要”ということで、ワークショップでは、子どもたちにAIで絵本を作ってもらいます。イントロは、『AIって完璧だと思わない?』で、実際に指示通りに絵本が作れるのか、と投げかけます」
宝槻「失敗体験をさせたい? 成功体験をさせたい?」
企業A「成功体験をさせたいです」
宝槻「成功させる自信はありますか?」
企業A「自信は……ないです。実際に私の子どもにやらせた時に思ったようなものは作れなかったので」
宝槻「では、子どもからすると、上手くできなかった体験ですね」
企業A「そうですね。それがいいなと自分はやってみて思いました」
宝槻「子どもがそこで得られるものは? 逆に興味を失いそうですが」
企業A「それは……AIに全部奪われると、自分の自信が失われていくじゃないですか。そうじゃないんだよという自信をつけたい」
宝槻「では、この場合のドライビングクエスチョンは何でしょう?」
企業A「“思い通りの結果が得られるか?”」
宝槻「それだと『いいえ』と言うだけ。その時、子どもが感じるのかを考えると、たぶん『悔しい』だと思います。うまくいってないから。『悔しい』感情に何を問いかけるのか。『じゃあ、どうすればうまくいくんだろうね』と問いかけて、AIを上手に使った人の絵本を見せたらいい。そうすると『すごい、面白い! じゃあこれを作った人と僕たちの違いってなんだろう?』ってなりませんか?」
企業A「たしかに!」
セッションしながらアイデアが磨かれていくのを目の当たりにした参加者からは、感嘆の声が上がっていました。
「ドライビングクエスチョンができると、皆さんのセールストークや、プレゼンテーション、マーケティングも大きく変わります。皆さん、顧客に問いかけていましたか? 伝えてばかりではなかったですか? 相手がどんなことを考えているのか、感じているのかを見立てながら営業したり、マーケティングのプレゼンを作っていくと、上手くいきます。顧客の心に火を付けること。買いたい、応援したい、就職したい、投資したいというモチベーションをつけるのも大事な本業。子どもの心に火をつけることと、顧客や投資家の心に火をつけることは実は変わらないんです」。
この日、実際にドライビングクエスチョンの効果を体験した参加者に、この言葉が深く刺さっていたようです。