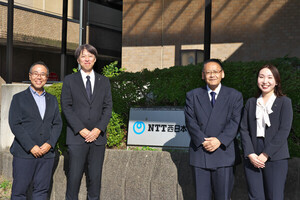NTT東日本を代表機関とするコンソーシアムは、2024年4月からローカル5Gなどを活用した遠隔型自動運転の実証を東京都狛江市で進めている。
その実証実験の進捗を体感してもらう場として、住民向けに遠隔型自動運転バスの試乗会が、12月20日・21日に小田急線 和泉多摩川駅前で開催された。
■自動運転サービスで狛江市の地域課題を解決
2023年12月、地域限定型の無人自動運転移動サービスの実現を目指す「デジタル田園都市国家構想総合戦略(2023 改訂版)」が閣議決定。総務省令和5年度補正予算「地域デジタル基盤活用推進事業(自動運転レベル4 検証タイプ)」が現在、地方公共団体と企業・団体からなるコンソーシアムが実施主体となって各地で実施されている。
地域限定型の無人自動運転移動サービス(限定地域レベル4)の実装・横展開に当たって課題となる遠隔監視システムなどに関する検証を行う本事業。
NTT東日本や狛江市などで構成されるコンソーシアムは2024年4月に実証団体として選定され、自動運転サービス実装の課題となる通信システムの検証が狛江市で行われている。
狛江市では多摩川住宅地区での再開発計画により2025年度以降の人口増加が見込まれる一方、公共交通機関の乗務員不足が深刻化。今後、バス路線の見直しや更なる減便が想定され、住民生活に必要な移動手段の増強・確保が喫緊の課題となっている。
その解決策のひとつとして、本実証では遠隔型自動運転バスの導入を検討。安心安全な地域公共交通の実現に向けた実証を行なっている。
12月20日・21日に行われた公道での遠隔型自動運転走行(自動運転レベル2)による試乗会には、事前に申し込んだ住民が自動運転バスに乗車。和泉多摩川駅~多摩川住宅間を結ぶ約5㎞を走行した。
市民の関心も高かったようで狛江市が試乗会参加者を募ったところ、すぐに計96名(2日間開催の延数、1便あたりの定員は12名)の定員に達したという。
■ローカル5G×自動運転、自治体の公道での実施は初
本コンソーシアムにはNTT東日本と狛江市のほか、ティアフォー、マップフォー、一般財団法人計量計画研究所、unerryが参画し、実証システムを構築した。
ティアフォー社の自動運転実証車両 Minibusは、さまざまなカメラやセンサー、マップフォー社の3D地図データ(自己位置・走行ルール用)を搭載。交通ルールを守りながら最大時速35キロで、コンソーシアムが策定したルートを往復30分程度かけて自動走行する。
本実証の自動運転レベルは、車両に人間の運転手が乗車するレベル2(ハンズフリー)となっており、運転手による手動走行の切り替えは1周につき平均4.3回程度。車両自体はドライバーフリー(遠隔監視が必要)となる自動運転レベル4を見据えた機能を備え、ルートの大部分を自動走行で周回することに成功しているという。
一方、現状では歩車分離がされていない道路や車線がない道路、緊急車両や道路工事といったイレギュラーケースでは対応が困難な場合が多いようだ。
また、レベル4自動運転を社会実装する上での技術的課題としては、都市部などでの混雑環境も挙げられる。通勤時間帯を中心とする駅前ロータリーや交流量の多い交差点の混雑、住宅地域の生活道路と接道する信号無し交差点など、複雑な予測・判断や運転操作が必要な交通環境が都市部では発生しやすい。
そのため、こうした場面での滑らかな自動走行には、インフラ側で取得したデータによる先読み機能や遠隔監視室での支援が重要と考えられている。
本実証では自動運転用のローカル5G(NTT東日本 ギガらく5G)を開通。多くの人が通信を利用することが想定される駅などに基地局を設置し、自動運転レベル4に必要な遠隔監視映像などのデータを高速・安定の無線通信で自動運転車両や遠隔監視拠点へ伝送している。
NTT東日本のローカル5Gを活用した自動運転の実証は、過去に成田国際空港での複数台遠隔型自動運転バスの実証などがあるが、自治体の公道での実施は本事業が初めて。現在は映像データなどを伝送する通信速度や画質なども含めて、データの蓄積と検証を行なっている段階だという。
■車両側とインフラ側の機器で取得したデータを活用
今回の実証事業にあたり、NTT東日本は団地内の見通しの悪い交差点と駅前ロータリーの2カ所に「スマートポール」を設置した。
「スマートポール」は、自動運転レベル4の円滑な走行を補助するための路上インフラ。4台の広角の高精細カメラや「LiDAR」(周囲に赤外線を照射してその反射で状況を把握するセンサー)、ローカル5Gアンテナなどが取り付けられている。
和泉多摩川駅の駅前ロータリーは時間帯によっては送迎のための車が多く滞留し、進入する際、車道を走行している自動運転車両で取得する情報のみではロータリー内の状況把握が遅れてしまう。
その結果、交差点や横断歩道の真上で急ブレーキ・急停車して歩行者などの通行の妨げてしまう可能性もある。そこで「スマートポール」に取り付けた機器でロータリー内の状況を検知。そのデータを遠隔監視室や車両に伝送して連携させることで、より安全でスムーズな自動運転の実現をめざしているそうだ。
同様に団地内の信号無し交差点も今回の実証のポイントのひとつとなっており、一般的なカーブミラーの代わりに自動運転では「スマートポール」を活用して、急ブレーキなどの低減をめざしているという。
実際に試乗させてもらうと、車通りの多い信号付き交差点なども歩行者や自転車、信号の状況を認識して、危なげなく走行していると感じた。道なりに走行する際は運転手の走行と大きく変わらない印象だ。
まだまだ開発途上の技術のため、ブレーキが強く掛かるようなシーンも多かったが、ブレーキ操作に関しては来年度以降にチューニングを施し、より快適な乗り心地を実現していける見通しだという。
自動運転の走行は路上駐車など外的要素に左右される部分も大きく、地域住民や地域の交通事業者などの理解促進や社会受容性の向上を図る住民試乗会などの取り組みも不可欠。 NTT東日本ではそうした機運醸成も進めながら、さらなる課題の抽出・解決のための実証実験を重ね、2027年度までに限定地域での自動運転レベル4の社会実装を目指すとしている。