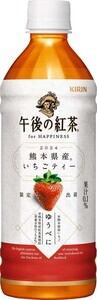キリンビバレッジは、紅茶飲料売上本数No.1ブランドである「キリン 午後の紅茶」の「ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」の味覚・パッケージデザイン・容器を2018年以来6年ぶりに大刷新する。2024年6月18日より全国発売するのに先駆け、「午後の紅茶 戦略発表会」を開催した。
●キリンビバレッジならではのCSV経営
「『午後の紅茶』はおいしい紅茶飲料という価値だけではなく、社会課題の解決に貢献しているブランドでもあります」と話すキリンビバレッジ 代表取締役社長の井上一弘氏は、午後の紅茶を含むキリンビバレッジならではのCSV経営について紹介する。
国内における飲料市場は、人口減少の影響によって縮小する見込みであり、インバウンド需要の増加や健康ニーズの拡大などによって市場が好転する可能性はあるものの、「将来の見通しは不透明で難しい」という。そういった環境が今後も続くことが予想される中、キリンビバレッジが消費者に愛され、生き残っていくためには、「キリンの強みを最大限に活かしたCSVの実現が不可欠」との見解を示す。
CSVは“Creating Shared Value”の略で、社会課題の解決と経済価値を両立し、成長の次なる推進力にするもの。「キリングループは、様々な食、サービス、取り組みを通じてCSV経営を推進しており、従業員ひとりひとりがCSVを実践する力を持っている」という井上氏。中でもキリンビバレッジは、清涼飲料を通じて、子供から大人まで、幅広い層に価値を提供する会社であり、グループ内でもCSV経営を牽引する立場にあるという。
キリンビバレッジでは、「おいしい飲み物を通じて、お客様の心と身体の健康に寄与したい」という想いから、すべての事業活動の上位概念として、「お客様の毎日に、おいしい健康を。」という【お客様との約束】を設定。キリングループが標榜するヘルスサイエンス事業の成長を支援する意味でも、同社がはたす役割は大きく、極めて重要だとの認識を明らかにし、キリンビバレッジのCSVを伸ばしていくためには、従業員のマインドが大切であるとした。
さらに、「現場と本社の連携強化も重要」だと指摘。現場で気づいた課題を本社に共有し、適切な戦略を組み、それを現場で展開するといったPDCAを高速で回すことが必要であり、「戦略を実現するには、本社が描いている設計図が現場に伝わり、しっかり腹落ちできる実行感が大切」であり、中長期的には、現場から新たなCSV事業を起案するようなボトムアップ型の取り組みも進めていきたいとの展望を明かした。
そして2024年は、【お客様との約束】に基づく持続的な成長に向けて、ヘルスサイエンスを強みとした強固な事業ポートフォリオへの変革を加速させるとともに、CSVを基軸とした強いブランド作りと収益性の向上を目指すため、「おいしい健康を実現する強固なブランドの構築」と「持続的な成長を支える事業基盤の強化」といった2つの重点課題を設定。そして、「おいしい健康を実現する強固なブランドの構築」を実現するためには、プラズマ乳酸菌などのヘルスサイエンス飲料の拡大に加え、同社の基幹ブランドである「午後の紅茶」から新たな価値提案を行い、紅茶カテゴリをさらに魅力化、活性化していく必要があるとした。
●「午後の紅茶」から新たな価値提案を
「午後の紅茶」は、日本の紅茶市場をリードするカテゴリーNo.1のブランドであり、「キリンビバレッジのDNAといっても過言ではない」という井上氏。「午後の紅茶」がさらに成長し、日本に紅茶文化を定着させていくために、2024年は年間を通じて、紅茶が持つ上質感や報酬感が伝わるような飲用体験を提供していくとし、その中で、「午後の紅茶」の中核商品である「ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」については、中味、パッケージ、容器を6年ぶりに大きく刷新し、6月18日に発売する。
この3商品以外にも、新たなアプローチで紅茶の魅力を発信。「午後の紅茶」に一部使用されているスリランカ産の紅茶葉は、その品質の高さから世界中で愛されており、本年はスリランカ産紅茶葉を訴求することによって、「午後の紅茶」の品質感をしっかりとアピールしていくほか、夏場はアイスティーとして楽しむことで、紅茶をより身近な飲み物として感じられるシーンを提案していく。
「『午後の紅茶』はおいしさという価値だけではなく、社会課題の解決に繋がる価値を持つブランドでもある」と繰り返し、「午後の紅茶」に一部使用されているスリランカ産紅茶葉は、その約4割が日本に輸入されており、さらにその2割が「午後の紅茶」に使用されている点を言及。スリランカにおいて茶葉は国を代表する農産品であり、その輸出額は農業分野の約半数を占める。「つまり、『午後の紅茶』が売れるということは、スリランカ農家の経済的な支援にも繋がる」と井上氏は強調する。。
キリンビバレッジでは、スリランカの紅茶農園に対して、国際的な農園認証制度である「レインフォレスト・アライアンス認証」の取得支援を行っているが、この活動は、農家が自然や人権に配慮しながら継続的に紅茶葉を生産できるように、農業の技術を学び、認証取得に向けたサポートを行うというもので、同社のサポートによって、スリランカ国内の3分の1にあたる大規模農園が認証を取得。持続的に紅茶葉が輸入できる地盤が整いつつあるという。
また、2021年から発売されている「熊本県産いちごティー」は、売上の一部を熊本県の復興応援に寄贈して、地域支援に繋げているほか、ペットボトルに使用するプラスチックを削減することによって、環境負荷の低減を実現。「『午後の紅茶』は、まさにCSVを体現するブランド」と井上氏はあらためてアピールする。
日本でも数多くの紅茶葉が流通するようになり、ペットボトル飲料の種類も増え、コーヒーショップのような紅茶専門店も増加していることから、「日本の紅茶市場はまだまだ成長のポテンシャルがある」と井上氏。「日本の紅茶市場は『午後の紅茶』が牽引していると言っても過言ではありません。『午後の紅茶』ブランドを成長させていくことで、紅茶市場の拡大、紅茶文化の浸透に貢献し、お客様の毎日に、おいしい健康を届けてまいります」と締めくくった。
●スリランカにおける紅茶産業
続いて登壇した、駐日スリランカ大使のE.ロドニ・M・ペレーラ氏はまず、キリンビバレッジがスリランカの紅茶葉を使用した新商品を継続して発売していることに感謝の気持ちを述べ、「御社が紅茶葉の産地を具体的に紹介する取り組みは、消費者に深い感動を与え、商品との絆をより一層深めるもの」だと評価した。
また、キリンビバレッジがレインフォレスト・アライアンス認証のような世界的持続可能性の取り組みに積極的に参画していることを称賛。スリランカは日本と同様に、米と茶を主要作物とする農業国でありながら、気候変動による気象パターンの変化という深刻な課題に直面しており、経済的、環境的、そして社会的な持続可能性を取り入れた取り組みは、スリランカ農業の未来を担う重要な役割を果たすとの見解を示した。
ここでペレーラ氏は、「17世紀、イギリス国王のチャールズ2世は、紅茶をこよなく愛するポルトガル王女のカタリナ・デ・ブラガンザと結婚。この結婚をきっかけにしてイギリス王室では紅茶が朝食の飲み物として取り入れられるようになり、上流階級を中心に紅茶が流行。その後、徐々に庶民でも手の届く価格帯となり、現在では世界中で愛される飲み物となりました」と紅茶の歴史を紐解き、「近年、チャールズ3世が王位についたことから、今後さらに紅茶の消費量が拡大していく」ことに期待を寄せた。
そして、「セイロン紅茶の歴史は実はコーヒーから始まります」とペレーラ氏。イギリスの植民地時代、コーヒー農園者が生産物を町へ運ぶための輸送網を整備し、さらにイギリス国内の市場へも流通させる仕組みを整えたことでセイロンは世界最大のコーヒー生産国となった。しかしさび病という深刻な病気が蔓延し、セイロンのコーヒー産業は壊滅的な打撃を受けることに。そこで、壊滅したコーヒー農園の損失を補うため、セイロンティー産業が誕生。その数年後には、セイロンティーがロンドンの市場へ出荷されはじめ、茶の商業栽培は成功を収めたという。
「興味深いことに、ほぼ同じ時期の1862年、福沢諭吉が日本からヨーロッパへ向かう途中と、帰国時にスリランカを二度訪問している」との豆知識を披露。「現在、スリランカから日本への主要輸出品目である紅茶は、両国の友好関係をさらに豊かにしてくれている」と続け、ペレーラ氏自身、1月1日に発生した地震の被災地である能登半島を三度訪問し、被災者を励ますために、スリランカの紅茶とともにスリランカカレーをふるまったというエピソードを明かした。
セイロンティーは、土壌、日光、降雨量、標高差、そして東と西からのモンスーンの風がもたらす独特の気候条件によって、比類なき香りと味を生み出す。「高い抗酸化作用から認知機能向上効果まで、セイロンティーは健康と幸福感を高めるために最適な選択」だというペレーラ氏は、スリランカの「高原列車」についても言及し、「曲がりくねった路線をゆっくりと登る列車の車窓からは、緑あふれる茶畑、絵画のような丘陵地帯、そして雄大な森林が広がり、息を飲むような絶景が次々と現れます」とアピールした。
●「午後の紅茶」のブランド戦略
「『午後の紅茶』にはスリランカ産の茶葉が欠かせない」と話すのは、キリンビバレッジ マーケティング部 午後の紅茶 シニアブランドマネージャーの原英嗣氏。1986年の発売以降、一貫してスリランカの紅茶葉が一部使用されていることから、この紅茶葉の品質を高め、持続的に調達できるような環境を維持するために、レインフォレスト・アライアンス認証取得に向けた取り組みに加え、2007年にはキリンライブラリーを立ち上げ、農園の中にある学校に対して、図書を寄贈する活動も行われている。
「午後の紅茶」は、「日本に紅茶文化を創造し社会とお客さまの毎日を豊かにする」というブランドビジョンを掲げており、「紅茶を飲む価値、紅茶自体の価値をお客様に感じていただくことによって、日本でも紅茶が日常的に選ばれるような文化を作っていきたい」という原氏。コロナ禍を経て、楽しかった感情が下がり、ポジティブな感情がなかなか戻らない「お客様のマインド」に対して、「身近な紅茶で何かできることがあるのではないか」との想いを明かし、少しでも心も身体も豊かで良い生活を過ごしたいというマインドが上がってきている現状に対して、「そういったお客様の変化を捉えながら。紅茶を浸透させていきたい」と展望を示した。
紅茶の持つ可能性として、紅茶には上質感、香りの豊かさに加え、ホットでもコールドでも、ミルクを入れてもおいしいといった多様性も魅力のひとつだと指摘。紅茶ポリフェノールの健康価値も含め、そういった魅力があるからこそ、年代、季節、シーンを問わず、常に消費者に寄り添える存在である一方で、紅茶を普段飲まない人にとっては、「(他のカテゴリーと比べて)紅茶を飲むシーンがわからない」、また一部の人にとっては「ジュースの選択肢のひとつ」になっているなど、現状とのギャップを指摘。「よりお客様が紅茶を飲みたくなるようなシーンを作り出し、紅茶本来の上質な体験で、『紅茶っておいしい!』という経験をひとつでも多く作っていく」という必要性を示した。
そういったギャップを埋めるためにも、「2024年は、お客様が紅茶を飲みたくなる瞬間をイメージできるようなアクションをしていきたい」という原氏。特にレギュラー3品と言われる「ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」や、「おいしい無糖」を通じて、紅茶を飲むシーンを想起できるような活動をしていくとし、さらに昨年発売された「TEA SELECTION」シリーズなどによって、紅茶の強みである報酬感を特徴的に伝え、紅茶の上質な体験を創造。こうしたことを通して、「紅茶カテゴリー拡大戦略」を継続していくとした。
「カテゴリーを拡大するために重要なのがこの夏の取り組み」であり、清涼飲料の最盛期である夏に、昨年から始まった「夏のアイスティー」を継続して訴求。その中心となるのが6月18日にリニューアルされるレギュラー3品であり、さらに普段紅茶を飲まない人が紅茶を手に取る機会を作れるような新商品やイベント体験などを協業パートナーとともに盛り上げていきたいという。
そして、「午後の紅茶」のおいしさの理由をあらためて解説。「紅茶へのこだわり」として、「午後の紅茶」はフレーバーごとに紅茶葉の特長をいかした相性のよい品種が選定されているほか、「製法へのこだわり」としては、冷やせば濁るという紅茶の性質を、度重なる試行錯誤の末、雑味のない味わい、透明でクリアな液色を実現した「クリアアイスティー製法」、さらに、ポットで淹れる紅茶とまったく同じ手順で作ることにより、本格的な味わいを引き出す「製造工程へのこだわり」について言及した。
今回リニューアルされる3品について、「ストレートティー」は心地より甘みとすっきりした後味が楽しめるように、「ミルクティー」はミルクの満足感を高めるように、「レモンティー」は紅茶の香りとともにレモンの甘酸っぱさが感じられるようにそれぞれ味わいが変更されており、パッケージも6年ぶりに大きく刷新。これまでのシュリンクラベルからロールラベルに変更することで、プラスチックの樹脂量が削減されているほか、「午後の紅茶」のシンボルであるアンナ・マリアの肖像を少し大きく目立たせることで、現代性や上質感をアップさせているという。