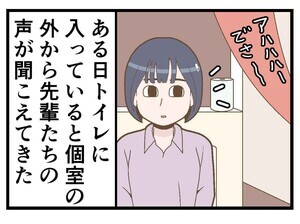◆本記事はプロモーションが含まれています。
【この記事のエキスパート】
音楽/DTM/PCオーディオ 専門ライター:田澤 仁
90年代にプロドラマーとして活動、その後、音楽ライターとして書籍、雑誌などの執筆を行なっている。
DTM、PCオーディオ関連の著書、DTMソフト、シンセサイザーの日本語マニュアル制作など多数。
Webでは2007年~2009年までサイトAll Aboutで「ロック」のガイドを務めたほか、音楽情報サイトBARKSでは国内外の数多くの有名アーティストのインタビュー、ライブ取材などを行なっている。
得意分野はAOR、ハードロック、フュージョン、80年代。
カスタネットは誰もが子どものころから慣れ親しんでいる楽器で、フラメンコやオーケストラ、バンドのパーカッションでも広く使われています。ここでは、音楽ライターに聞いたおすすめと選び方を紹介。通販サイトの最新人気ランキングもチェックしてみてください。
音楽ライターがおすすめする
カスタネットの選び方
それでは、カスタネットの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の3つ。
【1】種類・形状で選ぶ
【2】素材で選ぶ
【3】サイズは手の大きさにあわせて選ぶ
上記の3つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】種類・形状で選ぶ
カスタネットは形状に応じて「丸型」「貝殻型」「柄付きタイプ」の3種類のタイプに大きく分けることができます。それぞれどのような特徴があるのでしょうか。
丸型:小学校でおなじみの定番カスタネット
カスタネットといえば、多くの人が思い浮かべるのが赤と青に色分けされた子ども用の「丸型」のものでしょう。片手で持って叩けば音が出る簡単な仕組みなので、教育用にも使われていて、子どもが音楽に親しんだりリズムを身につけたりするのに最適です。
貝殻型:フラメンコなど本格的な演奏に
クラシックのオーケストラやフラメンコで使われるのがこの「貝殻型」です。音程の異なる1組を両手に持って複雑なリズムを鳴らせるのが特徴。
通常は閉じた状態なのできちんと技術を身につけないと鳴らせませんが、慣れればドラマチックな演奏ができるようになります。本格的な演奏をしたいなら貝殻型を使いましょう。
柄付きタイプ:扱いやすく種類が豊富
貝殻型のカスタネットに柄が付いたものが「柄付きタイプ」です。手や脚に打ち付けて鳴らすこのカスタネットは、初心者でも演奏しやすいのが特徴です。
なお、貝殻型の練習に最適なコンサートカスタネットや、子どもでも扱いやすいスティックカスタネット、振るだけで音が鳴るフラッパーカスタネットなど、さらに種類が分かれています。
スタンドタイプ:パーカッション奏者向き
卓上に置いたり、スタンドにマウントして利用するカスタネットが「スタンドタイプ」です。これはさまざまな楽器を並べてプレイするパーカッション奏者向きになります。
【2】素材で選ぶ
カスタネットに使用される素材はおもに「木製」と「樹脂製」です。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
木製:深みのある音が特徴
木製のカスタネットは見た目の雰囲気がよく、音には深みがあって響きもよいので、あたたかい音で演奏したい人や複数人数でカスタネットを演奏する人にも向いています。ただし、希少な高級木材を使ったものは値段も高価です。
樹脂製:抜けのよい音が特徴
樹脂製のカスタネットは湿気などの影響を受けにくく、スティックなどで叩いても破損しにくいなどの特徴があり長期間使えます。また、木製より音の抜けがよいのでほかの楽器がたくさんあってもしっかり聞こえてきます。バンドで使うなどの場合は樹脂製をおすすめします。
【3】サイズは手の大きさにあわせて選ぶ
【エキスパートのコメント】
カスタネットにも色々なサイズがあります。サイズが大きいほど音量も大きく音程が低くなり、コンパクトなものは音量が小さく高い音になりますが、演奏のしやすさを考えると、音よりも自分の手の大きさに合わせることのほうが重要です。できれば一度は店頭などで手に取って、しっくりくるサイズかどうかを確認しておきましょう。
また、カスタネットのサイズは、5号、6号というように号数で表されることがありますが、メーカーによって同じ号数でもサイズが異なることがあるので注意してください。