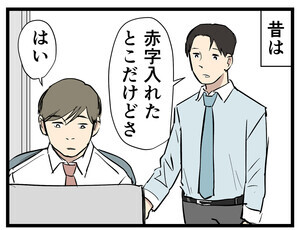浮遊感あるサウンドと映像、目を惹くタイトルの「あ」の一文字。感性を刺激されるさまざまなコンテンツをつめこんだNHK Eテレの子ども向け人気番組を元にした企画展『デザインあ展 in TOKYO』が、日本科学未来館(お台場)で開催されている(10月18日まで)。
「デザインあ展」は、2013年以来2度目の開催となり、2018年の展示は内容が一新されている。同展は東京以前に開催された富山会場も、今後巡回予定の山梨会場と熊本会場、そして2013年当時の展示場所もすべて美術館で、科学館が舞台になったのは、この東京展が初めてとなる。
サイエンス関連のユニークな企画展を多く展開している未来館が、「デザイン」をテーマにした同展の東京会場となった理由はどこにあったのだろうか。展示内容の一部、および同展にかかわったクリエイターたちの言葉を紹介しながら、同展の開催意図に迫っていきたい。
「みる」「考える」「つくる」
「デザインあ展」は、番組で映像を介して伝えている「デザインマインド」を、インタラクティブに体験することを狙った企画展となっている。
「デザインマインド」とは、身の回りの物事がはらむ問題・課題を見つけ出し、解決法を生み出す一連の思考を指す。とはいえ、番組にも展示にも、この文章から感じるような堅苦しさはない。ごく身近なテーマから、あらたな発見を導き出すような仕組みが盛り込まれている。
もちろん、番組を手がけているクリエイター陣が同展にも携わっている。総合ディレクターは、番組総合指導を行っているグラフィックデザイナーの佐藤卓氏。映像に関しては映像ディレクターの中村勇吾氏、音楽はミュージシャンの小山田圭吾氏が担当している。
また、展示構成については、「解散!」「デザインの観察」など人気コーナーを制作した岡崎智弘氏、「てん せん めん」「のこり」などを担当するパーフェクトロン、「アン・ドゥ・トロワ」「なんやかんや」を手がけたplaplax(プラプラックス)がディレクションを行った。
展示内容は現地で「体験」することで完成するものが多いため、ここでの紹介は最低限にしたいが、個人的には、展示会場の最後のエリアにあった「しくみ寿し」(パーフェクトロン+柴田大平)を何ループかするほど夢中になって見てしまった。
入場してすぐ広がる「観察のへや」の展示には、いずれの作品にも、先の思考をかみ砕いた「みる」「考える」「つくる」という3ステップが含まれている。

来場者自身が作品に触れ、手を動かすことで成立する展示も多く、それには「あそべる」というマークがつけられている。
デザインという「思考」は科学に通じる
未来館で数々のヒット展を手がけてきた名物キュレーター・内田まほろ氏は、「デザインあ展」は未来館でやる意義のある展示と胸を張る。
その一方で、著名な宇宙飛行士の毛利衛氏を館長とし、宇宙開発やロボットなどに関する常設展を備えている「日本科学未来館」は、「科学技術の知識を得る場」としてのイメージが強い。そんな同館が今回、「デザインあ展」の会場をひきうけた狙いについて問いかけた。
すると、「デザインあ展」と未来館という場が結びつきにくいのは、「デザイン」という言葉が持つイメージが、日本と諸外国とで異なることが前提にあると指摘された。
「日本では、デザインについて学ぶコースは美大にあることが多く、美術の一角にあるようなものと思われがちです。一方、ヨーロッパやアメリカではデザイン科が工学部にあることが多く、かつプロダクトデザイン以外の領域にも広がりがあります。『デザイン』は特別な人の才能ではなく、思考と感性によって問題を解決する力です。近年では日本でも、そうした捉え方が徐々に広まっている段階にあると考えます」(内田氏)
未来館の展示企画は、「科学技術を軸にしながらも、『未来のために思考する』ことに重きを置いて」立案されている。そこで、未来館では、複雑な問題を解決しなくてはならない未来をつくっていく上で、デザインは「必要不可欠な新たな知」と捉え、「デザインあ展」の開催に至ったと語った。
また、未来館が主に扱っている科学技術は、デザインと接点を持っている、と内田氏。初代「デザインあ展」会場となった21_21 DESIGN SIGHTのディレクター・三宅一生氏と、同館の毛利衛館長は以前より交流があり、立ち上げ当初から共に企画を練り上げてきたという。
「展示はテーマごとに『みる』『考える』『つくる』という3つのステップで展開されていますが、これはさまざまな科学技術や研究者のマインドの中にも見つけることができる要素です。同展をきっかけに、科学に興味のある方がデザインに、逆にデザインに興味のある方が科学技術にも興味を持つことで、相互理解が深まり、”未来をつくる力”が高まっていくと信じています」
こうした「相互理解」を促進するために、東京展限定のコンテンツとして、『かがくの「あ」』というパネル展示を設置している。
総合ディレクターの佐藤卓氏は、内覧会の中で「子どもの頃からデザインマインドに触れることは大切」と語っていた。それを受けてか、同展の会期は夏休み期間を含む約3カ月に設定されている。
夏休みの未来館は例年多くの子どもたちが来場するため、子どもの好奇心を受け止められるような企画展が催されている。「『デザインあ展』は子ども達の期待を引き受けられるものとなっているので、会期は自然と夏に設定された」(内田氏)そうだ。
デザインという言葉がビジネスの場でも現れるようになって久しいが、内田氏の指摘にあるように、日本ではまだグラフィックデザインやファッションデザインのイメージが強い。また、ビジネス分野における"デザイン"は、「デザイン思考」「UX/UI」などのキーワードに代表されるように、いわゆる”美大で学ぶデザイン”とは異なる知見として認知されているようにも感じられる。
佐藤卓氏は、「”デザインのこと”を決定するのは、デザイナーではないことが多い。全ての方々にデザインを考えていただくきっかけになれば」と、実務家の視点からもコメントしていた。
「デザインあ展」の内容は、子ども達はもちろんのこと、"デザイン"を専門としない、デザイナーの「クライアント」となる可能性のある人々にとっても、日常に根ざした新鮮な驚きを与えてくれるものになっている。
デザインが「特別な才能」ではなく「思考の方法」として広がることによって、未来はより良い方向に”デザイン”されていくのかもしれない。
(杉浦志保)