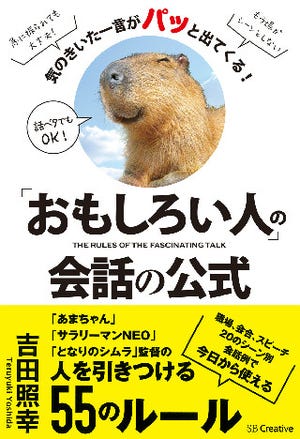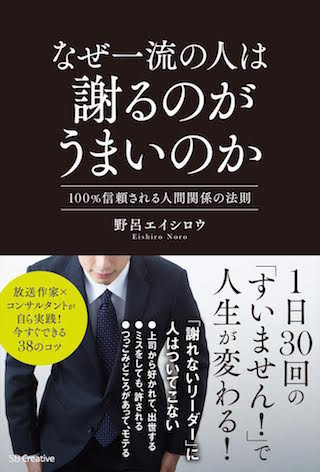"Stay hungry, stay foolish"で締めくくられるスティーブ・ジョブズのスピーチはあまりにも有名だ。YouTubeなどで動画を見たことがあるという人もきっと多いことだろう。このスピーチはスタンフォード大学の卒業式で行われたものだが、このように著名人が大学に招かれて卒業生に向けてスピーチを行うというのはアメリカではよく行われる。
ネット上ではスティーブ・ジョブズのスピーチばかりが有名になりすぎている気がするが、感動的な卒業スピーチを行ってきた著名人は彼以外にもたくさんいる。たとえばアマゾン創業者のジェフ・ベゾスやグーグル創業者のラリー・ペイジのスピーチなどは、スティーブ・ジョブズのスピーチに勝るとも劣らない感動を与えてくれる。今回紹介する『巨大な夢をかなえる方法 世界を変えた12人の卒業式スピーチ』(佐藤智恵訳/文藝春秋/2015年3月/1600円+税)は、そんなハイクオリティな卒業スピーチを12個収録したある意味では非常に贅沢な本だ。将来の方向性に迷いつつある人は、読んでみると何か掴めるものがあるかもしれない。もちろん、純粋に著名人のスピーチに興味があるというだけの人でも十分に楽しめる。
世界を変えた豪華な12人
本書のサブタイトルは「世界を変えた12人の卒業式スピーチ」であるが、これは本書に掲載されている12人のラインナップを見てみると決して誇張ではないことがわかる。とりあえず、メンバーを列挙してみよう。
ジェフ・ベゾス(アマゾン創業者)
ラリー・ペイジ(グーグル創業者)
メリル・ストリープ(俳優)
トム・ハンクス(俳優)
ジャック・マー(アリババグループ創業者)
ディック・コストロ(ツイッターCEO)
イーロン・マスク(テスラ・モーターズ創業者)
ジェリー・ヤン(ヤフー創業者)
マーティン・スコセッシ(映画監督)
チャールズ・マンガー(バークシャー・ハサウェイ副会長)
サルマン・カーン(カーンアカデミー創設者)
シェリル・サンドバーグ(フェイスブックCOO)
いずれも世界最先端の起業家、投資家、教育者、俳優、映画監督であり、実際に日々世界を変え続けている人たちである。気になる人が1人でもいるならまずはそこを起点として、できれば12人全員のスピーチを読んでみて欲しい。きっと上質な時間を体験できることだろう。
人生のステージを先に進めるためのヒントとして
もしかしたら、この12人のような「すごすぎる」人たちの話は、自分とは次元が違いすぎて全然参考にならない、と決めつけてしまう人もいるかもしれない。
そうやって本書を避けてしまうのは正直もったいないと思う。彼らはたしかにある分野についての専門家でそういう意味では彼らと同じ次元に立てる人はあまり多くはいないはずだが、そもそも本書で彼らが語っているのはそういう専門的な話ではなく、誰にでも通じる「生き方」や「夢を叶える方法」についての話だ。
このような卒業スピーチは"commencement speech"(コメンスメントスピーチ)という名前で呼ばれている。commencementという単語には「開始」「始まり」という意味があり、つまるところcommencement speechとは大学を卒業して、人生の新たなステージを始めようとする卒業生に向けて激励の言葉を贈るという行為にほかならない。テーマも「失敗」や「家族」といった普遍的なものであり、これが参考にならないという人は基本的にはいないはずである。人生のステージを先に進めるためのヒントとして、本書はきっと役に立つに違いない。「偉大なる先輩」からの激励メッセージだと思って、変な先入観は持たずにとりあえず読んでみることをおすすめする。
たまに訪れる成功の数より試練の数のほうがずっと多い
個人的に、本書で一番興味深く読んだのは映画監督のマーティン・スコセッシがニューヨーク大学で行ったスピーチである。今では巨匠と称されないことがないマーティン・スコセッシであるが、必ずしもトントン拍子で今の地位を築いたというわけではない(これは、他の11人についてもほぼ共通して言える)。憧れの監督から突き放されたこともあるし、出資候補者から「君には一ミリの才能もない」と酷評されたこともある。スコセッシ曰く、芸術家の人生をトータルで考えれば、たまに訪れる成功の数よりも、試練の数のほうがずっと多いのだそうだ。
それでも彼が成功を手にすることができたのは、「創作そのものに対する情熱」を失わなかったからだ。この「情熱」がまず大前提としてある、という姿勢は芸術に限らずあらゆる分野で成功するための基本的な考え方なのではないだろうか。僕はマーティン・スコセッシのスピーチを読んでそんなことを考えた。
みなさんも、本書で自分なりの生きるヒントを見つけだしてもらえればと思う。
日野瑛太郎
ブロガー、ソフトウェアエンジニア。経営者と従業員の両方を経験したことで日本の労働の矛盾に気づき、「脱社畜ブログ」を開設。現在も日本人の働き方に関する意見を発信し続けている。著書に『脱社畜の働き方』(技術評論社)、『あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。』(東洋経済新報社)がある。