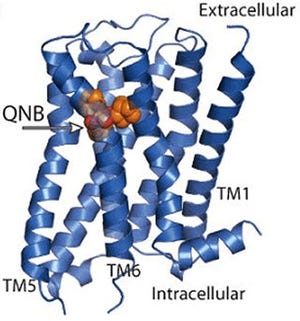京都大学(京大)は、ヒトのES細胞からドーパミン神経細胞を誘導し、この細胞をパーキンソン病モデルのカニクイザルの脳内に移植することによって神経症状を改善させることに成功したと発表した。高橋淳准教授と土井大輔研究員(ともに京都大学再生医科学研究所/iPS細胞研究所/医学研究科脳神経外科)らの研究グループと、理化学研究所との共同研究による成果で、論文は「Stem Cells」に掲載された。
パーキンソン病は進行性の神経難病で、「ドーパミン神経細胞」が減ることで脳内のドーパミン量が減り、手足が震える、体がこわばって動きにくいなどの症状が出るのが特徴である。
これまでの薬物や電極を用いた治療法では、いったん症状は改善できてもドーパミン神経細胞の減少を食い止めることはできないことが問題となっていた。そこで、細胞移植によって神経細胞を補い、新たな神経回路の形成を促して機能を再生させるという、より積極的な治療法に期待が寄せられており、ヒトES細胞やiPS細胞もその移植細胞の候補となっている。
これまで、マウスやヒトのES細胞から作製したドーパミン神経細胞は、パーキンソン病のラットモデルで症状改善効果が確認されているが、ヒトES細胞から誘導したドーパミン神経細胞の挙動が霊長類の脳で調べられたことはなかった。臨床応用を目指すためには、霊長類のパーキンソン病モデルを用いて、ヒトES細胞から誘導したドーパミン神経細胞の有効性と安全性を厳しく検証する必要があるというわけだ。
これまでマウスやラットへの移植で、神経分化が不十分で未分化ES細胞が残っている場合には、移植後に腫瘍が形成されることが報告されている。研究グループは、同じ霊長類であるサルの脳内で細胞の増殖がどのように進むのかを調べるため、あえて未分化ヒトES細胞が約35%混じった神経細胞をサル脳に移植し、9カ月間観察した。
その結果、腫瘍は形成されたが、悪性所見はなく境界は鮮明であることが確認された。一部未分化ES細胞が凝集し細胞増殖が盛んな部分があったが、この部位は「フルオロチミジン」を用いた「ポジトロンCT(FLT-PET)」によって検出が可能だったのである。
分化日数を長くしていくと、成熟したドーパミン神経細胞の割合が多くなるが、分化日数を長くするに従って移植片が小さくなり、42日間分化誘導した細胞のサル脳への移植では4頭中3頭で6カ月後から移植片の増大が見られなくなった。つまり、十分に分化させた細胞の移植では、移植後の細胞増殖が低いため、腫瘍形成が見られなくなったというわけである。
細胞移植後、手足の震えや歩行状態などを点数にして12カ月間経過観察をしたところ、3カ月目から有意な症状改善が見られ、12カ月間持続した。また、ドーパミン前駆物質を用いた「ポジトロンCT(FDOPA-PET)」において移植部位に一致して取り込み上昇が見られ、移植細胞がドーパミンを合成していることを確認した。
さらに脳切片の免疫染色により、12カ月後においてもドーパミン神経細胞が多数生着していることが明らかとなった。つまり、ヒトES細胞由来ドーパミン神経細胞の移植によって、カニクイザルパーキンソン病モデルの神経症状が改善したのである。
今回の研究では、ヒトES細胞由来ドーパミン神経細胞の移植によってカニクイザルパーキンソン病の神経症状が改善されることが世界で初めて明らかにされた。ドーパミン神経細胞を多く含んだ細胞の移植では、移植片が増大しなくなったと同時に神経症状の改善が見られたという点がポイントだ。
この成果は、ヒトES細胞を用いたパーキンソン病治療が可能になることを示唆している。おそらく、ヒトiPS細胞でも同様の効果が得られるものと考えられている次第だ。今後、より安全で効果的な移植を行うためには、ドーパミン神経細胞を純化する技術の開発が必要であると思われると、研究グループではコメントしている。