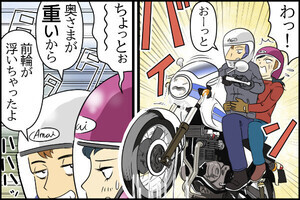車をお持ちの方もそうでない方も、知っていますか?
クルマのバッテリーは消耗品なんです!
クルマの神経をつかさどるECU(エンジンコントロールユニット)をはじめ、エンジンを始動させるイグニッション、ヘッドライトやエアコンなど、とにかくクルマに関する多くの機能にバッテリーが関係しているんです。
だからこそ、バッテリーも、「エンジンオイル交換などと同じくらい、気に留めてあげて」とメカニックたちは言います。でも、「いつが交換タイミングなの?」「どんなバッテリーを選べばいいの?」と分からないことばかりなのが、現実ではないでしょうか。
マイナビニュース会員501名を対象に行った「車についてのアンケート」でも、約半数にあたる48.1%の方が「ほぼ毎日運転している」と回答しているにも関わらず、「車のメンテナンスで不安なことや分からないこと」として、51.9%の方が「バッテリー交換」を挙げています。
クルマに積まれたバッテリーが、どんな仕事をして、どうメンテナンスすべきか――。
「そのリアルな実情を聞くならば、自動車用バッテリー日本国内シェア第1位(※)のGSユアサじゃないか」ということで、同社のバッテリー専門チームに問い合わせると、「現場のメカニックに聞くとわかりやすい」という答えが返ってきた。
※国内調査会社による2016年度国内自動車用補修バッテリーシェア調査において
国内各地にいるバッテリーマイスターという存在
そこで取材班は一路、茨城県守谷市へ。常磐自動車道谷和原インターチェンジから南へ1.5km、ナオイオート 守谷店にて、整備工場とカウンターを休む間もなく動き回るサービス事業部スーパーバイザー 杉田貴志さんにお話を伺った。
杉田さんは、スーパーバイザーとは別の肩書としてバッテリーのスペシャリストである「バッテリーマイスター」を持つ。これはGSユアサが認定しているもの。同社では、バッテリーのスペシャリストを育成・認定する同制度を展開しているのだ。
現在、GSユアサ認定マイスターは、のべ1万人を超え、マイスターが常駐する店舗は、2017年5月末時点で約3200店を数える。このマイスター店のなかでも、ナオイオートは全国トップクラスのバッテリーのスペシャリストだという。
クルマもスマホや電化製品と同じように見てあげて
そんな杉田さんにまず「バッテリーとは」という質問をしてみた。すると、杉田さんは、クルマの専門的なことに知識がない人にも分かりやすいように、こう教えてくれた。
「いまのクルマはスマホや電化製品と同じように、『電気を使って動いている』ということを知ってもらいたいです。エンジンの回転で発電して、電気を適宜、充電して放電しているんです」
要は、スマホやノートパソコンのバッテリーと同じように、クルマの電池も寿命があるということだ。
「通常、クルマのバッテリーは2~3年で交換時期がやってきます。エンジンをこまめに止めたり回したりする使用状況のほうが、バッテリーに負担がかかるんです。なので、たとえば駅や保育園への送り迎えや近場の買い物で毎日クルマを走らせていると、キーを回す機会が増えるので、バッテリー負担も大きくなるんです」
バッテリーの状況が見えないからこそ予防整備
「いま走っているクルマたちは、燃費を向上させる充電制御機能が付いたタイプ、アイドリングストップ車、従来までのスタンダード車、ハイブリッド車(プラグインハイブリッド車)、の大きく4種類に分かれます。」
この大半を占める充電制御車とアイドリングストップ車は、バッテリーの劣化や寿命にドライバーが気付きづらくなっているという。
「クルマのバッテリーは消耗品であることも、まだまだ認知されていません。時計やデジカメの専用電池と同じように、必ず劣化して交換時期をむかえます。マイスターとしては、ちゃんとバッテリーにテスター(測定器)をあてて、現在のバッテリーの体力を数値で判断して、ユーザーに予防整備を提案していくことが大切なんです」
なぜGSユアサか? プロが感じた利点
こんどはバッテリーのメーカーに注目してみる。ナオイオートは、GSユアサ製バッテリーをバックヤードに取り揃える「マイスター店」。GSユアサ以外にもバッテリーを製造・販売を行っている会社はあるが、なぜGSユアサなのか。
「若い人たちは、その知名度や家電製品で親しまれている会社のバッテリーを選ぶことが多いですが、圧倒的シェアと実績、歴史、信頼性でいうとGSユアサですよね。クルマを知っている人であればGSユアサというブランドの価値が分かっているはずですよ。それから、GSユアサのバッテリーは、さまざまな車種にマルチに対応しているところが特徴です。車種別のバッテリーを置くと、どうしてもバックヤードの在庫も増えてしまいます。このあたりは同じ業界内でも、GSユアサ製が評価されるポイントですね」
杉田さんは、GSユアサ製バッテリーのアドバンテージについて、この在庫管理上や対応力のほか、メカニックやサービス対応のスタッフたちへの教育という側面で貢献している点を挙げた。
「商品知識や整備技術を向上させるために、不定期でバッテリーの工場見学などを行い、知見を深めています。メカニックも、生産工程を見て体感すると、バッテリーの技術的側面などもわかり、次のサービスに活きる。インターネット上の知識を超えるスキルが身につきますよね。そういった機会をGSユアサさんが提供していることも大きいですね」
発電機を壊すとトータルコストで痛手に
話をユーザー視点に戻して、こんどはバッテリーを定期的に交換するポイントについて、杉田さんに聞いた。
「バッテリーを長く使おうと考える方も多いのですが、いまのバッテリーはむやみに長く使い倒そうとすると、こんどは発電機に負担がかかって、最悪の場合は発電機が壊れてしまいます。発電機の交換費用のほうが大きいので、バッテリーを定期的に交換するほうが、トータルコストとしては有利です。これが予防整備という考え方です」
「クルマの買い替えを数年後に考えているのであれば、提案の仕方も変わりますが、そのクルマに長く乗りたいという場合は、定期的なバッテリー点検と交換を提案しますね。もっともわかりやすいのは、車検時の交換。2年サイクルで交換していくというスタンスですね」
こうしたバッテリーの基礎知識や、交換方法、メンテナンスなどについては、GSユアサ公式ホームページにも掲載されている。
マイナビニュース読者からの質問
ここからは、読者から寄せられた質問を、杉田さんに聞いてみよう。

A.「基本的には自分で交換しないほうがいいですね。電化製品と同じで、車載コンピューター(ECU)が、クルマの使用状況を学習していますから、自分でバッテリーを外したり付けたりすると、その蓄積データがリセットされちゃうリスクがある。最悪は、アイドリングストップの挙動が変わったり、燃費が悪くなったりします」

A.「タイヤはその側面に製造年月日が記されています。劣化はわかりづらいので、3年という経年数がひとつの判断材料です。もしくは、タイヤの溝にあるスリップサインが出ているか、ヒビが入っていないかによっても見極めることができます。それから、保管状況ですね。太陽の紫外線で、ゴムが固くなっていきます。あとセルフスタンドの普及でバルブが劣化するケースが多いですね。セルフ給油のスタンドが普及すると、タイヤのエア充填などのサブメニューもドライバー自らが、見よう見まねで試し始めますよね。タイヤのエア充填の入り口となるバルブは、意外と繊細なんです。そのため、プロでない方がエア充填を行うと、バルブが壊れてしまうケースがよくあるんです。なので、タイヤとエアーバルブをセットで交換したほうがいいですね」

A.「ワイパーは、雨滴を掃き取るというイメージですが、実はきれいに水の膜をつくっているんです。だからゴムだけ交換するだけではなくて、ブレードもいっしょに交換して、均一のテンションでワイプできるようにメンテナンスしたいですね。ゴムは半年に1回、ブレードは2年に1回程度が目安です」
クルマはかかりつけ専門医による定期検診を
ここまで杉田さんにクルマのメンテナンスについて、いろいろ聞いてきた。バッテリーもタイヤもワイパーも、消耗品であることをあらためて知らされた。
別れぎわ、杉田さんは最後に、クルマと長く付き合うポイントとして、こう教えてくれた。
「かかりつけの医者、主治医と同じように、クルマも専門医による定期検診を続けてほしいですね。我々も、GSユアサのマイスター制度などを活用して、常に最新の情報と、更新した技術や知見でユーザーに提案し、ユーザーのクルマ生活に寄り添っていきたいと思っています。ユーザーのカルテを常に更新させて、そのときのベストな提案をしていきたいですね」
ナオイオート 代表取締役 直井清正氏より

ナオイオート 代表取締役 直井清正氏
昨今の自動車は、安全装備や各種の電動化が進み変化がめまぐるしい状況です。しかしながら、自動車にとってバッテリーがなくてはならない部品であることには変わりありません。こうした中、予防整備の提案こそが、我々整備業者としての役割、任務ではないでしょうか。 これからも社内勉強会やGSユアサとの連携を通じて、最適な提案が出来る環境整備に努めたいと思っております。