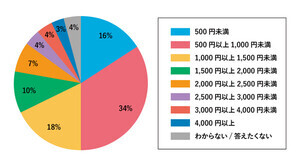ギリシャに端を発したユーロ危機はまたたくまにアイルランド、ポルトガル、スペイン、イタリアに対する金融懸念に広がりユーロ経済圏を脅かしつつある。これらの国にはアイルランドを除いて共通点がある。
地中海に面している事である。そこには愛すべき心のやさしい小柄な人々が住んでおり、細かいオーガナイズが不得意ではあるが、それにはちゃんとした理由が有る。
プライドは高く、いざとなると一身を投げ打ってでもものにのめりこむ情熱を持っている。美しいものと美味しいものを愛し、時間の流れをいつくしみ楽しむ術を心得ている。アイルランドも地中海からは遠い事を除けば確かな共通項が見出せる。
私は人生で最も心地よい時間をしばしばこれ等の国々で過ごした。
真っ暗闇な古代ギリシャ野外劇場
「ブラボー」、「ブラビッシモ」。まるでサクラではないかと思われるほどの大げさな歓声と共に拍手の波が巻き起こった。後から考えるとサクラであったのかもしれない。舞台上の私は椅子から立ち上がりお辞儀をして改めて会場を見渡した。紀元前にギリシャ人がやって来て建てたというこの野外古代劇場には照明設備が全く無い。舞台の上に設置された6台のスポットライトだけが私とチェロを真っ暗闇の中に浮かび上がらせていた。古代劇場の客席はと言うと漆黒の暗闇に包まれ、私だけを照らすライトが眩しすぎて何も見えなかった。円形競技場のような設計なので舞台と観客席は非常に離れており、観客の誰一人として見ることが出来なかった。しかし沢山の人々がそこに居て、私を注視しているのは気配で分かった。
 |
(画像:昼間、舞台から観客席で休む筆者を写した。石造りの椅子は反響版の役目を果たすように設計されている) |
ただ拍手だけがワンワンと呻りながら魑魅魍魎(ちみもうりょう)のように暗闇の中から私に向かって押し寄せて来る。それは本当に気持ちの悪い経験だった。もしこの拍手がサイレンであれば、刑務所の脱獄に失敗した囚人がサーチライトに捕捉されて壁に追い詰められるあの絶体絶命の光景である。
そうだったのか。昼間に訳の分からない連中が会場をごてごてと飾り立てていた赤や青の照明は観客席を照らす為の物だったのか。私は総練習の時にすっかり腹を立てて、それらの照明の取り付けを断固として拒否し、取り払いを命じたのだ。
事の発端は昼間に大きなトラックがやってきて、ロックバンドが使うような巨大スピーカーや、使いもしない何本ものマイクロフォンを勝手に設置し始めたからだった。私が演奏するのはイタリアで16世紀に作曲された現存する楽譜としては恐らく世界で最古のチェロ無伴奏曲だった。
当時のチェリストがもしもこの古代劇場でこの曲を演奏したら、マイクロフォンと1000ワットの拡声装置を必要としただろうか? ましてや舞台から観客席まで取り囲むようにして設置され始めた赤と青の下品なライトを必要としただろうか?
これじゃ、盆踊りで無ければダンスパーティの会場ではないか。「なにこれ? そんなものいらない」。彩色照明の意味が分からなかった私はその設置を固く断ってしまったのだ。

|
|
(画像:左側に巨大な6基スポットライト、右側に2基。照明の設置が始まった) |
昼間、大型トラックに満載の大げさな器具と驚くほど多人数の作業員を引き連れてやってきたシチリア風に浅黒い肌のステージマネージャが言った。「マエストロ、私たちは自分たちの仕事をやってるだけなんだから、任せてくれないか? 別に何を設置しようがあなたが構うことじゃないと思うんだがね。そんなに心配する事はない。マエストロ、この前フランク・シナトラがやって来た時もショーは完璧に上手く行ったよ!」。
え、フランク・シナトラ・ショー? これはショーではない。コンサートだろう? 私はあきれ返って言った。「いらない、いらない、赤や青の照明は全部取り外して欲しい。こういうのはクラシックでは使わないのだよ。」
シチリア島からの招待
 |
(画像:シチリア島地図、Wikipedia, GNU Free Documentation Licenseによる引用) |
その半年くらい前のこと。イタリアの何とかカントカ文化交流センターを名乗る組織から電話があったのがそもそもの始まりだった。知らない人がいきなりこう切り出してきた。「タナカさん、お願いがあるのだが、あなたは国際的な音楽文化交流企画の経験が豊富だと聞き及んでいるのですが、もしよろしければシチリア島に日本の古典芸能を紹介する企画に協力をしていただけないだろうか?」
そういわれると確かに私は当時、尺八の遠藤ひとみ氏とハープのテツケ・クラインと組んでムジカ・トリフォルムという実験的なトリオを結成しオランダ国外まで演奏旅行に出かけたり、ローマには既に二度ほどクセナキス・アンサンブルと演奏旅行に出かけ、この企画の中で現代日本の優れた弦楽四重奏曲をイタリアに紹介したりしていた。またイタリアからは神秘主義作曲家の巨匠ジャキント・チェルシや若手のルーカ・フランチェスコーニの作品をオランダに紹介する企画などにも頻繁に参画していた。
 |
|
(画像:ローマ古代遺跡における演奏会。湯浅穣治作曲弦楽四重奏曲、昼間の総練習中) 「ついては、是非貴国のゲイシャ・ダンサーズをシチリアにお呼びしたいのだが如何なものでしょうか? 」私は呆気に取られて絶句するばかりだったが、そもそもゲイシャ・ダンサーズという魅惑的な名前が一体何を指しているのか、聞きただしているうちに向う側も実は自分が何を欲しているのか良くは分かっていない様子が判明してきた。 |
私はゲイシャ・ダンサーに一度として会う幸運に巡り合った事すらない。ふつうなら、こんなに的外れな企画を持ち込まれたら直ぐにお断りするのだが、シチリア島からの誘いであり、しかも一番肝心の資金がたっぷりと用意されている様子が気になった。この電話が私にとっては世にも奇妙なコンサート、もしくは彼らが呼ぶショーの企画が立ち上がったキッカケである。
とりあえず、アムステルダムにその組織の支部があるので、そこの支部長から詳しい説明を聞いて頂きたいということになり、そこを訪ねてみる事にした。支部と言っても普通の住居内に構えた事務所に綺麗なイタリア人女性がたった一人で迎えてくれただけなのではあるが。
要するにシチリア島で二番目に大きな港町シラクサ(シラクーザと発音されていた)の近郊にある古代ギリシャの遺跡でゲイシャ・ダンサーズによる伝統舞踏の興行をしたいという企画だった。その企画は私には無理な注文なので、他を当たるか、丁度アムステルダムに居住する琵琶の名手上田純子さんの古典琵琶ソロリサイタルが良いのではないかと提案した。
ついでに琵琶曲が日本で作曲された時代に合わせて、16世紀前後のイタリアでベネチア楽派のジョヴァンニ・ガブリエーリが作曲したチェロ無伴奏曲を弾いて聴き比べたら面白いのではないかと便乗提案もしてみた。別に音楽的内容に強いモチベーションがあったわけではなく、どうしても一度は行ってみたかったのだのだ、シチリア島に。
 |
(画像:Giovanni Gabrieli by Annibale Carracci, via Wikimedia Commons license) |
私はゴッドファーザーが大好きで何度も見たが、とりわけ舞台をニューヨークからシチリア島に移したパートIIIがたまらなく好きだった。パレルモのオペラ劇場での惨劇、そしてあの胸をかきむしる素晴らしい「愛のテーマ」。その歌を、シチリア民謡だとされる設定で語り弾きするシーン。これを初めて聞いたときはあまりの切なさに涙が止まらなくなった。それほど好きなのだ。
結局提案は受け入れられ「では一体幾らお払いすればよいのでしょうか? 」という事になった。もちろんチェロを含む2枚の航空チケットと滞在費全ては別で。わたしは多額のお金が用意してあるのだろうと感じていたので思い切って数倍にレバリッジを掛けてみる事にした。だめもとのつもりで「じゃ、X千ドルでなら、まあ行ってもいいかな? 」すると一瞬相手が絶句して黙り込んでしまった。「しまった、はったりを利かせ過ぎたのだ、コリャ直ぐ損切りだ。どうしよう。」
しばらくして口を開いた相手の答えはこうだった「Oh, really? Are you sure? 本当にそんな少ない額で良いのですか? 」
私のシチリア島への旅は、明らかに何かがオカシク始まったのだ。そして最後までオカシイ旅になる。そもそもなんで私のところにこの様な話が舞い込んで来たのか? 日本大使館にでも聞けば良いのに何故なのだろう?
古都シラクーザ
シラクーザは他のイタリア諸都市とは全く違う異国情緒に包まれた港町だった。それはこのシチリア島が古代からギリシャの植民地を経てローマ帝国、フランス、スペイン、そしてアラブ人にまで支配されてきた歴史そのものを町の建物が物語っているからだった。波乱に富んだ地中海文明の歴史そのものを血として引き継いできた人々は独特の風貌をしており、この町では時折息を呑むほど美しい女性や男性とすれ違うことがある。
 |
(画像:アラブ人が描いたシチリア島地図、wikipedia commonsより引用) |
シラクーザ最初の印象は到着してホテルで最初に食べたスパゲッティだった。それはニンニクとオリーブオイルだけで味付けしたとても黄色い硬いスパゲッティで、刻み唐辛子を僅かに振り掛けてあった。生まれて初めて食べたアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノだった。私はスパゲッティが大好きで週に1、2度は食べるのだが、トマト味のスパゲッティしか知らない。オリーブオイルだけでこんなに美味しいスパゲッティが食べられるのだと感心した。
 |
(画像:コッポラ鳥打帽氏、By Nicola Di Maria licensed under the Wikipedia Creative Commons license.) |
シラクーザの町並みと人々を素晴らしいカメラで収めた映画がある。ジョゼッペ・トルナトーレ監督の「マレーナ」がそれだ。トルナトーレ監督は「ニュー・シネマ・パラダイス」でも有名だが、こちらもシチリア島で過ごした少年時代の初恋を回顧した映画で、エンリオ・モリコーネが作曲したテーマソングが胸をかきむしる。誰しも心の中に永遠に潜み続ける少年時代の初恋への哀愁と郷愁を切なく描き切った名作だ。映画に出てくるほとんど全ての男性がコッポラと呼ばれるシチリア独特の鳥打帽氏をかぶっている。
 |
(画像:Monica Bellucci, Photo by Manfred Werner, Wikipedia GNU Free Documentation License) |
何度かイタリアを訪れた結果、私の心にはイタリア人女性は美しいというイメージが定着してしまったが、シラクーザの女性は並外れて美しかった。私が今までに遭遇した最高の美人は演奏会が開かれた古代劇場の近くの田舎町、あの街角のジェラート(アイスクリーム)屋で見かけたあの若い娘さんだった。ほんの1分ほどの無言の出会いだったが不思議といまだに忘れる事が無い。
そのイメージを私はお伝えする筆力を持たないが、映画「マレーナ」を見ていただけると幾分かでもそれが分かっていただけるかもしれない。イタリアの宝石、女優モニカ・ベルッチが主演している。
ゴッドファーザー
演奏会が終わった夜は、近くの田舎町で打ち上げの夜食会だった。地中海沿いの国では、コンサートは真っ暗になってから始まり夜遅く終わる。その後演奏家たちはレストランに向かい深夜零時頃まで飲み食いするのである。イタリアではそれを「マンジャーレ」と呼びそれがまた楽しい。
洞窟を利用して作ったような変な内装のレストランで夜食会が始まった。入れ替わり立ち代り誰かが入って来ては挨拶を交わし、親しい知り合い同士で飲み食いに興じている様子だった。思い出したように私に握手を求めてくる人もいたが、おおむね主客であるはずの私を全く意識していないことは明らかだった。
 |
(画像:夜食会、筆者撮影) |
ふとゴッドファーザーに何度も出てくる会食の場面を思い出し、それとなく主催者側に切り出してみた。これは最初から最も気になっていたことだったのだが、どうしても聞く機会が無かったのだ。今を逃したら聞くチャンスは無くなる。
「ところでシチリアと言えば、思い出すのはゴッドファーザーですよね。僕はあの映画が大好きで何度も見ましたが、こんな風に皆が集って食事をする場面が何度も出てきますね。私は特にシチリア島を舞台にした第III部がいいと思うのですが、あなたはどう思いますか?」
この企画そのものの有り様といい、無駄な出費ともいえる大げさな舞台仕掛けやフランク・シナトラ・ショーの話といい、これは我々が知っているような仕組みで出来ている演奏会のあり方とはあまりにも違う。
主催者の代理として私について回っている世話人は「ははは」と笑って応えた。それまで私のことをわざとらしく「マエストロ」と呼んでいたのに、突然「マイ・フレンド」と言って私の目をじっと見た。その目が一瞬ギラリと輝いたように思えた。そして今度はパチッとウインクしてまた「ハハハ」と笑って肩を軽くイタリア式にすくめたのだ。「明日のランチはとても面白いところにお連れしますよ。楽しみにしてください」。そして私にはそっぽを向いて夜食会の参加者と話しに興じ始めた。
マフィア
当時のシチリア島では公共事業下請けのほとんどがマフィアに独占的に支配されていたらしい。時には警察権までもが下請けに出された時期があったといわれる。行政権力よりも地元のボスの方が組織力があったと言う事なのだろう。この島では2千年近く入れ替わり立ち代り権力者が島外からやって来て島民を支配してきた為に権力に対する不信感と抵抗が強く、国家や行政が逆にここではうまく機能しないという歴史がある。そういう事情でマフィアが当初は一種の自己防衛組織として生まれ、行政からもその組織力を利用されたという歴史があるらしい。文化行政予算の一部がこういう下請け組織に流れている構図は容易に想像できることだった。
古代劇場の会場設定を行っていた巨大トラックと多くの作業員。夜食会のなんとなくしっくりこない内輪の集まりのような雰囲気。マフィアとの関係は公然の秘密とされるフランク・シナトラ招聘の話。これは大変な相手に招待されたものだ。
ジェラート(イタリア風アイスクリーム)
翌日主催者側の人が「ランチに面白いところ」を案内してくれた。それは一見マクドナルド風ハンバーグを立ち食いする店のようで、田舎町の若い男女たちがかなり沢山たむろしていた。何を食べているのだろうと思ってよく見てみるとそれは緑や赤や白のハンバーグならぬアイスクリームだった。それを丸パンに挟んでマック風に食べているのだ。
これには驚いた。確かにイタリアン・アイスは欧州中に名をとどろかせるほど美味しく、例えば私も夏場になるとわざわざ隣町ユトレヒトの有名なアイスクリーム店まで家族で食べに行く。オランダの至る所で、イタリアや、もしくはイタリア系スイスから夏場だけアイスクリームを売りに来る専門の職人が店を開くのである。ジェラートと呼ばれるこの氷菓子はローマ時代に遡って皇帝クラスの人々に食べられていたらしい。2000年にわたってシンプルな味を磨き上げてきた。
シチリアのこの町ではこのアイスサンドを豪快に一気に沢山食べる男が一番男らしく、女の子にもてるそうだ。では私ならこの島でもてるチャンスは十分有りそうだ。氷菓子とマフィアのイメージとは相性が悪く、シチリアを巧みに描き切ったコッポラ監督のゴッドファーザーにもさすがにこの話は出てこない。殺戮場面の後で、殺人者がジェラートを上手そうに頬張る場面が、狙い通り成功するかどうか自信はもてないだろう。わたしならそれを試みてみたい。
その店の片隅に驚くほど綺麗な年頃の娘さんがアイスを買いに来ていた。傍にはまるまると太った戦車の様に強そうなおばさんがピタリとくっついて誰をも寄せ付けない怖い顔をしていた。珍しい東洋の客人を見て向こうも一瞬視線が私に釘付けになった様子だった。(もしくは私がそう思い込んだだけなのかもしれないが)。
あの美しい人は今頃あのお母さんと同じになっているのだろうか? 欧州で私が学んだ知恵によると間違いなくそうなっているに違いない。そうだとしたら何と言う儚い(はかない)美しさなのだろう。
 |
(画像:シチリア島山間部。シラクーザから車で数時間通り抜けると、ギリシャの古代劇場遺跡にたどり着く。Photo by Giampaolo Macorig, Creative Commons Attribution-Share Alike license) |
この続きは数週間後、間奏曲(4)その2:神々が住む山、ギリシャのデルファイ神殿での演奏会
田中雅氏のプロフィールはこちら