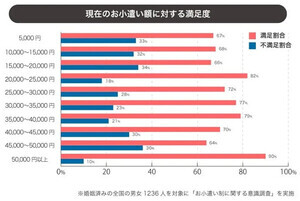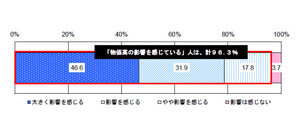取引者としての成長過程
個体の進化の過程は、しばしば種の進化の過程をたどると言われている。これは、われわれ市場参加者の進歩の過程についても言えるようだ。ある人が相場の参加者として上達していく過程を追ってみると、そこには個性的取引スタイルの発達だけではなく、相場人類が歴史的にたどってきた共通の進化過程を反復する傾向があることが分かる。
そこで古典的取引手法の歴史を回顧してみたい。現在生き残っている古典的取引手法は、先人がわれわれに残してくれた貴重な遺産であり、歴史というフィルターに掛けられた知識のカンヅメでもある。一見かび臭い古臭いのは表面だけで、その内面は賞味期限が切れているわけではない。
取引手法と分析手法
その前に取引手法と分析手法とをはっきりと区別しなければならない。取引手法とは、売り買いの注文に直結する決断を、単純明解に導き出すルールのことである。一方、分析手法とは、必ずしも売り買いの決断を導くとは限らず、分析した参考意見を述べることである。取引ルールと言うからにはそこから注文が即座に引き出せるものでなければ意味が無い。
相場のように複雑怪奇な現象を観察すると、それに対処するルールも曖昧で複雑なものになりやすい。これは相場という分かりにくいものに接して、われわれが困惑しきった挙げ句の果てに選択する、非常に自然な反応であるとも言えよう。
この複雑な現象を単純明快に認識し、表現するというのは実に困難な作業であり、あらゆる科学技術や芸術の極意であると言ってもよいが、相場も同じことである。
最も易しいシステマチックな取引手法
ポピュラーな相場分析指数のほとんどは分析手法であって取引手法ではない。これらは「参考」にするための指数ではあっても、直ちにそこから取引注文を発注できる第一次的原理とはなり得ないのである。
さて、もっとも易しい機械的、システマチックな取引手法とは何だろうか?それは「順張り」のブレークアウト取引である。これは「トレンド・フォロー」の一種である。相場の天井や底を予測してポジションを取るのではなく、要するに相場が動こうとしている方向に自分も自動的に、機械的について行く。文字通りトレンド(傾向)にフォローする手法である。この逆をする場合は「逆張り」と言う。
ブレークアウト
順張り(トレンド・フォロー)の取引手法はさまざまなものが開発されてきたが、歴史的には「抜け幅を定めて、そこからのブレークアウトについていくやり方」が最初のもので、後に卓上計算機やコンピュータの出現で複雑な可変バンドや可変チャンネルを抜け幅とするように変遷していった。
ブレークアウトとは、相場がある値幅分動いたときに、新しいトレンドが発生(Break Out)したとしてポジションを取る手法で、古くは本邦のカギ足、新値足、米国のポイント・アンド・フィギュアなどがその概念を使用している。
我が国の順張り取引手法
 |
(画像 : 大阪堂島米会所) |
トレンド・フォローというといかにも米国あたりで考案された手法であるかのように聞こえるが、恐らく我が国がその本家本元である。これは日本には江戸時代から米相場のような先物市場が発達していたためで、もしも、古代ギリシャに先物市場があったなら、ギリシャ人はやはりトレンド・フォローの手法をあみ出していたであろう。要するに人間が相場に接して必死になって考え出した取引手法は古今東西共通しているということである。
(と10年前の初連載では書いたのだが、実はギリシャ人は恐らくトレンド・フォローの手法を決して編み出すはずが無かった。というのもギリシャ人は「未来は既に運命として決まっており、それは分析の対象ではなく、占いの対象だ」と考えていたからである。「取引手法は古今東西共通する」という考えは正しくないと思われる。この事を筆者はリーマンショックの直後に強く意識した。詳しくは別途「間奏曲」として触れる事にする。)
世界の最先端を走っていた江戸時代の日本
古来わが国はローソク足のような優れた分析手法を産み出してきたが、それだけでは無く、「取引手法」に関しても、歴史的に世界の最先端を走っていたようだ。
それらの取引手法とはカギ足、練行足、新値足等である。便宜上これらを古典的罫線と呼ぶことにする。ちなみに、古典的罫線でもっとも有名なローソク足はパターン認識の手法であり、必ずしも明確な売買のルールではない。それでも世界中で受け入れられ市民権を獲得したのは何故だろうか?人は(特に東洋人は)必ずしも完璧で単純明快なルールを好むのではなく、ある程度の曖昧さを好むという性向があるのかもしれない。特に相場のような限りなく曖昧な世界では、はっきりさせないことの方が、はるかに居心地が良く、現実に即しているとも言えるのだ。
 |
(画像 : 上 : バーチャート、下 : カギ足(鈎足) : かぎかっこの連続のような形のチャート。価格変動が生じた時点で線が折れ曲がるという非時系列チャート。非時系列という驚くべき概念を導入してあるのが特色。トレードシグナルにて作成) |
日本の古典的罫線
わが国の古典的罫線はチャンネル・ブレークアウトに分類できる。すなわち一定の転換幅を設定し、何らかのルールで陽転と陰転を判定し、陽線もしくは陰線で表現する。陽転が買いシグナルを表し、陰転が売りシグナルとなる。
三段新値足
三段新値足は直前の過去のボラティリティーを新値三段というレンジで表現することから、さらに進化したボラティリティー・ブレークアウトの原形とも言える。
 |
(画像 : 新値三段足=新値三本足。新値足の変化型。陽転、陰転する際に、「直近の3本を抜いたとき」という条件をつける。五段新値足なら、直近の5本を抜いたときにトレンドの転換と見る。トレードシグナルにて作成) |
これらの古典的罫線は試してみた方も多いはずである。詳しくその取引能力を検証した結果、儲からないという結論に達したことがあるかもしれない。
取引手法の本質に迫る
しかしここで結論を早まってはいけない。これらの手法が考え出された時代には、計算機もコンピュータも無かった。筆算かせいぜいソロバンが計算の手段だった時代である。手法といっても単純で、一見原始的にその根本概念だけがプレゼンテーションされているものが多い。しかしもしかすると肝心要の本質だけはしっかりと把握していたのかもしれないのだ。
究極の取引手法を探し求めてあれこれ試した挙げ句、原始的な概念や着目点の重大さに気付いて、また元からの再出発となることは何度もある。それほど「事の本質が重要」なのである。そうならば歴史を探るのが一番である。「事の本質を探り当てた」古今の熟練者が残してくれたもの、それが古典的知恵であり、究極の取引手法の本質を学ぶことが出来るからだ。
筆者は2007年度に機会を得て幾つかの古典罫線の基本形を、為替市場の時間足に適用して徹底的に調べたところ、罫線取引で素晴らしい成績を上げることを発見した。人があまり試したことの無い未知の分野において、古典的原理は非常に有効である。問題は同じやり方で使い古されたことにあるのであって、原理そのものが間違っているわけではないのだ。時間足に適用するような、新鮮な使い方をすれば素晴らしい成果を上げてくれる。
 |
 |
|
(右画像 : 練行足の記録方法) / (左画像 : 練行足:非時系列チャート。上下いずれもトレンドが発生した際に、一定の値幅分で改行して追加して行く。練り歩く行列からの命名、乃至は、あたかもレンガを積んだように見えることから、この名がついたとも言われる。トレードシグナルにて作成) |
|
時間の認識
我が国の古典的罫線は、顕著な特色を持っている。足を描く際に「時間の流れ」を無視して、一定の値幅を超す動きだけを、ある一定のルールに従って記録する点である。このアプローチは時系列分析手法と根本的に異なる。欧米では時間枠の尺度を厳密に規定し、その枠組みの中で値動きを詳細に記録し観察しようと試みるのが普通である。
日本の文化と科学芸術を調べて見ると「時間の流れ」を厳密に計測して見たいという意欲そのものが感じられない。そのような歴史的痕跡がほとんど無い。仮にリンゴの実が木から落ちたときに、それを見て日本人が成し得る人類への最大の貢献は、天体の運行と万有引力の法則に思いを馳せることではなかった。誰もそんな狂気の沙汰を望まなかったのだ。正岡子規ならそのリンゴを拾って食べたに違いない。そこで丁度、法隆寺の鐘さえ鳴ってくれれば、日本人はそれ以降数百年間その心象風景を国民的な規模で繰り返し楽しむことが出来た。
西欧の一時間に相当する江戸時代の一時(いっとき)とは、毎日伸縮する可変時間だった。夏と冬とでは一時の長さは異なっていた。それで良かったのだ。
時間の芸術
 |
(画像 : 「日本古典音楽の記譜法」小節という尺度が存在しない。筆者撮影:奏者 ドイツ生まれの次男田中研) |
これは時間の芸術とも言われる音楽でもそうであり、日本の伝統音楽には小節やリズムといった時間分割のコンセプトは全く発達しなかった。発達しなかったので、西洋音楽に比べて未開なのだという先入観を筆者は持ち続けていたが、その偏見が崩壊したのがインドネシアでガムラン音楽に接した時のことである。
ガムラン音楽の無時間手法
ガムラン音楽はオーケストラに匹敵するほど複雑で、奇怪なほどに精緻な音響芸術であるが、時間をコントロールするのに無時間と言う手ぶら手法で立ち向かっている。要するに楽譜という時系列で制御された精密な青写真を必要としない。複雑極まりない音響の曼荼羅を、多数の音楽家が共同で構築しているのに、音の長さを尺度で計量し合意すること無しに、それが可能なのだ。これは数百人の建築家と作業員がメートル尺を一切使わないでエッフェル塔を建設するほどの偉業といえる。
アジア伝統音楽の時空認識
日本だけではなく、アジアの伝統音楽は西欧風に理解すると時空の無制御で成り立っているのが普通である。これはアジアの音楽が時空を制御できないほど「未開」であることを意味するのではない。時空の認識方法が根本的に違うのである。これは相場を考える上でも恐ろしく魅惑的な考え方である。本掲載ではカオス理論について時折述べているが、アジア音楽の時空認識との共通接点を見出すことが出来る。
 |
(画像 : バリ島ガムラン合奏団、楽譜を必要としない。http://en.wikipedia.org/wiki /File:Javanese_Gamelan.jpg) |
欧米の時空認識
一方西欧では、時間の経過を決定的に重要な要素として分析し、時系列情報を徹底的に使用し尽す取引手法が主流である。時間の流れを無視するのはポイント・アンド・フィギュアだけである。西欧の取引手法では、価格変動だけではなくその時間の推移を正確に計測し分析したものが市場ではより有利な立場に立てると考えている。米国の現代取引手法の代表格と言える「ボラティリティー・ブレークアウト」の手法はもちろんの事、現代的金融工学では、時間の経過をありとあらゆる側面から計算しつくす高度な技術が発達している。
この「時間の計測」という問題は、考えれば考えるほど肝心かなめ、事の本質であったので、筆者を過去26年間悩まし続けた最大の問題の一つだったが、それについては最終章「テクニヘッジ・システムの基本原理」にまとめてある。
米国の順張り手法
(画像 : マーケットの魔術師 : ジャック・D. シュワッガー著 / 提供 : パンローリング社)
移動平均線
さて、太平洋の向こう側、近代の米国では、トレンドラインが考案されたが、その可変的数値バージョンとも言える移動平均線をグランヴィルが考案して以来、これが最も初期的なトレンド・フォロー手法となった。平均することの目的は相場の細かい動きをノイズとして濾過してしまうことにある。この頃の移動平均線の詳しい使用実例は「マーケットの魔術師」という著名な書物の中に生き生きと描かれている。大変に儲かったそうだ。是非参照していただきたい。
コマ足
平均という考えは計算を好まない本邦の古典罫線では使われなかったが、近代日本のコマ足という手法に応用されている。コマ足と移動平均線とどちらが先に開発されたのかは知らないが、近代の市場分析取引術の発展においては、日本人と米国人とがお互いを知らずして先駆的業績を競っていたようだ。
(画像 : ドル円コマ足。平均足とも呼ばれ、ろうそく足の一つ一つが過去数本のろうそく足平均を表す。コマに似た形になりやすい。トレードシグナルにて作成)
練行足の米国版 ポイント・アンド・フィギュア
もう一つ見逃してならないのが、前述のポイント・アンド・フィギュアの手法である。これは日本古来の手法の基礎をなしている転換幅の認識を原理としていることから、練行足の米国版であると言ってよいだろう。
そしてコンピュータが一般化するに連れて、比較的複雑な計算を必要とするボラティリティー・ブレークアウトが最新のテクニックとして登場してきた。このボラティリティーが何を意味するのかは、次章以降で詳しく取り扱っている。
(画像 : ポイント・アンド・フィギュア:欧米で古くから使われている。トレンド系チャート。日本のカギ足、練行足、新値足と類似している。トレードシグナルにて作成)
最後にアンチ・トレンド・フォローの取引手法、すなわち、逆張りについても考えてみたい。この手法は、トレンド・フォローの明らかで宿命的な欠点に着目し、その逆をいくもので、トレンド・フォローの反世界と考えて良い。これはボラティリティー・ブレークアウトを詳説した後に手短に取り上げる予定である。
順張り手法実例
さてここで順張りの取引概念を注文の実例から垣間見てみよう。
次に示すのは、ある仮想ドル円短期取引システムの注文である。
ここでは仮に取引量を1本(百万米ドル)と定める。
単純に買いの注文だけを取り上げる。
Buy new 1 USDJPY at 111.00 stop, day order. If done, sell 1 at 109.00 stop GTC.
新規買い:ドル円を1ミリオンドル、本日限り、逆指値111円00銭新規買い。
成立したら、109円00銭に、1ミリオンドル、キャンセルするまで有効な逆指値仕切り売りを入れる。
この注文は前日ニューヨーク市場がひけた後で、ディーリング銀行にファックスまたは口頭で伝えられる。
現代の証拠金為替取引であればマウスとキーボードを使って注文画面に簡単に直接打ち込むことが出来る。
この注文は、 翌日のオセアニア市場からニューヨーク市場までの約24時間足らずの間有効である。
その間、筆者は必ずしも相場を見ている必要は無い。市場で何が起きているのか全く知らなくても構わない。注文がその日中にすべき事をあらかじめ全て指示してあるからだ。このようにあらかじめ全てを指定出来るのが、システム取引の特徴である。市場に拘束されないのでこれは大変な魅力といえる。
この注文が指定していることはドル円が上昇して111円に到達したら買うこと。
もし成立したら損切りの注文を109円に入れてここまで下がったら損を確定して売ること。
仮に前日のNY市場の引け値が110円丁度であったとすると、1円上昇したら買い。引け値から1円下落した水準では売って損失確定、という注文になる。
この1円幅を「抜け幅」と呼ぶ。昨日の引け値に比べて、上方の1円以下の動きは無視せよ、下方の1円以下の動きは、やはり無視せよと言う意味である。これらの「抜け幅」を相場の値動きが超した(=ブレークアウト)ときにのみ取引行動を起こせと司令している。
この抜け幅を決めるのにボラティリティーという概念を使って計算を行うので、この手法はボラティリティー・ブレークアウトと呼ばれる。
古来、トレンド・フォローの手法にはさまざまな変形が考え出されたが、それらは皆、共通の大原則に従っている。値段がある程度上がったら買う、ある程度下がったら売るという原則である。高値を買い、安値を売るのである。
(画像 : 筆者作成のボラティリティー・チャンネル・ブレークアウト取引システム。売買チャンネル例)
順張りの問題点
ポジションを自動的に取る
高値を買い、安値を売るのでは、商売の原則に反しているので損をするのではないかと思われるが、まさしくその通り、この手法は相場が保ち合い(=もちあい)ないしは乱高下になると損になる。何故そんな変な注文をあえてするかというと、こうしておくと上昇トレンドが発生したときは100%の確率で「買いポジションを自動的に取ることが出来る」からである。ポジションを取り損ねるということは無い。曖昧な予想屋が一番嫌うのがこの手法である。この手法の根本原理は単純明快である。即ち「ポジションを持たない限り、如何に優れた市場予想も理論も絵に描いた餅で、何の役にも立たない」ということだ。
ブレークアウト手法の長所
とはいえ順張り手法の欠点を克服する何らかの改良が必要となってくるが、順張り手法の中でもブレークアウトの手法は「短所が非常に単純明解」なので改良がしやすいという大きな長所がある。
この手法で成功する秘訣は、次の三つに要約されるだろう。
- 保ち合いや乱高下の少ない、トレンドやブレークアウトが発生しやすい市場を取引する。
- 保ち合いと乱高下を感知してそれを避けて取引するような工夫をする。
- 損切り、ブレークイーブン確保、利食いなどの手法をシステマチックに導入し、トレンド・フォロー順張りの欠点を補う工夫をする。
トレンドを有する市場を発見する
さて、(1)のトレンドを有する市場を取引するということであるが、トレンドを発見するのは実は簡単では無い。しかし筆者の経験ではトレンドを有する良いマーケットとは、意外なことに先進国ではなく新興国の有る程度未熟な市場に多く発見される。未熟な市場をいかにして発見するかであるが、第一に手数料が高く権威によって保護されており、第二に規制が厳しくて自由度が小さく、第三に情報が公平には共有されていないようであれば十分である。つまり先進国にあと5~10年で仲間入りするような急伸中の状況であれば申し分の無い結果となるだろう。
シカゴ先物市場
筆者が1980年代から90年代に最も得意としたドル円取引は、80年代 当時は世界最大の投機市場がシカゴ先物市場だった。インターバンク市場が拡大したのはそのかなり後の事である。しかもポーク・ベリー(豚あばら肉)ピットの横で、始めは彼らの片手間に取引されており、そこが世界最大だった。考えても頂きたい。80年代の欧州では「君は何処から来たのかね?」と聞かれると「 東京です」と答える。すると「ああ中国から来たのかね、遠くからようこそ」と挨拶された時代である。筆者はシカゴ市場で一番トレンド特性の強い商品としてドル円を特定し、これを好んで取引していた。豚肉の隣とは正にトレンド発生の条件を完璧に備えた理想的環境(=未熟な市場)だったというわけだ。
(画像 : シカゴ・ボード・オブ・トレード / 出典 / http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chicago_bot.jpg)
その逆に、世界で最も成熟した先物市場は恐らくシカゴで取引されるS&P500株価数先物であるが、非常に優れたシステム取引者でも、ここで勝つのは難しいと感じるだろう。一般に市場は成熟すればするほど、予測不可能のランダム運動が顕著になり、順張りブレークアウトのシステム取引が難しくなる。そして最も成熟した取引形態がネット取引であることを考えると、世界最大のインターバンク市場にネット取引で参入するのはそれほど簡単なものでは無いと言うことも察しが付く。そこは非常に効率的で、自由で、公平な競争世界であり、従って取引者には一番怖い場所でもあるのだ。
フィルター
(2)の保ち合いや乱高下局面を避ける手法であるが、普通「フィルター」という手法を使う。トレンド・フォローの手法を使って取引する上で、成功するための鍵となるのがこれである。「フィルター」とは取引したくない市況の条件を定めて、その条件に合致する局面では取引を避けるシステム上の工夫である。通常は過大なボラティリティーや過小なボラティリティーを感知すると新規取引を停止するように設計するが、実に多様なフィルターが考案された。
(3)の損切り、利食いの手法については重要なので第4部以降に独立した章を設けて詳説する。
田中雅氏のプロフィールはこちら