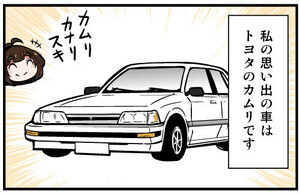ハイエンドなヒストリックカーのミーティング・イベントともなれば、集まる車のクオリティが高いのみならず、エクスクルーシブな耳より情報が発信され、華やかな社交サロンの場としても機能する。その意味で、第10回の記念開催となるオートモビル カウンシル2025において、日本市場におけるインポーター勢の中でも、マセラティ ジャパンのプレスカンファレンスはことさら重要なものだった。同社の木村隆之社長が、2021年からスタートして今のところイタリア本国でのみ行われているという、過去のマセラティ車のクラシケ認定の審査を、日本のマセラティ・オーナー向けに開始すると述べたのだ。
【画像】オートモビル カウンシルの会場に展示された1969年マセラティ・ギブリ・スパイダー(写真39点)
マセラティ・クラシケのプログラムは無論、ヒストリックかつクラシックなマセラティ車両の修復保存を促し、正統性を未来に向けて認証することを旨としている。検証と審査を通じて、マセラティ本社の担当者から認定の下りた車両には「認定証」が発行され、スペアパーツの再生産や車両レストアのサポートといったサービスが受けられやすくなる。
じつはこれはイタリア本国以外では初となる試みで、そもそもなぜ日本でスタートさせたのか? 木村社長に問うてみた。
「それはシンプルに、自分がやりたかったからです(笑)。ギブリⅡ、1988年式のちょっと古いマセラティに自分でも乗りながら、じつはマセラティ・クラブ・オブ・ジャパンにも入会していますから。これまで販売したマセラティ車の残存台数でいうと、日本はアメリカや中国、イタリアの次ぐらい。つまり1980年代以降のガンディーニ・デザインのマセラティ中心ながら、世界で4番目にマセラティが多く残されている国なんです。現行モデルでも、じつはMC20がアメリカの次に売れているのは日本ですし、イタリアや欧州以外で始めるなら日本しかないと本国にずっと働きかけてきました」
対象となる車両は大別して3カテゴリーある。まず1947年~1978年までを生産年とし、古典的なマセラティGTも対象となる「クラシック」。次いで1978年以降で生産後20年以上を経過した「ネオクラシック」が挙げられ、日本で1980年代辺りから人気を集めたビトゥルボ系や一連の222、ギブリⅡやシャマル、3200GTなどはここに含まれる。そして3つ目はMC12やその派生車種、320Sといった歴代の「スペシャルカー」と呼ばれるカテゴリーだ。今回のオートモビル カウンシルで展示された1969年式ギブリ・スパイダーのような、ジウジアーロの手によるデザインにして125台のみがデリバリーされたという希少な車種は、無論「クラシック」の候補といえるだろう。
マセラティ・クラシケがもうひとつ”新しい”理由は、イタリア本社から認定担当者が審査にやって来ること。つまりマセラティのオーナーは、日本に車両をとどめながらにしてクラシケ認定にトライできる。
「イタリア本国への輸送や運送手続きは欠かせないことのようですが、コスト面でも手間の上でもオーナーに大きな負担、ストレスにもなりますから。それらが省かれるよう、本国からクラシケ認定の担当者を来日させることで、検査から認定までのプロセスを可能にしました」
審査を希望するオーナーは6月1日から30日までの1カ月間に、マセラティ・ジャパンの公式サイト上で登録する必要があるが、初年度となる2025年は最大8台に対して審査の扉が開かれる。
「担当者を来日させる分、時間が限られているからこそ、まずは8台という上限枠を設定しました。正直、少ないかな?とも思いました。我々が何か、イベントごとのために100~200台といった規模で集まってもらいたい時も、いつも半分ぐらいはすぐにクラブの方々の参加で埋めてくれますし、さらに半分以上が新車のマセラティも購入してくれていますから。それだけ日本のマセラティ・オーナーのロイヤリティは高くて、情熱的なのです。メカニックにもガレージ伊太利屋時代からずっとマセラティひと筋といった人材もいますし、実際にマセラティ ジャパンのアフターセールスからは3名が常設のチームとしてクラシケ担当にあたり、クラシケ認定を目指すオーナー様の修理メンテナンスをフォローします」
これまで旧車乗りの間では、修理が難しいとか手強いといった先入観をもたれていた旧いマセラティだが、クラシックもしくはネオクラシックとして価値が安定することで、中古相場も一定以上の上昇があるかもしれない。ただ木村社長の狙いはそれ以上に、ブランドとしての信頼感を揺るぎなく確かなものにしつつ、それと並行してニューモデルを提案していくという青地図が見える。日本市場での地歩を固めつつあるマセラティの動向は、これからも注視していく価値がある。
文:南陽一浩 写真:南陽一浩、マセラティ ジャパン
Words: Kazuhiro NANYO Photography: Kazuhiro NANYO, Maserati