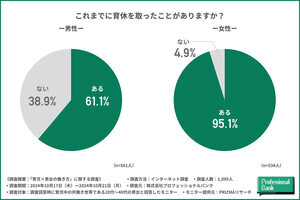OKANは3月25日、「小1の壁」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年2月21日~2月25日、小学校低学年の子どもを持つ働く女性515名を対象にインターネットで行われた。
「小1の壁」認知度は84.7%
子どもの小学校入学を期に仕事と育児の両立が難しくなることを指す「小1の壁」という言葉を「知っている」と回答した人は84.7%で、「小1の壁」という言葉は小学生の子どもを持つ働く女性の間で広く認知されていることがわかる。
小学校入学を機に「仕事と育児の両立が難しくなったと感じたことがある」と回答した人は64.5%で、働く女性の過半数が「小1の壁」を感じたことがあることが明らかになった。
「小1の壁」を感じた時期として最も多かったのは「入学直後」で56.0%、次いで「1年生の夏休み前後」が20.8%、「入学前」が19.9%と、入学前後~夏休みまでの数ヶ月間で困難を感じていることがわかった。平日の小学校と仕事の生活リズムの違いや、夏休みなどの長期休暇によって仕事と育児の両立が難しくなることが示唆されており、企業が柔軟な働き方の推進を検討する場合はこれらの時期に合わせた支援策も重要であると考えられる。
勤務先の制度や支援について
勤務先の制度や支援の有無については、多くの項目で「制度・支援が存在しなかった」と回答した人の割合が高い傾向にある。特に、「テレワークの導入」「保育施設の設置運営」「育児や育児と仕事の両立に関するセミナー」「子連れ出社の実施」「メンタルヘルスの支援制度」は60%を超える人が「制度・支援が存在しなかった」と回答している。一方で、3歳に満たない子を養育する労働者に対しては設置が義務化されている「短時間勤務制度」は、制度の存在を認知している割合が高くなっている。
制度・支援が存在する場合の利用率を見ると、「子連れ出社の実施」が最も高く74.1%、「テレワークの導入」が60.4%と続いている。一方、「育児や育児と仕事の両立に関するセミナー」「メンタルヘルスの支援制度」などは利用率が低い傾向にある。
前問で「制度・支援は存在していたが、利用していない」と回答した人に、利用していない理由を尋ねたところ、「育児支援に関する情報提供」「育児サービスの費用助成」など、情報提供や経済的支援に関する制度では「制度についてよく知らなかったため」という理由が比較的多く、制度の周知不足が課題として考えられる。
また、「公的な制度を上回る子の看護休暇」「テレワークの導入」「メンタルヘルスの支援制度」は、「制度が必要ではなかった」以外で「利用したいと言いづらい雰囲気・人間関係だったため」を理由に制度を利用していない人が最も多いことがわかった。
2025年4月から改正育児・介護休業法の施行によって、企業による育児と仕事との両立支援の強化や制度の拡大が見込まれるが、企業側は制度や支援の設置だけではなく、従業員が安心して利用できるよう、わかりやすい説明やオープンで柔軟な職場環境づくりを目指することも求められる。
「小1の壁」の要因
-

職場において、子どもの小学校入学後の育児と仕事との両立を妨げる要因だと感じるものを全て選んでください/子どもの小学校入学後の育児と仕事との両立を妨げる以下の要因のうち、最も課題だと感じるものを選んでください
子どもの小学校入学後の育児と仕事との両立を妨げる要因については、最も多かった回答は「柔軟な働き方が選択できないこと」で、次いで「休暇が取得しづらいこと」となった。「適切な情報を入手できないこと」は回答割合が低いものの、複数回答で19.2%と、働く女性の約5分の1が、情報不足が育児と仕事との両立を妨げる要因だと感じていることがわかる。
前問で「周囲の理解が得られないこと」を最も課題だと回答した人に、どのような理解が欲しいか尋ねたところ、「子供が体調を崩しやすいことを理解してもらう」「年生は給食が始まるのも遅く、下校が早いため、入学直後は特にやむを得ず時短勤務などにすることを理解してほしい」「意外と小学校は帰宅時間が早かったり、保護者の出番が多いという小学生生活の内容が理解されるといい」といった回答が寄せられた。職場全体で育児に関する知識や理解を深めることを求めているという状況が明らかになった。
「小1の壁」に有効な施策について
仕事と育児との両立に関わる制度のうち「小1の壁」に有効だと感じる施策を1位から5位まで選択してもらい、加重平均により順位づけしたところ、休暇制度や柔軟な働き方に関する施策が上位に挙がった。
休暇制度や柔軟な働き方に次ぐ7位には「制度を利用したいと言いやすい雰囲気・人間関係」が挙げられている。適切な情報の入手に関わる施策の順位は低くなっているが、約1割の人が有効な施策の上位5位以内に選択しており、軽視することはできない。
さらに、前問の選択肢以外で「小1の壁」に有効だと感じる施策を尋ねたところ、以下のような回答が得られた。
休暇に関する制度や支援
休暇に関する制度や支援については、「夏休み期間に合わせた休暇」「子供の熱など証明があれば、有給のような扱いになる制度」という回答が寄せられた。さらに、「子供の体調不良や行事で休むことを、申し訳ない…という気持ちではなく、当たり前にできる社会になってほしい」という要望も挙げられた。
柔軟な働き方に関する制度や支援
柔軟な働き方に関する制度や支援については、「教員や保育士、介護士などの対人関係の仕事でも、月に何日かは在宅勤務ができるなど、柔軟な働き方ができるような人員配置」を求める声があった。また、「4月はリモートや、短時間勤務、または休職するくらいして慣れるまでのんびり働いていいようにして欲しい」という声も寄せられた。加えて、「例えば1ヶ月だけの時短やフレックス等、年単位で設定するのではなく月単位で勤務内容を選択出来るような制度や、時間有給(有給を時間単位で取れる)」という意見もあった。
預け先の確保に関する制度や支援
預け先の確保に関する制度や支援については、「放課後、始業前の子どもの居場所」や「どうしても休めない時の子連れ出社」を求める声が寄せられた。また、「保護者が参加する授業の時だけ、中抜けができたり、子供の下校後に利用できる学童保育が職場にあれば負担が減るのではないかと思う」という声も見られた。
経済的な制度や支援
経済的な制度や支援については、「時短でしか働けない人への金銭補助」「勤務時間が減ってもその分を助成金が出る制度があったらいいなと思います」といった意見が寄せられた。さらに、「育児に関わるお休みで手当てがでるようにしてほしい。本当は子供のために休みたいが、休むと手取りが減るため半ば無理やり登校させた事が何度かあったため」という実情を訴える意見もあった。
その他の制度や支援
その他の制度や支援については、「制度だけではなく周りの協力も必要不可欠だと思います。制度があっても周りの方へ配慮して、引け目を感じながら仕事したり頑張りすぎてしまうママさんも見てきました。子供がいない方で代わりに働いてくださる方の支援や研修等もあると心が楽になるのかなと思います」という声が寄せられた。また、「現場の人手が足りないので休みや時短を選択しにくい。制度や支援については思いうかばないが、人員の補充が1人でもあれば柔軟な働き方ができるのにと思う。日によっては1人でも欠員がでたら仕事が回らないので人手不足を解消してほしい」という声も見られた。