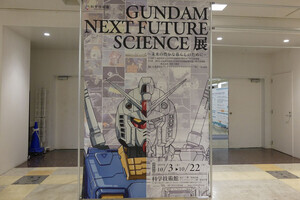日本製薬工業協会(製薬協)は、東京都千代田区北の丸公園内にある博物館「科学技術館」3階の常設展示室「くすりの部屋 -クスリウム」に、新たなコンテンツコーナーを新設。これに伴い、3月21日~23日の期間、くすりの研究者やくすりにまつわるさまざまな知識を学ぶ小学生親子向け体験型イベント「製薬協 クスリウム研究室」を実施した。3月21日には「初日メディア発表会」が開催。当日は製薬協会長上野らが登壇し、新規の常設展示の除幕式などが執り行われた。
薬の知識を体験型ゲームで学ぶ
本会には日本製薬工業協会の会長・上野裕明氏、理事長・木下賢志氏、専務理事・森和彦氏、公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館の代表理事・専務理事である吉田忍氏が登壇。新たな常設展示「ミクロアドベンチャー くすりの旅」のテープカットセレモニーが執り行われた。
製薬協の上野会長は、「2016年、製薬協は常設展示室としてくすりの部屋 -クスリウムを開設させていただきました。その後、2020年に改装しまして、今回新たに少し装いを変えてお披露目となります」と挨拶。
新たなに3つの展示を常設することを紹介した。その目玉となる「ミクロアドベンチャー くすりの旅」は、体重を前後左右にかけて画面を操作するクイズゲーム。クイズは全8問の中からランダムで4問ほどが出題され、クイズを通じてオーバードーズの危険性など学べる。
「薬は一人ひとりの生活に身近な存在である一方、科学技術館で展示されている他産業の展示物などと比較すると、どうしてもビジュアル的にわかりにくい面もあります。また、お薬の研究開発にはとても長い時間を要し、次の世代へバトンをつないで行くことも大切になります」(上野氏)
新規常設展示では、正面からフラッシュを焚いて撮影すると、背景のパネルに文字などが浮かび上がる仕掛けが施されたフォトスポットのほか、製薬のプロセスを学ぶパズルの展示も新たに用意した。
「さまざまな新薬によって、これまで治らなかった病気も治るようになってきましたが、治療が困難な病気もまだまだ多くあります。そうした病気に対して医薬品でチャレンジすることの大切さやおもしろさを、お子さんや親御さんに感じていただく機会に、これらの展示が少しでもお役に立てれば嬉しく思います」(上野氏)
科学技術館は1964年に開館し、昨年60周年を迎えた科学技術館の吉田氏はその挨拶で、「2024年度、当館の入館者数は約46万人の見込みで、そのうち27万人、約60%弱が小学生以下の子どもたちです。将来、科学者・研究者などお薬に関する仕事に少しでも興味を持っていただけるきっかけになれば幸いです」と、述べた。
クロマトグラフィー実験を実演
3階の常設展示の案内後は、3月21日~23日に開催された体験型イベント「製薬協 クスリウム研究室」のイベント会場である4階「D室特設会場」へ移動。実験ショーの内容や実演が行われた。
「製薬協 クスリウム研究室」は常設展示のクスリウムと関連した内容の体験イベントで、常設展の内容をより深く学べる構成となっている。
パネル展示では創薬のプロセスや、薬の発明などに関わった過去の偉人とその功績を紹介。製薬工場で薬ができるまでのプロセスをすごろくにしたゲームコーナーも用意した。
「薬の分子パズル体験」では、ポケモンにアイテム名としても登場する「ブロムヘキシン」(去痰剤のブロムヘキシン塩酸塩)など4種類の薬の分子を紹介し、分子模型を触って立体的なモデルをつくってみることができた。
また、1846年創業のドイツの顕微鏡メーカー・カールツァイス社の協力で電子顕微鏡の展示コーナーも設けられていた。カールスツァイス製の顕微鏡は、細菌学者のロベルト・コッホが結核菌やコレラを発見した際に使用したことなどでも知られている。
さらに特別イベント「製薬協 クスリウム研究室」では、「カラフル体験! 『くすりをみつける』」「しゅわしゅわ! 『酸とアルカリ』」と題した2つの実験ショーも行われた。
前者は、実際に創薬の研究室や現場でも用いられているクロマトグラフィーという分析手法をわかりやすく学ぶプログラム。後者は中和反応を体験しながら、胃酸や腸液など体内の酸/アルカリの知識やカプセル剤など、薬に関連した知識を学ぶプログラムとなっている。
本会では、この3つの実験のうち薄層クロマトグラフィー(TLC)の実験ショー「カラフル体験 薬を見つける」が実演された。
クロマトグラフィーは物質の分子同士の吸着力の差を利用し、混合物を分離する分析手法。サンプルに含まれる複数の成分の分子と、プレートの分子のくっつきやすさ/くっつきにくさを利用して、混合物を分離する。
この実験ショーではニンジン、ウコン、ホウレンソウから抽出した液体がサンプルとして用意し、プレートの3箇所それぞれにスポッティング。トルエンとアセトンを4: 1で混ぜた液体の入った瓶に入れ、オレンジ色をした「カロテン」の有無などを調べる。
プレートが液体を吸い上げて、上方へと染み込んでいくにつれて、プレートの分子とくっつきにくい性質を持つ分子はプレートの上方へとスムーズに押し流される。逆にプレートとくっつきやすい成分の分子は上に押し流されにくく、その速度差によって分子の種類ごとに分けられるのだそうだ。
クロマトグラフィーによる実験は、蛍光灯と肉眼では確認できなかった物質の特定の手がかりになることもポイント。紫外線を当てることで見え方が変わり、ウコンやホウレンソウのサンプルにも様々な物質が含まれていることが、ビジュアル的に理解できる。
今後は3階の常設展示「くすりの部屋 -クスリウム」で実験ショーを公開する予定だという。