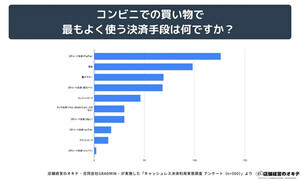丸井グループは3月21日、クレジットカードのエポスカードの新ラインナップとして「ミュージアム エポスカード」を発表した。国立美術館、国立文化財機構、国立科学博物館と連携し、それぞれが運営するミュージアムのコレクションをデザインしたカードを発行する。
決済に応じて付与されるポイントの一部を各団体に寄付する仕組みで、普段のカード利用だけで好きなミュージアムを支えられる仕組みとして、丸井グループでは「好き」を応援するカードと位置づける。
発行は21日から。年会費は永年無料で、国際ブランドはVisaとなっている。券面デザインは、3つの法人それぞれ4種類ずつ、計12デザインが用意される。利用額応じて獲得するポイント0.5%(200円につき1ポイント)のうちの0.1%が、選択したデザインの法人に寄付される。さらに、新規入会時にはエポスカード側が1件につき1,000円を寄付する。
-

発表会には各法人の代表も参加した。写真左から丸井グループ・相田昭一氏、国立美術館・東京国立近代美術館長の小松弥生氏、丸井グループ 新宿マルイ・三橋真唯氏、国立文化財機構・水田功理事、国立科学博物館副館長・栗原祐司理事
新宿マルイ店員の「好き」がカードに
ミュージアム エポスカードは、「好き」という感情や価値観を重視し、それを事業の中心に据えることで、新しい市場を創造しようとする取り組みの一環として生まれたカード。
調査では、「普段から節約するものとお金をかけるものを分けている」という回答が68%に上り、「とにかく安くて経済的なものを買う」という回答の28%を大きく上回った。これは、「趣味やコレクションなどこだわりたいものに消費を惜しまない、コスパ(コストパフォーマンス)とは正反対の傾向が見られる」と丸井グループ常務執行役員CDOの相田昭一氏は指摘する。
こうした「メリハリ消費」について、「『好き』が駆動する経済」と丸井グループでは位置づける。それは「コスパ経済の対極」(相田氏)であり、「好きなものに対すると価値と感情を重視する経済」だと相田氏は強調する。
この新たな市場においてプラットフォームとして位置づけるのがクレジットカードで、それが「『好き』を応援するカード」の発行に繋がった。「「好き」と事業を繋げ、幸せと利益の両立の実現を目指した」(同)という。
これまで、例えばミュージアムでは先行事例となっている愛知県・徳川美術館の「とくびぐみエポスカード」、主に障害のある作家のアートをプロダクト化しているヘラルボニーと協業した「ヘラルボニーカード」、アニメやキャラクターを応援するカードなどが発行されている。
2024年からは「オンリーワンカード」として自分のペットの写真や自分が撮影した山岳や自然の写真をカード券面に印刷して唯一のカードを作れるサービスも開始。こちらも動物保護団体や山岳保全団体に寄付する仕組みを活用したことが「支持されている要因」と相田氏は言う。
こうして発行されてきた"「好き」を応援するカード"は、2024年9月までの段階で88企画が稼働し、101万人の利用者を獲得してきた。それ以降も企画は拡大。すでに90を超えているそうで、今回新たに3つの団体との共創が決まり、3企画が追加された形だ。
さらにこの企画を推し進めて、同社の従業員と利用者が共通の「好き」を通じて結びつくことで新たなビジネスが創出できることを期待し、全社員が参加するコンクールを同社では実施。
すでに2回のコンテストが開催され、延べ210人の従業員が提案したコンクールでは、正社員だけでなくアルバイトや長期インターンシップの学生なども参加。その第1回目のコンクールで提案されたのが、今回のミュージアムとの共創だった。
提案をしたのは、新宿マルイの三橋真唯氏。同店で店内販促のPOPのデザインなどをしているそうで、普段、エポスカードの企画に携わっているわけではないという。以前から、ミュージアムに親しんでいた三橋氏は、「人生に迷ったときなどに、コレクションや展示から新しい視点をもらい、心を動かされる経験を何度もしてきた」と話す。
-

第1回のコンクールで提案され、1年間かけて商品化に繋げたミュージアム エポスカード。「1000年後 2000年後 にまもり、つなげる」というキャッチフレーズについて、国立科学博物館の栗原理事は「我が意を得たり、我々の目指している方向性と一致している」と称賛していた
そうした知識を与えてくれて、支えてくれたミュージアムに対する強い思い入れと、受け取ったものを少しでも返す機会だと考えて提案したという。こうした思いがミュージアム エポスカードとなり、国立美術館、国立文化財機構、国立科学博物館という3法人との共創となった。国立文化財機構の水田功理事は、「職員から、三橋さんのミュージアムに対する深い理解と熱い思いに心を大きく動かされたと聞いた」と話しており、三橋氏の熱意、つまり『好き』の気持ちが共創に繋がっていることが伺えた。
三橋氏は、「同じようにミュージアムが好きという人が気軽に支え合える仕組みを作ろうとした」と話す。国立科学博物館の栗原祐司理事・副館長は、「国からの予算が減ってきていて、なんとか外部資金を稼がなければいけない」と苦しい現状を吐露。エポスカードのメインターゲットが20~30代だと聞いており、なかなかミュージアムに足を運ぶ時間のない層と一致しているとのことで、そうした層に訴求できて支援をしてもらえる提案はありがたいと語る。
国立近代美術館の小松弥生館長は、ミュージアム エポスカードを使うたびにミュージアムに行こうと思ってくれて、カード券面を見せることで、デザインに興味を持ってもらって、ミュージアムのことを拡散して知ってもらうという社会貢献もあると指摘する。
相田氏によれば、この「好き」を応援するカードのLTV(顧客生涯価値)が「非常に高い」という。好きなものであればこそ利用も増えるし、他人にアピールすることも多いというわけだ。現時点ではゴールドカードもないが、「近しいものは必要なので検討している」と相田氏は述べる。
今回のデザインは、三橋氏が提案し、各法人とそれぞれ相談しながら決め、それぞれが所蔵する美術品や文化財、標本・資料などから厳選したという。例えば国立美術館はクロード・モネの「陽を浴びるポプラ並木」などの絵画を、国立文化財機構は遮光器土偶や埴輪 踊る人々など、国立科学博物館はフタバスズキリュウや筑波実験植物園などを選んだ。
さらにオリジナル会員特典として、入会後3カ月以内に税込3万円以上の利用があれば、選んだ券面デザインごとのミュージアムをイメージした特典がプレゼントされる。国立美術館は「鑑賞」をコンセプトに作品をコレクションしたアクリル8連キーホルダー、国立文化財機構は「実用」としてマグネットしおり3枚セットを、国立科学博物館は「体験」として自分で割るジオードセットが用意される。
なお、ミュージアム エポスカードは1人1枚の発行となるため、例えばコレクション的に「12デザイン全てを保有する」ことはできない。ただ相田氏は、そういった要望はあるとして、今後何らかの方法を検討していく考え。また、現在は12種類のデザインだが、ユーザー数の増加や周年記念といったタイミングで増やすことも検討していくという。
今回のミュージアム エポスカードは、社内コンクールから生まれた第1号の製品。同社では「好き」を応援するカードを今後もさらに拡大させていく予定で、社内コンクールも継続させていく。相田氏は、社内だけでなく外部にも広げてコンクールを開催していきたい考えも示している。