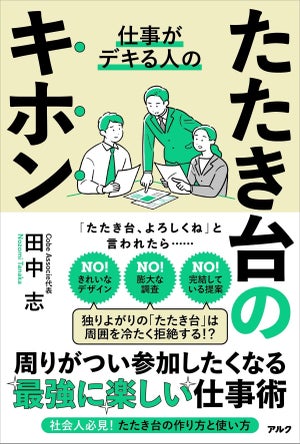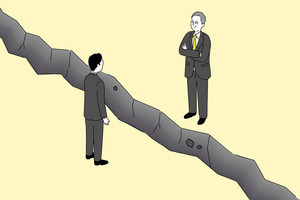電通のプランニング&クリエイティブユニット「電通若者研究部(電通ワカモン)」は、7月24日、メディア関係者に向けて「Z世代の仕事観とチームマネジメント」をテーマにしたセミナーを開催。
「若い部下をどう指導していいかわからない」「指導しても結果が出ない」と悩むリーダーも多い中、Z世代の若者の仕事観と「これからのリーダーに求められる7つの思考」を披露した。
■若者の仕事観「合理的ルートで幸せになりたい」
電通若者研究部は、若者を「未来の兆しの象徴」と捉え、大学生と高校生を中心として、10年以上にわたって若者研究を続けてきた。そこから導き出した若者の仕事観が、「合理的ルートで幸せになりたい」というものだ。
今の若者がざっくりと描いている人生のゴールは、「幸せに暮らしたい」。「どんな企業に就職しても絶対の安泰はない」とわかっているからこそ、冷静な視点を持ってリスクヘッジをしながら“合理的”にやりがいにも挑戦しているという。
若い部下の考えや行動を理解するためには、次のような若者の仕事観を知っておくことが欠かせない。
「ワークinライフ」が初期設定
仕事は人生の一部にしかすぎないと考える「ワークinライフ」が初期設定。みんなが目指す「正解」や画一的な「幸せのかたち」がなくなっている中、具体的なゴールは見えていなくても、「幸せに暮らしたい」という気持ちだけはある。
「就職した企業での仕事にやりがいを感じられなかったら、あなたはどの程度で退職すると思うか」という質問に対し、実に8割以上の大学生が「3年以内」と答えており、今いる場所で無駄なく・確実にスキルアップ・キャリア構築したいという意識が強い。「石の上にも三年」というが、むしろ「三年も待つのはもったいない」との心理がうかがえる。
「複業」「柔軟な働き方」志向が顕著
「複数の仕事・肩書を持って働いていきたいか」という問いに対し、「そう思う」「ややそう思う」と回答したのは10代で47.4%、20代で42.9%にのぼった。「組織のためではなく、自分の人生の充実のための労働」という意識が強いため、さまざまなスキルを得ながらやりがいを探せるのは効率がいいという意識が見て取れる。いつ何が起こるかわからない時代、「収入源の分散が安心につながる」との考えもあるようだ。
■「心地いいチーム」をつくる「フラット・マネジメント」
「若者の仕事観」を踏まえ、これからのチームや組織のマネジメントに必要な思考システムとして電通若者研究部が提唱するのが「フラット・マネジメント」だ。
今の社会において「マネジメントされる側」にいる人の多くが若者、つまりは「若い価値観を持っている可能性が高い人たち」である。だからこそ、時代の気分を一番知っている若者の価値観を起点としたマネジメント理論は、世代間ギャップ解消の一助となるのではないか。
最近のマネジメント層の悩みとして、「部下とのコミュニケーションで気をつけないといけない点があるのはわかるが、何に気をつけたらいいのかわからない」あるいは「どんなに指導しても結果につながらない」といったものがある。
これに対し、電通若者研究部の説田佳奈子氏は、「『これさえやればいい』というアクションなどないし、アクションだけをやればいいわけではない。今の若者は本質を見抜いてしまうので、『どのような思考に基づいて、どのような判断を下し、なぜその行動に至っているのか』がしっかりとリンクし、軸として言動の基盤となっていることが重要」と語る。
■これからのマネジメントに必要な7つの思考とは?
この「思考と判断、行動がリンクし、言動の基盤となっている」状態を作り出す「フラット・マネジメント」に必要な思考として、電通若者研究部が挙げているのが次の7つだ。
【1】固定観念より新しい価値観
時代とともに価値観が変化していく中、自分にとっての「常識」は部下にとっての「非常識」であることを自覚し、時代に適応していく意識をもつことが重要。そのために、古い慣習やステレオタイプを押しつけるのではなく、「すり合わせる」という意識で部下と向き合う。
【2】会社の都合より部下自身の「納得解」
今は個人が望む自分のあり方を実現できる時代。部下のモチベーションや動かし方においても、部下が思う“納得できるやる意味”=「納得解」を一緒に考えることで、「やらされ仕事」をゼロにすることが大事になる。
【3】費用対効果より時間対効果
「タイパ」が流行語となったように、時間対効果が重視されるようになっている。上司は「自分の時間は有限である」という今の時代の思考を理解した上で、部下と向き合う必要がある。具体的なアクションとして、労働時間の長さよりも生産性で評価する、明確な議題や目的のない会議はやめるなどがある。
【4】大きなビジョンより小さなアクション
今の時代において、具体的なアクションがない口だけの上司は部下の信頼を得られない。良いチームを構築するためには、言行不一致はNGだと心得て、「What to say(何を言うか)」より「What to do(何をするか)」を大事にする必要がある。
【5】上から目線より横から目線
今の若者は、上から目線での指導や強制的な物言いに抵抗を感じやすいため、リーダーのあり方を根底から考え直す必要がある。「上司だから偉い」と勘違いせず、部下からも学ぼうとする姿勢を持つことが大切。
【6】嫌われない建前より丁寧な本音
「部下を怒ってはいけない」という風潮が高まっており、若い部下を腫れ物に接するように扱う上司もいるが、部下を指導する上で「注意する」ことは避けられない。「配慮」は必要だが「遠慮」は不要。“怒る”と“叱る”の違いを理解し、本音で部下と向き合うことが重要。
【7】リッチキャリアよりサステナブルライフ
価値観が変化し続ける時代、リーダーに求められているのは、自分と相手の気持ちを尊重する姿勢で未来を見つめること。「違い」を認め、「互いの成功」を思案するスタンスで接することが必要で、お互いがWin-Winになるバランスを取り続けることで、チームとして成長できる。
説田氏は「今は、さまざまな価値観や個々人の思いに向き合ってチームをマネジメントしていかなければならない複雑な時代。これからのリーダーに求められるのは、多様な価値観に合わせて柔軟に思考を変えていく姿勢だと考えている。ぜひ多くのリーダーにフラット・マネジメントを実践していただきたい」とコメントした。
これらの内容をより詳細に取りまとめた書籍『フラット・マネジメント「心地いいチーム」をつくるリーダーの7つの思考』も発売されている。従来のリーダー像からの脱却を提唱するフラット・マネジメントは、若い部下との接し方に悩むリーダーにさまざまな気づきや発見をもたらしてくれそうだ。