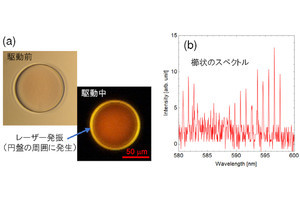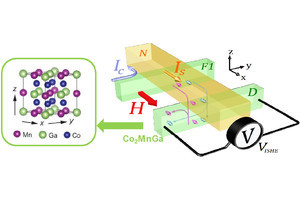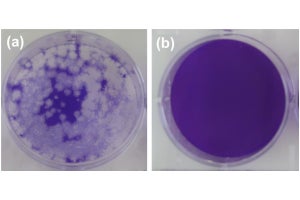物質・材料研究機構(NIMS)、大阪大学(阪大)、北海道大学(北大)の3者は3月5日、代表的な超伝導体であるインジウムを原子レベルの厚さまで削った超薄膜結晶を用いることで、強い磁場でも超伝導が破壊されない新たなメカニズムを発見したと共同で発表した。
同成果は、NIMS 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 表面量子相物質グループの内橋隆グループリーダー(北大大学院理学院 物性物理学専攻 客員教授(連携分野教員)兼務)、同・先端材料解析研究拠点ナノプローブグループの吉澤俊介主任研究員、東京大学 物性研究所の矢治光一郎助教(研究当時/現・NIMS 先端材料解析研究拠点 シンクロトロンX線グループ主任研究員)、阪大大学院 工学研究科 物理学系専攻の坂本一之教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
超伝導現象は、低温において物質の電気抵抗が消失する物理現象であり、量子力学の状態が巨視的なスケールで現れたものだ。MRIやリニアモーターカーの推進システムなど、超伝導はすでに多くの応用例があるが、実は課題もある。超伝導は、磁場によって容易に壊されてしまうという点だ。そのため、たとえばMRIに利用されている超伝導マグネットには、特別に処理が施された材料が使われ、自らが発生する磁場によって超伝導が壊れないよう工夫がされている。
一方で近年の量子技術の発展によって、超伝導体と磁性体を組み合わせた「量子マテリアル」の開発が重要になってきている。特に、次世代の量子コンピュータの素子として脚光を浴びている「トポロジカル超伝導体」を実現するには、超伝導体-磁性体ハイブリッド構造を採用することが有望視されているところだ。
トポロジカル超伝導体とは、連続変形に対する不変量が存在するというトポロジカルな性質を持つ超伝導体のことをいう。その特徴は、その物質中に発生する超伝導電流の渦中心には、「マヨラナ状態」と呼ばれる特異な状態が存在することだ。これを利用することで、量子情報を長時間保持して複雑な演算をすることのできる革新的な量子コンピュータが実現できると期待されているのである。
しかし、超伝導体と磁性体を接近させるとその強い「磁場」(磁気的な相互作用)により超伝導が壊されてしまう。そのため、強い磁場でも壊れることがなく、しかもデバイスの作製に適した薄膜状の超伝導材料の開発が望まれていたのである。
そして最近になり、グラフェンに似たある種の結晶構造を持つ層状の超伝導物質が、磁場に対して頑強であることが判明。ただし特殊な物質であったため、より一般的な超伝導物質にも適応可能な新しい指導原理の発見が望まれていたのである。
以前に共同研究チームは、代表的な超伝導体であるインジウム(原子番号49の金属)の薄膜を、その結晶性を保ったまま極限まで薄くし、原子レベルの厚さの2次元結晶を作製したことがある。そして、このような究極的な薄さにおいて、超伝導が壊れないということは、たとえ磁場のない環境であっても共同研究チームのメンバー自身が驚くほどであり、それを世界に先駆けて実証することに成功した。
そして今回、その実験技術を発展させ、極低温・強磁場の環境下においての測定が実施された。すると、超伝導が特定の方向の磁場に対して頑強になることが発見されたのである。
-
(a)超伝導転移を示す面抵抗(単位面積当たりの抵抗値)の温度依存性と、磁場依存性。(b)複数の試料を用いて測定された臨界磁場の温度依存性。臨界磁場は従来の理論値(5.5~5.8T)を超え、十分に低温では16~20Tに達することがわかる。比較のため、試料面に垂直方向に磁場を印加した場合の臨界磁場(10倍に拡大)も示されている (出所:共同プレスリリースPDF)
これは、磁性体から受ける「磁場」(磁気的な相互作用)に対しても頑強になることを意味するという。以前から考えられていたメカニズムによると、このインジウムの原子層結晶の臨界磁場は5.5~5.8Tだが、今回得られた臨界磁場はこの値を大きく超え、最大で16~20Tに達すると見積もられた。すなわち、臨界磁場がおよそ3倍に増強されていることが確認されたのである。
そこで、共同研究チームは世界最高クラスの性能を有する光電子分光装置と第一原理計算を駆使して、この原子層結晶の電子状態とスピン状態の詳細な分析を実施。その結果、電子の運動方向に依存してスピンの向きが異なり、電子の運動方向が一回転するとスピンの向きも一回転するような特殊な状態を取っていることが判明したとする。
-
光電子分光測定と第一原理計算により得られた試料中の電子の運動量(速度に比例する量)とスピンの向きを示すデータ。図の色の濃い部分に電子が多く存在することが示されており、中心からの赤い矢印はその場所における電子の運動方向が、青い矢印はスピンの向きが示されている。電子の運動方向が回転すると、スピンも回転することがわかる (出所:共同プレスリリースPDF)
この状態は、いわゆる「ラシュバ型スピン軌道相互作用」が存在していることを示しているという。ラシュバ型スピン軌道相互作用とは、電子のスピンと電子自体の直進運動との間に働く相互作用の一種だ。2次元的な性質を持つ試料においては、試料面内方向にスピンを向かせる働きがある。今回のインジウムの2次元結晶試料においては原子レベルの厚さしかないため、試料基板面に対して垂直方向のポテンシャル勾配(電場)が大きくなり、この相互作用が現れるのだという。
またこのような状況では、わずかに残っている不純物や欠陥によって電子の運動方向が曲げられると、スピンの方向もそれにつれて回転してしまう。このような現象が実際に試料中で起こっていることが、電子の運動方向の曲がりとスピンの「ひねり」がほとんど同じ頻度で起こっていることから確認された。
-
(a)今回の研究における、電子の運動方向が変化する度にスピンが回転することが表された模式図。(b)先行研究のスピンが磁場に対して垂直方向に固定されることが示された模式図 (出所:共同プレスリリースPDF)
このスピンの「ひねり」は、超伝導状態になった電子にとって大きな意味を持つという。すなわち、磁場に対してスピンの向きが頻繁に変わるために、ある時にはエネルギーを得してもまたある時にはエネルギーを損するので、平均するとエネルギーの損得はほとんどなくなる。
この損得がほとんどなくなるということが、とても重要だ。今回の試料のように薄い素材において超伝導が壊れてしまう原因は、磁場によって電子のエネルギーが変化してしまうことだ。つまり、エネルギーの損得がほぼなくなるということは、強い磁場があっても超伝導が壊れないということになるのである。
実はこのような効果は、古くから知られていたという。ただし実際に原子レベルの厚さの結晶が作製され、スピンが強制的にひねられる状況が作り出されたことで、同じメカニズムであっても従来比で数十倍から1000倍程度も強く働くことが今回明らかとなったのである。
今回超伝導体として用いられたインジウムはごくありふれた物質であり、特殊な結晶構造や強い電子間の相互作用などは持っていない金属だ。すなわち、このメカニズムは汎用性の高い一般的な原理だということができるという。
また共同研究チームによれば、最近報告された高い臨界磁場を持つ層状の超伝導物質との比較も、科学的に興味のあるところだとする。どちらもスピンの向きが電子の運動方向で決定されることを起源としているが、先行研究ではスピンが一方向(磁場に対して垂直方向)に固定される静的な効果が原因だ。それに対し、今回の研究ではそれとはまったく異なり、スピンがひねられる動的な効果が原因である。
共同研究チームは今後、今回の成果を応用して、より高い臨界磁場を持つ超伝導薄膜の開発を行うとしている。すでに予備実験では、別の種類の超伝導体を用いることで、磁場に対してさらに頑強な性質が観測されているという。
また、実際に原子レベルの厚さの超伝導体と磁性体からなるハイブリッド型のデバイスを作製し、トポロジカル超伝導体を実現するとしている。トポロジカル超伝導体は、次世代量子コンピュータの実現に欠かせない量子マテリアルであり、現在世界的な研究開発が進んでいる。
トポロジカル超伝導体はその作製方法にいくつかの提案があり、すでにその存在は確認されているが、多くは特殊な材料の組み合わせが必要だ。今回得られた成果はより一般的な材料でトポロジカル超伝導体を実現する道を拓くものとしている。