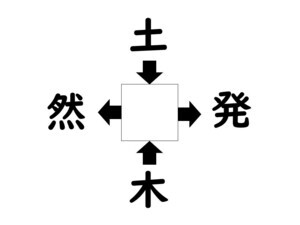◆本記事はプロモーションが含まれています。
【この記事のエキスパート】
住まいづくりナビゲーター/一級建築士・インテリアコーディネーター:神村 さゆり
住宅メーカー、ゼネコン設計部、設計事務所等で約300棟の新築設計実績と現場代理人女性としては希少な現場監督経験を生かしリフォーム物件も約70棟手がける。
住宅や暮らし方、環境整備をテーマに、これまで一般企業研修・公的機関・学校等にて講師としてこれまで述べ5000人以上を指導。
整理収納アドバイザー、ルームスタイリスト資格認定講師として800名余の資格者を認定。また資格試験対策として二級建築士やインテリアコーディネーターの受験指導も行っている。手描き図面やイラストでのプレゼンにも定評があり、多くの文具を試してきた。
多趣味が高じて醗酵教室や手抜き家事教室を開催し好評を得ている。
子ども3人。A型・獅子座
ガムテープよりも剥がしやすい養生テープ。台風対策や引越し時の荷物の梱包など、DIYに欠かせないアイテムです。この記事では、住まいづくりナビゲーター・神村さゆりさんおすすめの養生テープをランキング形式で発表。ユーザーイチオシの商品も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
養生テープの特徴
【エキスパートのコメント】
養生テープの一番の特徴は剥がせることです。キズを付けたくないところを守るためや、梱包を止めることなどに使われます。ほかにはペンキのはみ出しを防ぎたいときなどに予め貼っておくこともあります。ガムテープのように糊(のり)跡が残ることはほとんどありません。
マスキングテープも養生テープの仲間ですが、近年では様々なデザインもあり、剥がしやすいという利点をうまく活用しています。
養生テープとガムテープの違いは?
養生テープはガムテープよりも剥がしやすいというメリットがあります。また、切れやすいので梱包作業をするときなどに便利です。また、ガムテープと違い、剥がしたあとのベタつきもありませんし、貼った箇所の材質が剥がれることもありません。
デメリットとしては、ガムテープよりも粘着力が弱いので剥がれやすいところです。養生テープで固定したいときなどは多めに使用することをおすすめします。
養生テープの選び方
梱包やDIYだけでなく、日常でも使いやすい「養生テープ」。住まいづくりナビゲーター・神村さゆりさんに取材をして、養生テープの選び方を教えていただきました。目的に応じた養生テープの素材や、幅をよくチェックすることが大切です。ぜひ養生テープ選びの参考にしてください。ポイントは下記の5つ。
【1】素材から選ぶ
【2】テープ幅から選ぶ
【3】色で選ぶ
【4】粘着タイプから選ぶ
【5】特徴から選ぶ
上記のポイントをおさえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】素材から選ぶ
養生テープには大きく2種類の素材があります。素材によって特徴があるので、購入前に確認してください。一般的にマスキングテープと呼ばれる"紙"と表面がつるつるした"ポリエチレンクロス"の2種類です。
剥がしやすさで選ぶなら「紙素材」のマスキングテープ
紙素材(マスキングテープ)は比較的粘着力が弱いので、壁紙や貼り付け跡を残したくない家財などへの使用に適しています。クロス素材にも剥がしやすい商品はありますが、剥がしやすさと跡の残りにくさで選ぶなら紙素材がおすすめです。
紙素材の養生テープなら長時間貼っていてもかんたんに剥がれるので、下地の状態もキープできます。
粘着力が強い「ポリエチレンクロス素材」
縦横に細かいラインが入っているクロス素材は、家具の固定や塗装時の保護用に適しています。基材にはポリエチレンなどが使われているため、紙素材よりも粘着力は強いです。
耐久性と耐水性も高く、塗料がテープに浸透する心配がありません。水回りの周囲や、キッチンの壁紙にも問題なく使えます。強度を重視するなら、クロス素材の商品を選びましょう。
【2】テープ幅から選ぶ
養生テープには幅が広いタイプや狭いタイプがあります。使用する目的に合わせて選ぶことが大切です。
「25mm幅」は仮止めに便利
テープ幅の狭い25mm幅は、主に物を移動させるときに部品が落ちないように止めたり、収納ケースのフタを止める目的で使うことが多いでしょう。また、DIYなどでシートを貼るときの仮止めとしても使用されます。
「50mm幅」は段ボールとの相性◎
もっとも一般的なテープ幅の50mm幅は、引っ越し作業で大活躍する幅です。段ボールのフタを閉じるためや、養生シートの取り付けにも適しています。幅が広いので止めても外れにくいタイプです。
「100mm幅」は屋外での使用に最適
養生テープの幅のなかでもっとも幅広い100mm幅のテープは、幅が広いぶん粘着力も一番強く、屋外での作業でどうしても止めておきたい場所に使うとよいでしょう。風が強くシートなどが飛ばされる可能性のある場所で活躍してくれます。
また、屋外に使う場合、防水性もチェックしておくとよいでしょう。
【3】色で選ぶ
養生テープは色々なカラーがあります。緑や白、黒、透明などがありますが、色によって粘着力が変わることはありません。
引っ越し作業やDIYをするときに養生テープを使う場合は、作業中どこに仮止めをしたかハッキリわかるように、作業するものとは対照的な色にしたほうがよいでしょう。
【4】粘着タイプから選ぶ
養生テープは粘着力の強さで選ぶこともできます。貼った場所に跡が残らない程度の粘着力から強粘着力まで様々です。
「弱粘着タイプ」は糊が残りにくい
弱いといっても粘着力がほとんどないということではありません。テープを剝がした跡にテープの糊が残りにくく、作業がしやすいタイプです。引っ越し作業での仮止めに向いています。
「中粘着タイプ」は床養生向き
弱粘着対応よりは粘着力があるため、部屋の壁などに貼ると糊の跡が付く可能性があります。中粘着タイプは、床の養生など、糊が付いても目立ちにくい場所に向いています。
「強粘着タイプ」は耐久性抜群
強粘着タイプはなかなか剝がれにくいタイプなので、天候の悪い屋外作業のときにぴったり。建築中の家などの塗装養生としても用いられています。プロの職人さんが使う機会が多いかもしれません。
【5】特徴から選ぶ
養生テープには様々な特徴があるタイプがあります。使う場所に合わせて選ぶことが大切です。
「両面タイプ」は固定したいときに便利
両面に粘着剤が付いているタイプです。養生シートやカーペットを床に敷いたりする際、ずれないように固定するために使われることがあります。
「耐性タイプ」は環境に合わせて使いわける
養生テープの中には、耐水性、耐熱性、耐湿性、耐薬品性などの特性を持つものがあります。キッチンの水回りやコンロの周り、屋外での使用のときには、特性に注目して選ぶことが必要です。
選び方のポイントはここまで! では実際にエキスパートが選んだ商品は……(続きはこちら)