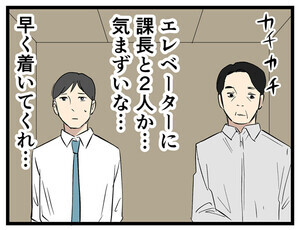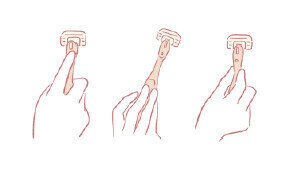◆本記事はプロモーションが含まれています。
【この記事のエキスパート】
思考の整理収納塾代表:田川 瑞枝
思考の整理収納塾代表。
2010年にライフオーガナイザー、整理収納アドバイザーの資格を取得し活動を始める。
大人になっても片づけが出来ないのは、学校で習っていないからだという声を聞き、学生のうちに身に着けておきたい暮らしの整理術を伝えたいと、全国でも珍しい高校での片づけの授業に取り組んでいる。
2016年、片づけのプロの全国大会「片づけ大賞」にて審査員特別賞を受賞。
現在は、研修、講演などの講師活動に加え、WEBサイトのライターとしても活動している。趣味は模様替え。
押し入れの通気性を良くしてくれるすのこ。木製やポリプロピレン製など、素材やデザインも豊富です。また、キャスター付きならベッド下収納になり、ジョイント式ならサイズをカスタマイズできます。この記事では、整理収納のプロにすのこの選び方とおすすめ商品を教えてもらいます。
整理収納のプロに聞きました
押し入れ用すのこの選び方
整理収納のプロ・田川瑞枝さんに、押し入れ用すのこを選ぶときのポイントを3つ伺いました。
【1】素材
【2】サイズ
【3】使い方
上記の3つのポイントをおさえることで、より具体的に押し入れ用すのこを手に入れることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】素材で選ぶ
【エキスパートのコメント】
すのこには、木製品だけでなくポリプロピレンなどの樹脂素材を使った商品があります。それぞれの素材の特徴をふまえながら、使う場所や用途に合わせたすのこを選ぶようにしてください。
<木製>
ヒノキやキリ、スギ、パイン材など天然木を使っているものが多いので、木の特性を理解して選ぶようにしましょう。たとえば、キリは比較的軽めなので、移動や持ち上げる時に力の弱い方でも比較的ラクに扱えます。ヒノキを使ったものは、香りの癒し効果も期待できます。
<樹脂製>
カラーが豊富な商品が多いので、部屋のインテリアに合わせた色を選ぶことができます。他にも、滑り止め加工を施した商品や柔らかい商品もあります。カビが生えることもなく安心して使え、汚れたら水で丸洗いできるので衛生的です。また、軽くて持ち運びしやすいので掃除がしやすいという利点があります。
【2】サイズで選ぶ
【エキスパートのコメント】
最近のすのこはサイズ展開が豊富なので、購入される前には使う場所に合わせたサイズ選ぶようにしましょう。そのためには、あらかじめ使用する場所の寸法を測っておくことをおすすめします。
すのこは、下駄を履かせたように、角材の上に板を打ちつけているので、その角材の分も寸法に入れておくことが重要です。いざ使おうと思ったときに、厚みが邪魔して使用できなかったということのないようにしたいですね。
【3】使い方で選ぶ
【エキスパートのコメント】
使い方によってもすのこの選び方が変わってきます。押入れやクローゼットのなかで使う場合、空気の流れを考えて角材の向きが扉に対して垂直に並ぶように配置します。そのほうが奥まで空気が流れやすくなるからです。寸法がちょうどいいからと平行に並べてしまうと、空気の流れが遮断されてしまい、せっかくのすのこのよさをじゅうぶんに生かせない結果になります。
他にもすのこには、底にすべり止めがついている商品やキャスター付きの商品があり、押し入れだけでなく室内でも活用できます。また、すのこ同士を組み合わせて棚を作ることも可能。どこで、どんな用途で、使いたいのかをしっかり決めてから選びましょう。